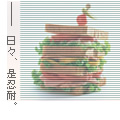| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
―――冗談じゃないわよ。
シャープペンシルを握る佳那子の手が、怒りでプルプルと震える。
―――今頃になって、新規ソフトの開発会議に2人出せ、ですって…!? どこにそんなゆとりがあるって言うのよ!?
「…佐々木」
「何よ」
「せっかくの美人が、台無しになる」
「美人なのはわかってるわよ。少し位崩れた方が世のためよ」
「お前―――それ、マジなのか? それとも謙遜した上でのギャグ? マジなら相当イヤミだぞ」
「―――久保田」
ジロリ、と久保田を見上げ、佳那子は書きかけのスケジュール表を派手に破った。
「私、仕事中なの。一体いつまでそこに立ってる気?」
「これ渡すまで」
ドン! と机の上に置かれたのは、CCレモンのペットボトルだった。佳那子の眉間に寄っていた深い縦皺が、すっと消える。
「…そっか、頼んでたんだったわね」
「般若面みたいで怖かったぞー。さすがの俺も、声かけようかどうしようか迷った位だ」
「私を般若面にする輩がいるのよ。笑顔の私が見たいんなら、そいつに文句を言って」
「中川部長だろ? 全く…お気楽な上司を持つと、お互い苦労するよなぁ…」
久保田は苦笑いをしながら、自分の分のCCレモンの蓋をあけた。佳那子も、バツが悪そうにしながら、ペットボトルを手に取った。
***
佳那子が勤める「株式会社ブレインコスモス」は、元々、大手メーカーと共同開発した金融機関向けシステムを手掛ける会社だった。
元銀行マンだった社長と大手メーカーのシステムエンジニアだった副社長が、それぞれの会社から独立して今から15年ほど前に設立した、比較的新しい会社である。ここ数年は、パソコンの個人ユーザー向けのセキュリティソフトやハードディスク管理ソフトも手掛けるようになった。顧客向けに「コール・センター」などを設けるようになったのも、個人客からの問い合わせが多くなったためだ。
大手メーカーの傘下に入っていることもあり、自社のシステムエンジニアの数はそう多くない。佳那子のいるPC部門は、全部で12人だ。システム部全体の人数は、30人程度だろうか。
部長の中川が最高齢だが、その中川でさえ40代後半である。設立当時からいるシステムエンジニアは大半がUNIX部門の人間なので、UNIX部門だけなら平均年齢もそこそこ高い。が、佳那子のいるPC部門は、やたらメンバー構成が若い。入社4年目の佳那子がチームリーダーなどを任されているのも、同世代の方が言う事を聞くだろう、ということと、世界共通の真理―――男は女に弱い、ということを中川部長が勘案してのことだった。
「なんでシステム部に女性が入ってこないのかしらねぇ…部全体で私一人てのは、あんまりだと思うわ」
佳那子は、眉を寄せつつ、また新しい用紙を机の上に広げた。一番上に「98年2月度スケジュール」と書き込み、ため息をつく。
「しょうがないだろ。求人しても、応募してくるのが男ばっかりなんだから。今年の春も期待できないぞ。俺、入社試験の監督やったけど、システム部希望者は男がズラリと揃ってた」
「あ…そ。なんか、このままいくと私、ただのキツくてうるさい女になりそうで嫌だわ」
「真面目だもんなあ、佐々木は」
と笑う久保田も、企画部PC部門のチームリーダーをやらされている。ただし、久保田の抜擢劇は非常に不真面目だ。25歳以上全員でアミダくじをひかされ、久保田が「あたり」を引いてしまった―――ただそれだけである。後から、全て仕組まれた茶番劇で、どうやっても久保田が「あたり」を引くよう操作されていた、と聞かされた時は、さすがの久保田もキレた。が、電卓2個をぶっ壊したところで和臣に止められ、大人しく始末書を書いてチームリーダーに収まったのだ。
「あんたは楽そうにやってるわよねぇ…同じチームリーダーなのに、何が違うのかしら」
のほほんとした久保田の笑顔を、半ば恨めしそうに横目で見ながら、佳那子はまたため息をついた。
「そりゃーまあ、性格の違いだろ? 俺は人使うのが得意な方だけど、佐々木は何でも自分でやらないと気が済まないタイプだし」
「部長とメンバーの板ばさみになって悩んだりしない?」
「するする。そういう瞬間は、俺だって多分、今のお前みたいな顔してると思うよ」
「今の私?」
「また眉間に皺寄ってる」
指摘されて、思わず額に手をやってしまった。可笑しそうに笑う久保田を一睨みし、またスケジュール表に目を落とした。
「ま、頑張んな。見事采配をふるえたら、今日の飲み代おごるから」
「…今度はどこよ? この間みたいに、指定銘柄ヒット率20パーセント、なんて結果にならないでしょうね?」
「ははは、あの店は失敗だった―――今度は大丈夫。地酒専門店だから」
「…なら、付き合ってやってもいいわ」
―――地酒かぁ…専門店でないと置いてないような、珍しいやつが飲みたいなぁ…。
などと期待をしつつ、佳那子は完全にスケジュール作業に没頭していった。
***
「は? 新春キャンペーン、ですか?」
かなり間の抜けた声で、久保田はそう聞き返した。須藤部長はニコニコと笑いつつ、大きく頷いた。
「そう。年も明けた事だし、まぁ今更大規模な事は無理だけど、せめて秋葉原の大型店を1つ位チョイスして、どーんとキャンペーンを打ちたいんだけどねぇ」
「…お言葉を返すようですが、そういうのは昨年中に企画する内容なのでは…」
「うん、僕もそう思う。けど、実際売り上げ落ちてるしね」
おい。そういう問題じゃねーだろ。
「第一、今、春のキャンペーンに向けて、全員忙しいですし。全小売店にキャンペーン内容浸透させてる最中にもう1つキャンペーンねじ込んだら、小売店側も混乱しますよ」
「うん、僕もそう思う。でも、決算考えれば、3月のキャンペーンだけ当てにするのは危ないからね。1月にもうっといた方が堅いだろう」
いや、だから、そういう問題じゃなくて。
「1月に割ける人員がいない、って言ってるんですよっ!」
「営業からの要請だから。ま、頑張ってくれ」
春の陽射しのような穏やかな笑顔を浮かべる部長が、本物の悪魔に見えた。
***
「ごめんなぁ、久保田。僕も無理だとは思うけど、うちも上部命令だからさ。誰にも振る事できないし、もう命令通り突っ走るしかなかったんだ」
営業部PC部門のチームリーダーが、済まなそうに肩を落とす。彼は、久保田より5つ上の、比較的若手の営業マンである。例のキャンペーンの件は彼から要請のあった話なので、久保田は要望を一応聞きに来たのだ。
「ははは…そちらのご苦労も、もの凄くわかりますよ」
眉を八の字にして、久保田は力なく笑った。
「…で、どういうキャンペーン打ちたいんですか」
「店頭デモかな。なにせ1月も残り少ないから、年末使った販促グッズの使いまわしでもかまわないよ。一番売り上げのいい量販店1店舗選ぶから、大至急、看板とチラシだけは用意してほしいんだ」
話を聞きながら、久保田の頭の中では、無理の利く印刷会社と、倉庫に眠っている使いまわし可能そうな看板の検索がスタートする。
他にもいくつかの要望を聞き出し、席に戻った久保田は、隣に座る和臣の肩をトントン、と叩いた。
「カズ、今週の日曜日って何か用事あるか?」
パソコン相手に、春のキャンペーンに使うチラシの下書きに頭を痛めていた和臣は、キョトンとした顔を久保田の方に向けた。
「無いですけど?」
「秋葉原でデモやる気、ないか?」
「え…えええ!? こんな急にデモなんて、販促物とかどーすんですか!?」
「まぁ、それは任せとけ。とにかく、多少は手が空いていて、しかも物覚えのいい、土日に文句言わずに店頭デモやってくれる優秀な人員が、大至急1名必要なんだよ。システム部にデモソフト借りて、簡単なロールプレイしとかないといけないからな」
「オレなら、別に構いませんけど…優秀かどうかは疑問だし、一人はちょっとまだ不安ですねぇ…」
和臣の顔に、思いっきり不安の色が表れる。それでも、優秀な人材が必要だ、という場面で自分に声がかけられたのは、新人としては結構嬉しい。
「だーいじょうぶだって。俺も裏方として一緒に行くから、トラブル発生すれば俺に言えばいいさ。ただし、そんな事態にならないように、社内ロールプレイだけはしっかりやれよ」
「あ、久保田さん来てくれるんなら、やります」
ホッとしたように、和臣が笑った。
だが―――実は久保田には、店頭デモ中画面がいきなり真っ暗になり、復活方法がわからず困った経験があるのだ。あの時は一人だったので、近所の文具店から厚紙とサインペンを買ってきて、急遽紙芝居仕立ての説明に切り替えて乗り越えた(客にはウケたが、後で部長に散々怒鳴られたのは言うまでもない)。そんな久保田なので、和臣が困って泣きついても、多分役に立たないだろう。
でも、そんな事はおくびにも出さない久保田である。久保田は知っていた。和臣の方が、自分よりはるかにパソコンに詳しい事を。久保田という逃げ道を作っておけば、安心してデモに立つだろうから、トラブルの確率はさらに低くなる。いわば久保田は「精神安定剤」だ。
―――さて、この調子で、芝浦印刷も丸め込みにかかるか…。
久保田は、最も無理なお願いを聞いてくれそうで仕事の早い印刷会社を頭に思い浮かべ、どうやって“お願い”するかな、と作戦を練りだした。
***
定時を過ぎる頃には、週末のデモの見通しもほぼ立った。
―――あぁ、疲れた。早く残りの仕事片付けて、飲みに行きてーなー…。
大きく伸びをした久保田は、そこでふと、そういえば佐々木はどうなったかな、と思い出し、席を立った。
パーティションの向こう側を覗くと、佳那子の頭が見えた。
「おーい、佐々木」
声をかけたら、その頭がピクン、と動いて、佳那子の顔が久保田の方を向いた。その顔を見た途端、久保田の目が丸くなる。
慌ててシステム部に駆け込む。休憩に入っているのか、佳那子以外誰もいなかった。
「お、おい、どうした?」
「…久保田ぁ…」
日頃の女傑ぶりはどこへやら、佳那子はボロボロ涙をこぼしながら、情けない声を出してきた。他の連中には死んだって見せない顔だ。誰もいなくなったので、とうとう我慢できずに泣いてしまったのだろう。
机の上には、白紙状態のスケジュール表。昼に見た状態から1歩も進んでいないのは明らかだ。
「もう駄目…限界超えたわ」
「なんだよ。誰もスケジュール調整つかなかったのか?」
「全然。先輩があんまり文句言うから、部長に直談判にも行ったわよ? でも、部長は何がなんでも2人出せって言うし、みんな仕事で手一杯だし…。上からも下からもプレッシャーばっかりかけられて…あー、もうっ! こんな無茶、実現不可能に決まってるじゃないっ!」
―――うわ、キレてんなぁ、こりゃあ…。
ここまでの状態は久々かもしれない。久保田と2人で飲みに行った時なら多少無いこともないが、他の人間に見られる可能性のある「社内」で泣くなんて初めてだ。やはりチームリーダーの責務が重くのしかかっているのだろう。
「そんなの、一番手が空いてそうな奴にばしーっと命令しちまえよ。全員の意見尊重してたら、お前の身がもたねーぞ」
「…だって…スケジュール上、一番可能性ある奴って、会議になったら毎回寝ちゃう奴なんだもの」
うっ、と言葉に詰まる。真面目な佳那子は、出すからには会議をきっちりこなす人材を出したいのだ。その気持ちはわかる。久保田だって同じ意見だ。
…でも。
「妥協しろ。時には妥協も必要だ」
「―――久保田の口から“妥協”なんて単語聞くとは思わなかったわ」
「俺は、妥協くらい平気だぞ。
「……」
「それに、だ。2人出せ、って言われて、そのうちの1人はお前が出る気でいるんだろ?」
「…そうよ」
「なら、もう1人は
「…それもそうね」
ハンカチで目元を押えていた佳那子が、ようやく同意の言葉を口にする。久保田は、ホッと胸を撫で下ろした。
「わかった。ありがと、久保田。納得いかない人選ではあるけど、大島先輩で我慢するわ」
「大島先輩!?」
ギョッとして、思わず聞き返してしまう。落ち着いてきた佳那子は、先ほどまでとはうって変わった明るい声で、
「ええ、そうよ。大島先輩。会議中眠る上にとんでもないイビキをかくから、周りに迷惑かけちゃうかもしれないけど、まぁ仕方ないわよね」
と続けた。
―――そうとわかってれば、止めたかも…。
一瞬、そう思った。大島先輩のいびきは、会議室の外の廊下でも聞こえるほど、凄まじいものなのだ。会議どころの話ではなくなるかもしれない。
…でも。
「いや、いい人選だ」
ニヤリと笑う久保田に、佳那子は「は?」という顔をした。
―――新規ソフトの開発会議って、確か、議長はうちの須藤部長だったよな。
せいぜい苦労しろ、と、オロオロする須藤部長の顔を思い浮かべて、久保田は笑みを深くした。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |