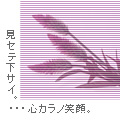| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
瑞樹が進捗日報を書き終えたところで、ちょうど携帯がブルブルと震えた。
午後11時。携帯の液晶ディスプレイに表示された名前を見た瑞樹の表情が、無意識のうちに和らぐ。日報をパタンと閉じ、通話ボタンを押した。
「はい」
『ハル?』
聞こえてきた遠慮がちな、様子を窺うような声に、思わず苦笑してしまう。
「どちら様ですか?」
『……もー。それ、ウケないからよそうよ。声、笑ってるよ』
「だったら毎回“本当にハルかな?”って自信なさげな声でかけてくんなよ。―――今日は早いな。俺まだ会社だよ」
『こっちだって会社だよ。明日までにテストデータ200件揃えろだって』
「どうせいつもの“課長”だろ? ライは目ぇつけられてるんだから、面倒そうな仕事の時は大人しくしとかないと」
『やだ。そんなの、課長に屈してるみたいで癪に障る』
「お前らしいなぁ」
『あ…と、今、電話してて大丈夫なの?』
「オレはもう今日はこれで終わり。帰り支度しながらだけど、いいか?」
『いいよ』
"rai"と初めて電話で話してから、既に1ヶ月ほど経とうとしていた。
が、信じられないことに、2人はまだお互いの名前さえ知らない。
瑞樹は彼女をライと呼び、彼女は瑞樹をハルと呼ぶ。週に2、3回、多い時は毎日、どちらからともなく電話をかけ、話をする。話題は、共通の趣味である映画やコンピューターのこと、仕事のことが多い。政治や経済の話で白熱することもあった。
よく考えると不自然かもしれない。まだ名前も知らない、顔も見たことがない相手と、親しげに電話をするなんて。
でも何故か2人の間では、この習慣化した電話はごく自然なものになり始めている。1日の最後に、他愛もない話で笑いあい議論しあう。時には愚痴を聞いてもらう。そうした会話で、なんとなく1日の疲れが多少消える気がしていた。
『昨日ハル、チャットに来なかったでしょ。結構大変だったんだよ、ミミと遭遇しちゃって』
「へー。あいつ、ライのいるような時間に起きてたのか」
『またコーヒーと緑茶作戦で眠気を乗り切ったみたい。ちょうど久々に"ご隠居"も来ててね。私にべったりするミミに向かって、延々13行にわたってお説教』
"ご隠居"というのは、最近ご無沙汰していたチャットルームの主のことだ。全く違うハンドルネームを名乗っているのに、説教好きなこと、年齢が50代と飛びぬけて上なことが理由で、他のメンバーは勝手に"ご隠居"と呼んでいる。"mimi"の破天荒ぶりには特に厳しいため、"mimi"は彼を非常に嫌っているのだ。
「ははは、ミミも少しは懲りただろ」
『懲りるかなぁ。かえって反発心
「ライが女だってわかれば、ミミ以上に説教されるぞ。“若い娘が、休日にビデオ三昧とは嘆かわしい!”とかな」
事務所のドアを開けながら、瑞樹がからかうようにそう言うと、受話器の向こうの声が一気に不機嫌になった。
『何、その“女だってわかれば”って。ご隠居はハルの倍近く生きてるんだからね? 女を男と間違えるようなバカする訳ないよ』
「それはわかんねーぞ? お前、男のフリすんの上手いからなぁ」
『男のフリなんてしてないってばっ。そりゃ、ネットの怖さ知ってるから、変に女っぽくならないようにはしてるけどさ。ハル、ネット歴長いのに、その位わかんないかなぁ?』
「…すみませんね」
『“もしもし”だけで切られた恨みは深いですから』
「それを言うな―――…っとと」
事務所の鍵をうっかり落としてしまい、チャリン! という音が、誰もいない廊下に響く。慌てて、身を屈めて拾った。
『なに、大丈夫?』
「ああ、ごめん。鍵落とした」
そう言いつつ顔を上げた瑞樹の視界に、薄いピンクのコートが映った。誰もいないと思っていた瑞樹は一瞬息を呑んだが、それが見知った人物だったので、体の緊張を解いた。
そこにいたのは、経理の石原真弓だった。エレベーターホールに佇んでいた彼女は、瑞樹が自分の姿を認めたのを見て、ペコン、とお辞儀をする。
「あー…、悪い、そろそろ電波届かないエリアになるから、電話切る」
事実だが、それより真弓の視線が気になった。やや唐突気味に瑞樹がそう伝えると、ライはそれを不審がる様子もみせず、あっさり答えた。
『うん、了解。じゃ、私も仕事に戻るね』
「無理すんなよ」
『Thanks。じゃね』
完璧な“th”と“s”の発音を残し、ライからの電話は切れた。
***
ライの声がなくなった途端、2人しかいない廊下が怖いほど静かになる。
なんとなく気まずいムードを払拭するように、瑞樹はガチャガチャ音を立てながら事務所のドアに鍵をかけた。
「何、こんな時間に」
「…日下部さんたちと、食事してカラオケ行って、帰ろうとして下から見たら、まだシステム部の所に灯りがついてたから、誰かまだ仕事してるのかな、って」
見ると、真弓は手にコンビニの袋を下げていた。おそらく差し入れのつもりだったのだろう。
「俺、もう帰るけど」
「じゃあ、駅まで一緒に、いいですか?」
「…どうぞ」
ニコッ、と笑うと、真弓はエレベーターの下矢印ボタンを押した。最上階の番号を指していたエレベーターのランプが、だんだん若い番号に降りてくる。5階まで降りてくるのに、それなりの時間がかかる。2人きりのエレベーターホールは、居心地が悪かった。
居心地が悪いのには、実は理由がある。真弓からは昨日、いわゆる“告白”を受けていたのだ。それまで石原真弓という名前すら知らなかったので当然断ったが、真弓は「彼女になれなくてもいいです。好きでいさせて下さい」と言って笑ったのだ。
「成田さんの自然な笑顔って、初めて見ました」
エレベーターを待つ間、唐突に真弓がそんな事を言った。
「そうか?」
「ええ。成田さんいつも、経理に来る時って、笑うとしたら作り笑いの時だけですから」
―――それはしょうがないだろ、経理の女たち、うざったいのが揃ってるんだから。
内心そう思いながらも、出てくる言葉は極々短い。
「そんなつもりじゃないけど」
「本気で怒ってるのも見たことないし」
ちょうどそこに、エレベーターが到着した。チーン、という音と共に扉が開く。
―――本気で怒るほどの関心も無いし。多少ムカつく程度なら、変に怒ってギャンギャン吠え付かれるよりは、無視して過ごした方が利口だし。本気で怒った俺知ってんのは頼子さん位か…あ、もう辞めたんだっけ。
エレベーターに乗り、1階のボタンを押しながら、瑞樹はそう考える。が、やっぱり出てくる言葉は極々短い。
「そうかな」
「経理の女の子の間では“ポーカーフェイス”で通ってますよ」
「…ふーん」
いちいち顔色変えてたら疲れるだろ、と心の中で答えつつ、瑞樹はデイパックを肩にかけ直した。
「でもさっき、電話してる成田さんの笑顔って、すごく自然だった。本当に楽しそうな笑顔だったんで、驚いちゃった」
―――俺にだって楽しいと思う瞬間位あるだろ。もしかしてサイボーグとかターミネーターと間違えてないか?
「さっきの電話って、女のひと?」
そのストレートな質問に、一瞬ギョッとし、思わず彼女の顔を凝視する。
「…女のひとなんですね」
先ほどまでとあまり変わらない笑顔が、かえって不気味さを醸し出している。自分なんかよりも、彼女の方がよっぽどポーカーフェイスなんじゃないだろうか、と、皮肉な考えが頭をよぎる。
そんな事を考えつつも、実際のところ、瑞樹の表情は全く変わっていなかった。軽く片眉を上げて口にした言葉も、極々シンプルだった。
「さぁ? どうだろう」
「…ずるいですね、成田さんって」
ああ、どうせずるいよ。
面倒になってくると、どんどん心の声までが投げやりで短くなってくる。表情には出ないものの、瑞樹はかなり苛立ってきていた。
1階に着き、鍵を守衛に預けて、通用口からビルの外に出た。途端、2月の冷たい風にさらされ、思わず身を縮める。
真弓は、瑞樹の数歩後ろを、同じ速さで歩いている。特に何も話そうとしないが、その顔は静かな微笑をたたえていた。
駅前のタクシー乗り場に来たところで、急に真弓は立ち止まった。
「私、タクシーで帰ります」
「まだ電車あるんじゃないの」
「うちの近所、結構暗くて危ないから、遅くなる時は遠くからでもタクシーで帰れって、母に言われてるんです」
―――ここから? 地元の駅から、じゃなくてか?
随分贅沢な事言う家だな、と瑞樹は思ったが、電車に乗るなら電車の中までこの重苦しい雰囲気を引きずらなくてはならない。助かった、という気持ちの方が大きいのが本音だ。
「そう。じゃ、おやすみ」
「成田さん」
さっきまでの倍くらいのボリュームで呼びかけられ、瑞樹は足を止めた。
真弓は、もう微笑んではいなかった。唇をきゅっと一文字に引き結び、瑞樹の顔を真っ直ぐに見返している。
「やっぱり、彼女にして下さい」
「…その話だったら、昨日断った筈だけど」
「でも成田さん、彼女いないんでしょう? 私のこと、顔を見るのも嫌ってほど、キライでもないでしょう?」
―――いや、そりゃ、そうだけど。
またこのパターンかよ、と、瑞樹は内心ひとりごちた。断る理由がないなら、とりあえず彼女の座につかせて下さい―――これまでも幾多のチャレンジャーが、この同じセリフを吐いてきたのだ。真弓も確かに、このセリフを口にした歴代の女達とタイプが似ている。外見的にも、話し方とかも。
そしてこのタイプは、断る理由もないのに断ると、非常にしつこい。やっぱり納得がいきません、なんて言って、何度も何度も食い下がるのだと、過去が証明している。
「…無駄だと思うけど」
「構いません。次の彼女までの繋ぎだと思って下さい」
ファイターと呼んだ方がふさわしい、真弓の目。瑞樹はとうとう折れた。
「―――ま、好きにすれば」
「ありがとうございます」
にっこりと微笑んだ真弓は、最後に表情を引き締め、こう締めくくった。
「私、負けませんから」
「は?」
―――誰に?
そう訊きたかったが、真弓は一礼し、止まっていたタクシーに乗り込んでしまった。タクシーの中からも軽く頭を下げる真弓の姿が見えたが、彼女が何に対して敵対心をあらわにしてるのかは、さっぱり読み取れない。
タクシーが走り去ると、そのあおりで風が一層強く感じられた。
寒さと、言いようのない不気味さにぶるっと身を震わせ、瑞樹は駅に向かって歩き出した。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |