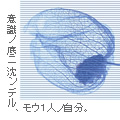| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
見慣れない店員がレジに立っているのを見て、瑞樹は思わず、店内を見回した。
「栗原さんは?」
「ちょっと体調を崩して入院しまして…1週間ほどお休みをいただいてます」
栗原は、ここ2年ほど、このレンタルビデオ店の夜の時間帯を常に担当していた、30代後半の男性である。言葉を交わす機会は少なかったが、週に1、2度は顔を見ていたので、別の顔になると結構違和感がある。
助っ人として派遣されたらしい店員は、栗原に比べるとかなり若い。瑞樹と同世代のようだ。和臣と少し似た明るい色の髪をしており、やさしげで整った顔立ちをしている。返却したビデオをチェックする手が、いまひとつ慣れていない感じがするので、もしかしたら店員ではないのかもしれない。このレンタルビデオ店は、元々大手の本屋が経営しているので、その系列からの派遣の可能性もある。
「チェックOKです。ありがとうございました」
顔立ち同様、やさしげで丁寧な口調で、その店員は挨拶した。
***
「え、栗原さん、病気なの?」
瑞樹から話を聞かされた蕾夏は、ちょっと心配そうな顔をした。
「ああ。1週間入院だって。何の病気か知らねーけど」
「ふーん…大変だねぇ。あの人、結構映画の趣味渋いんだよ。“カサブランカ”とか“旅情”が好きだって」
それを聞いて、瑞樹は訝しげな顔をした。蕾夏と一緒に件のレンタルビデオ店に足を運んだのは、両手では余る程度の回数だ。
「お前、一体いつそんな話してたんだ?」
「瑞樹がCDの試聴コーナーにはりついてる間」
言われてみれば、瑞樹は、行くたびに15分程度CDコーナーで新譜を漁っている。まさかその間に蕾夏が店員と映画談義をしていたとは知らなかった。
「ちょうどいい暇つぶしなのに、今日はいないのかぁ。残念。ねぇ、新しい店員さん、愛想いい?」
「…愛想はいいけど、ビデオの扱いには慣れてない感じだな」
「そうなんだ。…ま、話してみないとわからないよね。案外、すんごい映画通だったりするかも」
「―――今日は俺、CDコーナー無視するから」
少し機嫌を損ねたような瑞樹の声に、隣を歩く蕾夏は、キョトンと目を丸くして、首を傾げた。
付き合い始めた、と言っても、表面上、2人の間に特に変わったところはなかった。
腕を組んだり手を繋いだりして歩くのも、今更照れくさい。だから、つかず離れずの距離で並んで歩く。その距離は、以前と変わらない。
休日には、一緒にロードショーを観に行ったり、写真を撮りに行ったり。土曜日なら、見たいビデオを山ほど借りて、瑞樹の部屋でオールナイトのビデオ鑑賞をしたりもする。そんな休日の過ごし方も、付き合う前と同じだ。
ただ、ふざけたように髪に触れた時や、体温を感じるほど近くで並んでビデオを見る時、以前とは少しだけ変わった自分たちの関係を、僅かに実感する。その変化の微妙さに蕾夏は安堵し、恋愛感情を伴っていても蕾夏が逃げない事に瑞樹も安堵する―――そんな関係だった。
ゆっくり、ゆっくり―――少しずつ前に進めれば、それでいい。それをそのまま形にしたような、今の関係。こんな風に、だんだん互いに歩み寄っていければいい、と、瑞樹も蕾夏も思っている。
「今度、今まで撮った写真のうち何枚か、またプリントさせてもらっていい?」
「いいけど…今までだってお前、気に入ったやつは焼き増しして持って行ってたんじゃないか?」
不思議そうに瑞樹が言う通り、蕾夏はこれまでも、こんぺい糖の写真や屋久杉の写真などを、その都度焼き増しして持ち帰っていた。それは、既に相当な枚数になっている筈だ。
「うん。でも、今度は写真集作るための写真選びだから、前とは違うの選ぶかも」
「写真集?」
「昔からね、お父さんが撮った写真をアルバムに並べて、そこにコメントとか詩とか書いて、1冊の写真集みたいにして保存してたんだ。だから、瑞樹の写真でもそういうのやってみたいな、って思って」
「へえ…。面白いかもな。今日うち来たら、写真選別やるか?」
「あ、それもいいなー」
そんな話をしながら歩いているうちに、レンタルビデオ店についてしまった。写真選別をやるならビデオを見る時間などない気もしたが、いつもの習慣で、なんとなく店内に足を踏み入れた。
一瞬、レジカウンターに目を向けると、やはり栗原の姿はそこになく、おととい見たのと同じ店員が立っていた。やっぱり、今ひとつ慣れない手つきで、返却されたビデオを籠の中に整理して入れている。
あれがさっき言ったピンチヒッターの店員だ、と、蕾夏に教えようと振り向いた瑞樹は、背後に立つ蕾夏の顔を見て、眉をひそめた。
何故か蕾夏は、唖然とした顔をして、その場に立ち尽くしていた。その視線を辿ってみると、どうやら、カウンターの中の例の店員を見て驚いている様子だ。
「…由井君…?」
「え?」
「由井君!」
蕾夏のあげた声に反応するように、カウンターの中の店員が、ぱっと顔を上げた。すると、彼の目も、極限まで丸く大きく見開かれた。
「ふ…っ、藤井!? なんで!?」
「なんで、って…えええ!? なんで由井君がビデオレンタルにいるの!? 就職したのって書籍販売部じゃなかった!?」
「いや、オレは栗原さんの助っ人で有無を言わさず派遣されて…あ、どうも、いらっしゃいませ」
うろたえたような由井の目が、蕾夏の斜め前に立つ瑞樹の姿をとらえたらしく、由井はいささか唐突なタイミングで瑞樹に会釈した。どうやらおととい来店した際に顔を覚えていたらしい。
由井は、蕾夏と瑞樹の顔を何度も見比べ、瑞樹は、由井と蕾夏の顔を何度も見比べた。そして2人は、ほぼ同時に、同じ疑問を、蕾夏にぶつけた。
「誰?」
***
「…彼、気を悪くしてるんじゃない?」
カウンターの向こう側の由井が、CDコーナーにいる瑞樹を心配そうに返り見る。が、蕾夏はくすっと笑って、小さく首を振った。
「大丈夫。瑞樹には、ちゃんと通じてるから」
蕾夏は由井を、「中学・高校・大学と9年にわたる同級生」と瑞樹に説明した。
さすがに、なんだそりゃ、という顔をした瑞樹だったが、それに続く説明を聞いて、全てを察したような顔をした。
『あの日、辻さんとこまで送ってくれた友達。…翔子と同じ位、大事だった友達だよ』
「…藤井。もしかして、全部あの人に話したの?」
蕾夏の方に向き直った由井は、少し声を落としてそう訊ねた。少しバツが悪そうにコクンと頷く蕾夏を見て、由井は心底安堵した笑みを浮かべた。
「―――そうか。自分から話せるような相手と出会えたんだ。良かった」
「うん。瑞樹に聞いてもらえた事で、やっと、少し楽になれた気がする」
「オレさ。さっき、あの人と話してる藤井見て、本当に嬉しかったんだ」
「え?」
「成田さんに向ける藤井の笑顔―――オレと出会ったばっかの頃の藤井の笑顔そのままだったから」
懐かしむような由井の笑顔に、蕾夏は戸惑ったような表情を浮かべる。
「9年間同じ学校通いながら、あの頃の藤井の笑顔がもう1回見たいって、オレずっと思ってたから…今日見れて、すごく嬉しかったんだ。良かった。藤井が、そういう顔できる人に出会えて」
「…うん」
蕾夏は頷き、柔らかで静かな笑顔を由井に向けた。
それは、由井が9年間慣れ親しんだ“本当の蕾夏じゃない蕾夏の笑顔”だ。やっぱり瑞樹以外には、本来の笑顔を向ける事ができない。どこかで警戒している自分がいる。
「あ…、でも、藤井」
ふと思い出したように、由井が眉をひそめた。
「辻には、話した? 成田さんと付き合ってるって事」
「……」
由井の言う“辻”とは、辻家長男の正孝のことではなく、妹の翔子の方のことである。今度の問いかけには、蕾夏はちょっと表情を曇らせ、首を横に振った。
アメリカにいる翔子に連絡を取ろうと思えば、国際電話や手紙、それにメールという手もある。なのに、蕾夏はまだ、瑞樹と付き合うようになった事はおろか、辻との連絡を絶った事すら、翔子に伝えてはいなかった。
「なんか、翔子には言いにくくて…。きっと、怒ると思うんだ。私が辻さんから離れてくことを。そう思うと…」
そう言う蕾夏の、ちょっと沈んだ表情を見て、由井はやっぱり、という風に唇を噛み、視線をカウンターに落とした。が、意を決したように、また蕾夏の方を見る。
「…あのさ、藤井」
由井は、カウンターから半分身を乗り出すようにして、まっすぐに蕾夏の目を見据えた。
過去にも何度かあった、こういう目――― 一人暮らしをした方がいい、と助言してくれた時も、由井はこんな目をして蕾夏を見据えた。
「オレ、辻の事も正孝さんの事も好きだけど――― 一番幸せになって欲しいのは、藤井だから」
唐突な言葉に、蕾夏は怪訝そうな顔をした。
「藤井が不幸になったら、オレ、一生自分を責め続ける。だからさ―――どんなに辻が大切な友達でも、藤井は、自分の事を一番に考えろよ。辻とか正孝さんとかオレの事じゃなく、自分の事を」
「…考えてるよ?」
「考えてない」
由井は、きっぱりとした口調でそう言い切る。
「藤井が自分の事考えるのは、他の人間の事を一通り考えた後なんだよ、いつも。…藤井は、優しすぎるんだよ」
「そんな事ないよ。由井君、私のこと買いかぶりすぎてるんだよ」
「…まだ、時々、夢に見るんだよ」
由井の眉が、苦しげに寄せられた。カウンターの上、握られた拳が、力を込めすぎて色を失っている。
「―――藤井がオレに向かって“絶対来るな”って、悲鳴みたいに、叫ぶ声。…まだ、夢に見るんだ」
蕾夏の表情が、一瞬、強張った。びくん、と揺れた肩に、思い出させるべきじゃなかった、と後悔するが、由井はそのまま続けた。
「…買いかぶりじゃ、ない。オレが一番よく、知ってる」
「……」
「藤井は、優しすぎる。いつもいつも。だから…これからは、誰が傷ついてもいいから、成田さんと自分の事だけ考えてくれよ。頼むから」
蕾夏は、返す言葉が見つからなくて、曖昧な笑顔だけを由井に返した。
***
「随分、深刻そうな話してたな」
レンタルビデオ店を出て歩き出したところで、瑞樹がポツリとそう呟いた。
「…うん。でも、大丈夫。大した事じゃないから」
少し心配そうに眉をひそめる瑞樹に、蕾夏は笑顔を返した。
「俺の事で、何か言われたとか?」
「ううん、全然。あの事を全部話せるような相手と巡り会えて本当に良かったな、って嬉しそうに言われた。私が誰にも言えずに抱え込んでた事、由井君が一番心配してたから」
「なら、いいけど」
「逆に由井君、心配してたよ? 瑞樹に異性の友達紹介したりして大丈夫か、って」
「―――ふーん。お前の関係者にしては、珍しくまともな事言うじゃん」
「何それっ。なんで“お前の関係者にしては”なのよ」
「親父さんで散々、男親に関する常識を覆されてるから」
面白がるような笑顔で瑞樹にそう指摘されて、蕾夏も言葉につまった。
「う…、そ、それは…確かに…」
「だろ?」
「―――…そ、それでさ。瑞樹が気を悪くしたんじゃないか、って由井君言ってたけど、そんな事ないよね?」
「さぁ? どうだろ」
「え!」
思わぬ返答に、蕾夏は驚き、目を見張った。
「う、うそっ! 本当に!?」
「ま、この位は、面白くねー、って思ったかな」
そう言って瑞樹は、親指と人差し指で2センチくらいの幅を示してみせた。それを見て、ショックを受けたような顔をしていた蕾夏は、僅かに眉を寄せた。
「それって、全体がどの位の幅なの?」
「それは秘密」
「それじゃあ、どの位気を悪くしたか、全然わからないじゃんっ!」
「ハハ…、とにかく、大した量じゃないって事」
「ホントにっ!? 言っとくけど、由井君、翔子の元カレだからね? 中学ん時からずーっと翔子一筋で、翔子がアメリカ留学決めちゃったショックで第一志望の大学落ちた位なんだから! ほんっっっとに私とは友達なだけなんだからね!?」
「わかってるって。だから、そんな真っ赤になってエキサイトすんなって」
むきになって騒ぐ蕾夏の様子に、瑞樹は余計可笑しそうに笑った。
実際、それほど気を悪くしてる訳でもなかった。由井の目を見た時、辻と会った時感じたあの嫌な感じが、全くなかったから―――こいつは大丈夫だ、蕾夏の事を本当に心配しているし、そこには純粋に「友情」しかない、と、直感が告げていた。
でも、全く気にならないか、と言われれば、それも嘘だ。自分の知らない蕾夏を知っている、という点では、辻以上に、由井の方がよく知っているだろう―――その事に、嫉妬を感じるのは仕方ない。
だからつい、こんな風に蕾夏を揺さぶってみて、慌てて釈明する姿を見て安心したりするのだ。俺って結構ガキだよな、と、瑞樹は自分の行動に内心苦笑した。
と、その時。
歩きながら瑞樹の背中をポカポカ叩いていた蕾夏の手が、急にピタリと止まった。
どうしたのかと思って振り向くと、蕾夏は、瑞樹を通り越したもっと先方を見つめていた。そこに漲る緊迫したムードに、瑞樹まで少し緊張した。
「? どうした?」
「あ…危ないっ!」
「え? あ、おいっ!」
叫ぶと同時に、蕾夏は瑞樹の横をすり抜け、走り出していた。
慌ててその後を追おうとした瑞樹は、目に飛び込んできた光景に、ギクリとして立ち竦んだ。
瑞樹の前方20メートルほどの、2車線分の横断歩道―――小学校にあがったばかり位の女の子が、まだ赤信号の横断歩道を、トコトコと渡ろうとしていた。蕾夏はその子に向かって、全力で走っていっていた。
その向こうには、慌ててブレーキを踏んだらしく、キキキッという耳障りな音をたてながら直進してくる、1台のワゴン車。
「ま……」
“待て”、と。
待て、間に合ってくれ、と、瑞樹の頭の中で、誰かが叫ぶ。
「ま、待って! 止まってーっ!」
蕾夏が、走りながら叫んでいる。
その声に気づいた女の子が、一瞬、足を止めた。その一瞬が、蕾夏に追いつく時間を与えてくれた。蕾夏は、無我夢中で女の子を抱えると、歩道側にぐいっと引き込んだ。
その3秒後―――かなり減速したワゴン車が、2人の目の前を通過していった。
***
心臓が、ドキドキいっていた。
蕾夏は、肩で息をしながら、ゆるゆると女の子の体を離した。
「だ…っ、大丈夫? どこも怪我ない?」
ビックリしてしまったらしい女の子は、蕾夏のブラウスの裾をぎゅっと握ったまま、焦点の定まらない目で、コクン、と頷いた。
女の子が被っていた帽子がゆがんでしまっているのを直しながら、剥き出しの手足に軽く視線を走らせる。確かに、どこにも傷跡はなさそうだ。やっと本当の意味で、ホッとした。
「どうしたの。考え事してたの? 赤の時は渡っちゃダメでしょ」
まだショックが残っているらしく、女の子はまたコクンと頷くだけだった。
その時、歩行者側の信号が、青に変わった。すると女の子は、お礼も言わずに蕾夏の手を跳ね除けると、逃げるように横断歩道を渡ってしまった。さすがの蕾夏も、これには唖然とした。
―――そ…そりゃ、お礼が言われたくてしたんじゃないけど…。ちょっと…あんまりかも…。
以前、迷子になっているところを見つけた「おおしたつとむ4歳」の方が、よっぽど礼儀正しかった。親のしつけの問題かな、と少し憤慨しながら、蕾夏は小さくため息をついた。
「今の子供って、みんなあんな風なのかなぁ? ねぇ、瑞樹…」
愚痴り気味にそう言いながら瑞樹の方を振り返った蕾夏は、瑞樹の異変に気づいて、思わず眉をひそめた。
「…瑞樹?」
瑞樹は、電柱にもたれかかって、俯いていた。
口元に置いた手が、傍目にも震えているのがわかる。俯いてしまっているので表情をうかがい知ることはできないが、瑞樹は震えと乱れる呼吸を制御しようとしているみたいに、体を強張らせていた。
「ど…どうしたの? 瑞樹」
慌てて駆け寄った蕾夏を、瑞樹は、苦しげな目で流し見た。瑞樹のそんな目は見たことがなくて、蕾夏は激しく狼狽してしまう。
「―――なんでも、ない。行こう」
「で、でも」
戸惑う蕾夏を思い切らせるように、瑞樹は少し乱暴に髪を掻き上げると、先にたって歩き出した。その歩く速さがいつもより妙に速いので、蕾夏は慌てて、小走りにその後を追った。
胸が、ざわめく。
和臣たちの披露宴の時、パティオに1人で出て行く瑞樹を見た時にも感じた、胸のざわめき。瑞樹が話してくれるまで待つ、と決めた事。でも―――あの時以上に、今の瑞樹には不安を感じる。
何があったの、と訊きたい気持ちを、蕾夏はぐっと飲み込んだ。ただ、彼に置いていかれないよう、必死にその後を早足で追いかけた。
歩いている間も、アパートに着いて部屋の鍵を開ける時も、瑞樹はずっと蕾夏から顔を背けていた。表情が見えないと、余計に不安は募る。
「…ね…ねえ、瑞樹…」
玄関の扉が、バタン、と閉まった。
そこで。
瑞樹の意識は、ぷっつりと途切れた。
***
―――誰かが、呼んでる。
違う。呼んでる訳じゃない。俺の名前を、叫んでる。
『瑞樹が、あなたを、選ばせたのよ!』
…ああ。なんだ。夢か。
これは、いくつの時だったかな…10歳? 11歳? とにかく、「あの日」より随分後なのは確かだ。
今更聞いても、別に落胆も絶望も感じない話だから、妙に冷めた気持ちで廊下で立ち尽くしてたっけ。ただ
『あの頃も今も、私にはまだわからない―――窪塚さんと一樹、どちらをより愛してるのか。それでもあなたを選んだのは、あの子がいたからよ』
『…俺より、窪塚さんの方を愛してるのか?』
『違う! 選べない…私、選べないのよ。本当は私、待ちたかった。窪塚さんが帰ってくるまで、何年でも―――それを待ってから、あなたか窪塚さん、どちらかをちゃんと諦めたかった。2人とも愛したまま、結婚するなんて…そんな事、本当はしたくなかった。そうできなかったのは、あの子がおなかにいたからじゃないの! あの子がいなければ、こんな風に気持ちを引き裂かれたまま生きてく事になんてならなかった! 瑞樹が私に一樹だけを選ばせたのよ!』
…だから、我慢しろって?
心を真っ二つに裂かれたまま片方を選ばざるを得なかったのは、俺がこの世に生まれたせい。だから俺は、あんたを恨む権利も憎む資格も無いって?
『選べよ、倖』
『無理よ。選べない』
『俺を選べよ! お前自身で選べよ!』
『嫌! 嫌よ、一樹、やめてよ―――!』
嫌なら、やめて欲しいなら、窪塚を選べよ。
嫌だと言いながら、やめろと言いながら、なんであんたは親父を受け入れるんだよ? 窪塚とも同じ事してる癖に、なんでそんな風に嬌声を上げて親父を受け入れるんだよ?
自分の欲望が満たせれば、相手がどう感じようが、周りがどう傷つこうが、あんたにとってはどうでもいい事なのか?
その結果が、俺と海晴、2人分の命だってこと、どうしてあんたにはわからないんだよ?
こんな風になる位なら―――最初に、俺を、殺しておいてくれれば良かったのに。
手足もなく、考える力もない小さい頃に、この世から葬り去られていた方が、何倍もマシだった。
痛みも苦しみも感じるほど大きくなってから殺される事を考えれば、最初から存在しない方が、ずっとずっとマシだった。
生まれない方が良かった命なら―――なんで、殺してくれなかったんだよ―――…?
「瑞樹―――…!」
―――蕾夏?
蕾夏が、桜の木を抱きしめて、穏やかに笑ってる。
“
―――お前にとって“生命”は、それがどんな物の命であっても、そんな風に笑えるほどに大切な宝物なんだな。
でも、俺にはわからないんだよ、まだ。
俺の命の価値。俺が生きてる意味。…お前が精一杯教えてくれてるのに、まだわからない。
蕾夏―――お前の命の価値は、こんなにも実感できるのに―――なんで自分の命の価値は、実感できないんだろう…?
「瑞樹!」
びくっ、と、うずくまった瑞樹の肩が、蕾夏の声に反応した。
顔を上げた瑞樹は、自分の状況をよく把握していないようだった。ぎこちない動きで首を回し、自分の顔を覗き込むようにして
「俺…、今、どうしてた?」
「玄関入った途端、がくん、て膝ついちゃって―――うずくまったまま、動かなかったの。ほんの1分位だけど」
「…そう、か」
気を失った、というより、トリップしたに近い状態らしい。瑞樹は、大きく息を吐き出すと、玄関に据え付けられた下駄箱に手をついて、ゆっくり立ち上がった。
「…ねぇ、大丈夫?」
蕾夏も立ち上がり、自らを落ち着かせようとしてるみたいに髪をくしゃっとかき混ぜている瑞樹の顔を下から覗き込んだ。
瑞樹は、疲れ果てたような目になっていた。その目を蕾夏の方には向けず、微かに頷く。
「……大丈夫だから、心配すんな」
―――大丈夫? これで?
半分、死にかけてるみたいに見える瑞樹の様子に、ますます胸がざわつく。何かしてやれる事はないのか、と、うまく回らない頭で必死に考える。
「…あ。ちょ、ちょっと待ってね。今、お水持ってくる」
「いい」
「でも」
「いいって!」
部屋に上がって、台所へ向かおうとした蕾夏の手首を、瑞樹が掴んだ。
乱れた前髪の隙間から、瑞樹の、少し怒ったような目が、蕾夏を見据えていた。その目と、手首を掴む瑞樹の力の強さに、蕾夏は思わず息をのんだ。
掴まれている手首にギリリと痛みを覚え、その痛みに顔を歪める。それを見て瑞樹は、指を1本ずつ引き剥がすみたいにして、ゆっくり手首から手を解いた。
「瑞樹…?」
瑞樹は目を逸らすと、戸惑う蕾夏を置き去りにして、荒っぽい仕草で部屋に上がり込んだ。そして、蕾夏には背を向けるようにして、床の上に座り込んで膝を抱えた。
「―――今日は、お前、帰れよ」
瑞樹の言葉に、蕾夏は目を丸くした。
「な…なんで?」
「今日は、駄目だ。帰れ」
「帰れ、って…そんなの、わかんないよ。どうして?」
「帰れって! 俺、このままだと、何するかわからない―――頼むから、今は一人にしてくれよ」
膝に頭を埋めるみたいにして、瑞樹が声を絞り出す。
蕾夏には、その姿が、何故か小さな子供に見えた。暗闇を恐れて膝を抱えて震えてる、小さな子供に。
「…一人で、大丈夫なの? 本当に」
「…大丈夫だから」
「―――じゃあ、後で絶対、電話して」
「……」
「いつも通りに、電話に出るから。何も訊かないから。だから―――約束して。お願い」
「…わかった」
呟くような返事に、蕾夏は小さく息をつき、玄関先に放り出していたトートバッグを掴んだ。本当はついていてあげたい気持ちの方が強かったが、その気持ちを必死に押し殺して。
「―――蕾夏」
ドアノブに手をかけたところで、瑞樹の声が背後から追ってきた。肩越しに振り返るが、瑞樹は相変わらず蕾夏に背を向けたままだった。
「…ごめんな」
瑞樹らしくない、掠れたような弱い声に、胸が締めつけられる。
「…ううん」
「大丈夫―――少しすれば、いつもの俺に戻れる。だから、心配するな。電話、絶対するから」
「…うん…待ってる」
後ろ髪を引かれる思いのまま、蕾夏は、玄関のドアを閉めた。
***
魂の抜け殻みたいになって駅までの道のりを歩きながら、蕾夏は、さっき見た瑞樹の姿を思い出していた。
―――知ってる…。あれが、何なのか。
抑えても抑えても体の奥から湧き上がってくる震えを、必死にコントロールしようとしていた瑞樹。うまく息ができないみたいに、呼吸を乱しながら。
その姿は、瓜二つだった。
蕾夏が、事件のフラッシュバックを起こした時の姿と。
手首がズキン、と痛み、蕾夏はまた顔を歪めた。
見下ろすと、手首には、瑞樹の指の痕が赤く残っていた。その痕を、指で辿ってみた。
瑞樹が抱え続けている、悪夢。
蕾夏にも話せないほどに、その闇は深いのだろうか? それとも、蕾夏もまだ悪夢を抱えたままでいるから、重荷を増やすまいと遠慮しているのだろうか? 蕾夏では力不足だと思ってるのだろうか?
話を聞くことで、重すぎる荷物を、少しは肩代わりできるかもしれないのに。
『まだ、時々、夢に見るんだよ―――藤井がオレに向かって“絶対来るな”って、悲鳴みたいに、叫ぶ声。…まだ、夢に見るんだ』
…私も、まだ、夢に見るよ。
あの人に言われた事――― 一言一句
ねえ。
いつになったら、見なくなるのかな。
どうすれば、解放されるのかな…。
「―――瑞樹…」
名前を口に出したら、何故か、涙が溢れてきた。
―――帰れ、って言ったのは、もしかして、私を傷つけないため…?
こんな時ですら、瑞樹は私の事考えてくれてるのに―――私にできる事は、何もないの?
足を止めた蕾夏は、耐え切れず、その場にうずくまった。そして、涙が涸れるまで、いつまでも泣き続けた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |