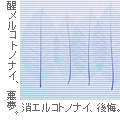| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
今でも由井は、時々、思うことがある。
何が、最初の1つだったのだろう? と。
佐野が蕾夏に目を留めてしまったこと、由井が佐野と折り合いをつけられなかったこと、由井と蕾夏が友達になったこと―――どれが最初の1つだったのだろう?
そのうちのどれだったにしても―――まるでドミノでも倒すみたいに、最初の1つが押されたら最後、結局最後まで行き着くより他、道のない事だったのかもしれない。
どんなに後悔しても、どんなに自分を責めても―――別のエンディングは最初からなかったのかもしれない。
***
蕾夏が由井の異変に気づいたのは、文化祭が2週間後に迫った頃だった。
「由井君」
「え」
「どうしたの、そこ」
眉をひそめて、自分の唇の端を指し示す蕾夏に、由井はハッとしたように口の端の傷を手の甲で押さえた。
ちょうど、殴られたような傷だった。ただし、よく見ないとわからない位、小さな傷だが。
「あ…ちょっと、ね。他のクラスの奴と、喧嘩しちゃって」
「由井君が?」
「…なんだよ、その顔。オレだって、喧嘩する事位あるよ」
不貞腐れたように、文化祭のパンフレットを2つに折り曲げる作業を再開する由井を見て、蕾夏はますます眉根を寄せた。
由井は、誰の目から見ても大人しいタイプの少年だ。本と音楽が大好きで、休み時間も一人で文庫本を読んでいるようなタイプ―――もし、何かの理由で喧嘩をする羽目になったら、暴力ではなく話し合いで決着をつける方が懸命だと考える方の筈だ。
「でも…」
蕾夏が更に訊ねようとしたところに、けたたましい笑い声が乱入した。
振り返ると、見覚えの無い女子生徒が1人、机の上に座って大笑いしていた。ここ1週間、ほぼ毎日見る光景―――でも、昨日見た子と、顔が違う。
「佐野ーっ! うるせーよ、そいつ黙らせろよ!」
文句を言われた佐野は、その声も、女子生徒の笑い声も聞こえてないみたいに、椅子に深くもたれたまま、窓の外を眺めている。
「…そろそろ、翔子ちゃん迎えに行ってくるね」
昼休みも残り少ないことに気づいて、蕾夏はがたん、と席を立った。午前の授業で気分の悪くなった翔子は、お弁当を保健室で、保健の先生と一緒に食べている筈なのだ。
佐野の席は、翔子の席の前だ。翔子が戻る前に、あのうるさい女の子がいなくなってればいいけど…と、蕾夏は、佐野の席を振り向いた。
佐野が、こちらを見ていた。
まっすぐに射抜く鋭い眼差しに、一瞬、息苦しくなる。くるりと踵を返して、蕾夏は教室を出て行った。
1週間前―――佐野をひっぱたいた右手が、まだじんじんと痛む気がした。
***
その言葉を聞いた時、蕾夏は、最初意味がわからず、目を見開いて佐野の横顔を凝視してしまった。
自分が1人になるのを見計らって訪れたのに違いない、午後の生徒会室。蕾夏は、手にしていた文化祭の資料を机の上に戻し、落ち着かせるために一度唾を飲み込んだ。
「…あの、もう1回、言ってくれる?」
「俺と付き合え、って言った」
感情のこもらない、佐野の声。でも、聞き間違いではなかったらしい。
「…なんで?」
「―――好きだからに決まってんだろ」
「だから、なんで?」
少し怒ったような目で、佐野が蕾夏の方を見た。でも、大きく目を見開いたまま佐野を見上げている蕾夏の表情を見て、苛立ったように舌打ちすると、またそっぽを向いた。
「―――藤井、だけだから。俺のこと、色眼鏡かけずに見てくれたの」
「? 私、何かした?」
「…何もしてねぇよ。ただ…挨拶して、笑うだけで」
「……」
佐野は、目が鋭くてちょっと怖いし、服装も校則違反だし、態度も悪い。だから女子生徒は勿論のこと、男子生徒からも距離を置かれている。登校途中に、「おはよっ!」と笑顔で挨拶して佐野を追い越していく蕾夏は、確かに特殊な人間だろう。ただ、笑って挨拶をするだけ―――ただそれだけのことに、佐野は飢えていたのかもしれない。
佐野が、蕾夏が日頃なにげなくしている事で気分良く過ごせていたのなら、それは蕾夏も嬉しい。でも―――それとこれとは、また別問題だ。
蕾夏は、由井が好きだし、翔子が好きだ。佐野についてはよくわからないが、以前ちょっとだけ見せたそこはかとない笑顔や、気まぐれに見せる親切な態度は、結構好きかもしれない。でも、その“好き”と、佐野が言っている“好き”は全然別物だ。
正直なことを言えば、蕾夏にはまだ、よくわからないのだ―――佐野の言う種類の“好き”が、実際には、どんな感情なのか。まだ、そういう意味での“好き”という感情を、誰に対しても抱いたことがないから。
「…ごめん。付き合うことは、できないよ」
力なく、蕾夏がそう言っても、佐野は特に表情を変えなかった。食い下がられるのも困るが、無反応なのも困る。生徒会室のあちこちに落ち着かない視線を彷徨わせた蕾夏は、ちょっと明るい声で、付け加えた。
「で、でもっ、友達になら、なれるよ? 由井君とか小山君とかみたいにさ」
「…馬鹿じゃねぇの」
佐野は、蕾夏の言葉にくっ、と笑うと、蕾夏の方に顔を向けた。鋭い目が、からかうような色合いをのせて、蕾夏を見据えてくる。
「由井が友達だなんて、本気で言ってんのかよ」
「…友達だよ?」
「男と女の間に、友情なんて有り得る訳ねぇじゃん。男が女に親切にする時は、大抵下心があんだよ。由井の事は、ガキの頃から知ってる。優等生ヅラしてるけど、あいつだって結局はただの男だよ」
蕾夏の表情が、にわかに険しくなった。
なんだか、由井と自分の友情を汚された気がする。それどころか、由井の翔子に対する想いまで汚された気がした。
「男と女でも、友情は成り立つもの! そういう友情を、佐野君が知らないだけじゃない。自分の知ってる範囲内だけで、由井君のこと勝手に中傷しないで!」
「ものを知らねぇのは、お前の方だろ。男と女なんて、全然別の生き物なんだよ。いい加減気づけよ」
「別に知らなくていいよ。由井君と友達じゃなくなっちゃう位なら」
「…んだよっ、さっきから由井、由井って! お前の方こそ本当にそれ、友情かよ!?」
その一言に、頭に血が上った。最高に馬鹿にされた気がして。
気づくと蕾夏は、佐野の頬を、力いっぱい平手打ちしていた。
「…蕾夏ちゃん? どうかしたの?」
「え?」
翔子の声に、蕾夏はようやく我に返った。
クラスの合唱の練習が終わり、気づけば教室には、蕾夏と翔子しかいなかった。どうやら、帰り支度をしながら、考え事に嵌り込んでしまっていたらしい。
「ううん、なんでもない。帰ろっか」
「うん」
文化祭まで、あと1週間になっていた。つまり―――佐野をひっぱたいてから、2週間。由井が殴られたような怪我をしてから、1週間。
佐野は、相変わらず昼休みに、別のクラスの女の子を教室に来させていた。ほぼ毎日、違う女の子なのだから、佐野は結構モテるのかもしれない、と蕾夏は初めて思った。
女の子たちを来させておきながら、佐野はちっとも楽しそうではない。いつも、彼女たちの話にほとんど耳を貸さず、面倒くさそうに窓の外を眺めている。蕾夏が交際を断ったから、自棄にでもなっているのだろうか? 佐野が何を考えているのか、全然わからない―――ただ、佐野が時々蕾夏に向ける視線で、あの妙な行動が自分のせいであることだけは、なんとなく想像がついていた。
由井は、あの後2度ほど、同じような傷を作って登校してきた。その都度、蕾夏が心配して訊ねるが、由井はやっぱり「ただの喧嘩だよ」と答えた。お金を脅し取られているとか、いじめを受けているとか、そういう心配を蕾夏はしていたのだが、由井は日頃からお金を持ち歩かないし、小山や原田もいるのにいじめに遭うとも考え難い。結局、誰に、何故殴られているのか、蕾夏にはわからずじまいだった。
「蕾夏ちゃん、何か悩みでもあるんじゃないの?」
下駄箱に上履きを仕舞いながら、翔子が心配そうに眉をハの字に寄せた。
「そんな風に見える?」
「見える。最近、女の子たちの視線がちょっとは柔らかくなったかな、って少し安心してたのに…何かあったの?」
実際、岡田たちに不満をぶちまけられて以来、クラスの女子生徒たちの態度は、僅かに変化していた。勿論、彼女たちの仲間に入れた訳ではないが、以前のような強烈な視線を向けられる事はほとんど無くなった。その事に、翔子も気づいていたらしい。
「蕾夏ちゃんって、私には何も相談してくれないじゃない? まーちゃんには色々相談してたみたいなのに」
ちょっと拗ねたように唇を尖らす翔子に、蕾夏は苦笑した。
「辻さんは、大人だもん」
「でも、同じ大人でも、親には相談しないんでしょ?」
確かに蕾夏は、日々悩んだりつまづいたりした事を、家の中にだけは持ち込まない。アメリカにいた頃から、そうだった。
家族は蕾夏の「避難場所」だ。外ではいつも、戸惑ったり悩んだりする事が多い蕾夏だからこそ、家の中だけは何も考えずに済む場所にしたかった。クラスの女子の中で浮いてしまっている事も、佐野や由井の件も、親には一切話していない。だからこそ、家では無邪気に笑っていられるのだ。
「幼馴染なんだから、私にも相談してよ。蕾夏ちゃんの方は私の面倒随分見てくれてるのに、私からは何もできないのが歯がゆいのよ」
「ん…ありがと」
―――でも、これはちょっと言えないよ、翔子ちゃん…。
由井の翔子に対する気持ちを知っているだけに、由井が誰かに殴られているらしい事など、翔子に相談できる筈もなかった。由井にとっては、殴られている事は屈辱的な事かもしれない。それを翔子に知られるのは、きっと嬉しい事ではない筈だ。
佐野の事も、到底言う気にはなれない。前の席に座る佐野の奇行のせいで一番迷惑を被っているのは、誰でもない、翔子なのだから。自分の健康に一番気をつかわなくてはいけない翔子に、要らぬ心配などさせたくない。
「あ、そういえばね」
靴を履き替え、並んで歩き出してすぐ、翔子がポニーテールを揺らしながら蕾夏の方を向いた。
「私、由井君の事で、妙な噂聞いたんだけど―――蕾夏ちゃん、何か知ってる?」
「え?」
ちょうど由井のことを考えていた蕾夏の心臓が、ドキン、と鳴った。
「なんかね、佐野君と、学校始まる前に難しい顔して話しこんでた、とか」
途端。
蕾夏の顔色が、変わった。
***
学生鞄を小脇に抱えた由井は、無意識のうちに、今朝殴られたところを手で押さえて歩いていた。
「…いってー…」
殴り方を心得てるんだな、と、妙な事に感心する。口の中はかなり切ってしまったが、外見上は僅かな傷で済んでいる。喧嘩慣れしているだけのことはある。バイオレンスと無縁できた自分とは正反対な人間だな、と、つくづく思う。
―――でも、どれだけ殴られても、藤井の友達を辞める気なんて、ないし。
消えろ、と。目障りだ、と。何度そう言われても、その言葉を受け入れる気にはなれない。
由井は、昔から友達を作るのが苦手な方だった。だから蕾夏は、由井にとっては、これまでで一番仲が良くなった友達なのだ。これからだって、“親友”と呼べるほどに親しくなれる人間は、そう現れない筈だ。2、3回殴られた位で、そんな相手を諦める訳にはいかない。
お前のそれは本当に“友情”だけかよ、と佐野に言われ、少しギクリとしたところもある。確かに、僅かながら、恋心もあるかもしれない。だからこそ、翔子とうまくいくように、と蕾夏が平然と口にすると、少し寂しい気がしたりするのかもしれない。
けれど―――蕾夏との間の気持ちは、圧倒的に“友情”が大きい。蕾夏に彼氏ができても、由井に彼女ができても、やっぱり蕾夏は由井の大切な友達だ。
「あ…由井くーん!」
背後から、聞き覚えのある声で名前を呼ばれ、由井の心臓が跳ね上がった。
慌てて傷口から手を離し、振り返る。翔子の、柔らかそうなポニーテールと、バラの花みたいな笑顔が目に入り、思わず赤面した。
「め…珍しいね。1人?」
「うん。一緒に帰る?」
「いいよ」
隣に並びかけてきた翔子に笑顔を返し、並んで歩き出した。
すぐそばに、それこそ体が触れる位近くに翔子の存在を感じると、ますます心臓が暴れる。翔子と2人きりで帰るなんて、初めてのことだ―――いつも、蕾夏がいるから。
…いつも。
―――そうだよ。
いつも、藤井がいるのに―――…?
瞬時に、嫌な予感が、体を駆け抜けた。
「…辻さん」
「なぁに?」
「藤井は? 一緒じゃなかったの?」
訊きながら、ある答えが頭をよぎる。
どんな答えでもいい。その答えでなければ、なんでも。頼むから違う事を言ってくれ―――そう祈りながら、隣の翔子の答えを待った。
「あ…うん。なんか、用事思い出したから、私は先に帰れって…」
「用事? なんの?」
「う…ん。私には、よくわからないの。でも、もしかしたら…佐野君、かも」
気まずそうに翔子が出した名前に、由井の肩が、強張った。
「由井君と佐野君が、学校始まる前に近所の公園で会ってるのを見た人がいる、って話をしたら、突然“用事を思い出した”って言ってたから―――ごめん、言っちゃいけない事だった?」
―――藤井…、あいつ―――…!
はぐらかさずに、自分の口からきちんと説明しておくべきだった、と今更後悔しても、遅い。友達が殴られていると察して、黙っていられるような蕾夏でないことは、由井が一番よく知っているのに。
いつも蕾夏は、由井のことや翔子のことを優先してしまって、自分の身に降りかかろうとしている危険には、最後まで気づかない。多分―――今も。
「…ご…めん…。辻さん」
「え?」
「ごめん! 俺、忘れ物したから、ダッシュで戻らないと!」
翔子の目が、キョトンと丸く見開かれた。こんな瞬間でも、翔子はとんでもなく綺麗で、魅力的だ。
でも。
「ごめん、1人で帰って。また明日!」
「え、えぇ? ゆ、由井君―――!?」
驚く翔子を置いて、由井は全力で走り出した。
***
頭に、血が上っていた。
文化祭直前で部活動も休みになっている。すっかり人のいなくなった校庭をつっきり、人気のない体育館の前を通り過ぎる間も、頭の中は沸騰寸前になりながら、その奥の奥は、キリリと冷たいもので凍り付いていた。
体育館脇の倉庫まで行くと、人の気配がした。蕾夏は唇をきゅっと引き結び、倉庫の扉をノックもなしに開けた。
予想通り、佐野が、道具類に囲まれて、煙草を吸っていた。
「…よぉ」
「由井君に、何したの」
いきなり本題を突きつける。が、佐野は一切動じなかった。
「よくここ、わかったな」
「体育祭の時、ここで煙草吸ってるところを生徒会全員に見つかって追い出されたのは誰よ」
「…俺だよな」
佐野は、面白くなさそうにそう呟いて、煙を吐き出した。
「それより、答えて。由井君に、何したの」
「殴った」
それがどうした、という声で、佐野は短くそう言い、煙草を地面でもみ消し、立ち上がった。
涼しい顔の佐野とは対照的に、蕾夏の方は、怒りに震えていた。どうしてそんな事を、と訊くまでもない。佐野と由井の接点など、ほとんどない。あるとしたら、蕾夏自身という接点ぐらいだ。
「…二度と、そんな真似、しないでよ」
「約束はできねぇよ」
「殴るんなら、私を殴ればいいじゃないの! 無関係な由井君を殴るなんて卑怯だよ!」
「―――っとに、お前って奴は…」
苦笑のような、どこか嘲るような―――でも、どこか傷ついたような笑いを浮かべて、佐野は1歩、歩み寄った。
「お前って、見た目も中身も、とことん真っ白だよな」
「…え?」
「綺麗すぎて、まぶしい位真っ白で―――そういうお前見てると、滅茶苦茶に壊してやりたくなる」
―――壊、す?
その言葉に、本能的に1歩下がる。
なんだかわからないけれど、とんでもなく危険な領域に、足を踏み入れてしまった気がする。本能から来る緊張感に、怒りに震えていた蕾夏の表情は、次第に、不安と恐れに変わりつつあった。
まわれ右して引き返すなら、今のうちかもしれない。
蕾夏がそう思った次の瞬間、佐野が蕾夏の肩を掴んだ。
「や……っ!」
悲鳴をあげる暇もなく、一瞬後には、蕾夏の体は、板張りの倉庫の壁に叩きつけられていた。
抵抗するように佐野の腕を叩いた両手は、佐野の左手ひとつで簡単に捕らえられてしまい、壁に縫いとめられてしまった。その動きのあまりの速さと力の強さに、恐怖心より先に、うちのめされたようなショックを受けた。
「―――お前がどんだけ同じだって言っても、違うだろ、全然。女の力じゃ敵う訳ねぇんだよ、男には」
「こ…こんな事しても、私を手に入れることは、できないよ」
必死に震えを抑えながらそう言うと、佐野は皮肉っぽい笑いを浮かべた。
「好かれようなんて、今更思っちゃいねぇよ。…憎めばいい。一生、俺の事忘れられなくなる位、殺したくなる位、憎めよ」
蕾夏の眉が、意味がわからない、という風にひそめられる。蕾夏のような人間には、理解できなくて当然だ―――佐野は、ますます皮肉な笑いを色濃くした。
「怪我、させたくねぇからさ」
佐野の言葉と同時に、何かが、蕾夏の肩口を掠め、鈍い音と共に壁に突き立てられた。制服越しに感じた硬く冷たい質感に、蕾夏は初めて恐怖を感じた。
見なくても、わかる。
これは、ナイフだ。
「だから、大人しく、やらせろよ」
「や―――…!」
嫌だ、という言葉を、佐野が噛み付くようなキスで塞いだ。
必死に首を振って抵抗するのに、抵抗らしい抵抗にならない。悲鳴をあげたくても、それすら許してもらえない。何の障害もなく、まるで当然の権利を得たみたいに、佐野の手が体のあちこちを這い回るのがわかった。
―――や…やだやだやだ! 気持ち悪い、やめて! 触らないで!
そう思うのに、手はおろか、自由の利く筈の足ですら、佐野の膝だけで簡単に押さえ込まれてしまう。思い知らされる、圧倒的な力の差。
これが、男の子。
これが、私と、佐野君や由井君との違い。
なんで―――なんでこんな事を見せつけるの―――…!?
蕾夏は、唯一の抵抗のつもりで、佐野の唇を思いっきり噛んでやった。途端、蕾夏の手を押さえつける佐野の手がびくん、と痙攣し、離れる。
唇が離れ、佐野が思わず唇を手で拭った。その隙をついて、蕾夏は、半開きになった倉庫の扉に手をかけた。
―――早く…早く! 今のうちに逃げないと―――!
必死の思いで扉を押し開いた瞬間、蕾夏は、遠くに見覚えのある姿を見つけ、一瞬、凍りついた。
―――由井君…!
その一瞬の躊躇が、命取りになった。
佐野が背後から腕を回してきて、蕾夏はあっという間に引き戻された。必死に掴んでいた扉から指が離れると同時に、蕾夏はそのまま地面に引き倒され、背中と頭を思い切り打ちつけた。
意識が遠のきかける。何がどうなってるのか、頭が混乱する。その混乱した頭の一部が、目の端に映った銀色のナイフに反応して、無意識のうちに蕾夏の体を捩らせ、逃げるような動きをさせた。
ガツッ! と。
鈍い、音が、した。
蕾夏の背後で、地面に、ナイフが刺さる、音。
でも、その音より何より、右の背中に感じた強烈な痛みと焼けつくような熱さに、蕾夏はとうとう、絶叫のような悲鳴を上げた。
「だ…っ、だから、おとなしくしろって言ったじゃねぇか…!」
少し動揺したような、佐野の声。脅すだけのつもりが、蕾夏が下手に逃げようと動いたがために、誤って斬りつけてしまったらしい。でも、そんな事はこの状況で理解できる筈もない。今感じた痛みと、一瞬だけ見た由井のことばかりが、頭の中でぐるぐる回る。
駄目。
今、来たら。
今もし助けに来たら、由井君も、刺される。
「…だ…め…」
佐野の手が両肩を地面に押し付けるのを感じながら、蕾夏は必死に声を絞り出し、叫んだ。
「ゆ―――由井君! 来ないで! 絶対、来ちゃ駄目―――!!」
次の瞬間、もの凄い力で、佐野に頬を平手打ちされた。
たったの一発で、意識がどこかへ行ってしまいそうな、衝撃。
「俺を見ろよっ!」
朦朧とする視界の中、傷ついた表情の佐野が、そう叫んでいた。
「なんで由井を呼ぶんだよ! 俺を見ろよ、藤井!」
口の中に血の味が広がる。気力を殺がせるためか、更に平手打ちを繰り返す―――でもその痛みより、佐野の傷ついたような顔のことばかり、頭に浮かんだ。
…これが、佐野君の言う“好き”って気持ち?
その気持ちに応えられなかった私は、こんな制裁加えられるほど、酷い事したの? 私、そんなに佐野君を傷つけたの?
バラバラに壊されて、叩きのめされて―――気が、狂いそう。
ううん。
多分、
もう、
狂いかけてる。
もう好きにすればいい。一瞬、そう思った。意識も朦朧としている。気を失ってる間に済めばいいのに―――そんな事すら、頭をよぎった。
なのに。
蕾夏の手は、無意識のうちに、地面の上を探り回っていた。さっき佐野が投げ捨てたナイフを求めて。
佐野が、セーラー服を引き裂くのと、蕾夏の手がナイフの冷たい感触を探りあてたのは、ほぼ同時だった。
羽織っていただけの学生服を脱ぎ捨て、白いシャツと中に着たTシャツだけになった佐野の肩あたりを、蕾夏は、どこか冷めた頭で見ていた。けれど、脚を這い上がる佐野の手の感触に、嫌悪感が再び強烈に襲ってきた。
―――い…や、だ。…嫌だ―――…!!
そう思った瞬間。
蕾夏は、ナイフを握り締めていた。
***
必死の思いで倉庫の扉を開け放った由井は、目の前の光景に、その場に凍りついた。
佐野は、左の二の腕のあたりを押さえて、壁に寄りかかるようにして地面に座り込んでいた。押さえている手の指の間から、真っ赤な血が伝い落ちている。ほとんど乱れのないその服装に、とりあえず未遂だったらしい事を察し、ほんの少しだけ安堵した。
けれど、蕾夏の方の状況を見て、一瞬感じた安堵は、前を上回るショックにかき消されてしまった。
セーラー服なのか何なのかわからない位、滅茶苦茶に破かれた服は、白い襟が血で染まっていた。由井よりはるかに酷い傷が唇の端にできていて、ところどころ覗く白い腕や肩は、無数の擦り傷で赤くなっている。紺色のプリーツスカートは泥で汚れていたが、それが守ってくれたのか、脚はさほどの傷を負ってはいないようだった。
そんな状態で、ぺたん、と地面に座っている蕾夏は、手に血のついたナイフを握っている。蕾夏はそれを、表情を失った目で、見下ろしていた。
それで、理解した。
蕾夏が、自分の身を守るため、佐野の腕を、斬りつけたのだ、と。
胸が、極限まで引き絞られる。あまりの痛みに、由井は思わず、自分の制服の胸元をぎゅっと握り締めた。
殴りかかりたいのを耐えながら、由井は佐野の方を睨んだ。暴力に訴えても意味がない事を、由井はよくわかっている。今すべき事は、蕾夏を助けること―――それだけだ。
「…行けよ」
怒りを押さえ込んだ声で由井がそう言うと、佐野は、少し驚いたように眉をひそめた。
「早く、藤井の目の前から消えろよ! どんな形でも、藤井が好きなんだろ!? だったら、藤井助けるのに協力しろよ!」
「……」
「この事…絶対、誰にも言うなよ。お前が藤井の事襲ったなんて噂がたてられたら、お前じゃなくて藤井が苦しむ。その怪我も、藤井にやられたなんて言うな。他校生にやられたでもいいし、オレにやられたでもいい、藤井にやられたとだけは、死ぬまで言うな!」
佐野は、今にも掴みかかりそうな勢いの由井を暫し見上げ、それから視線を逸らすと、制服を掴んで立ち上がろうとした。が、蕾夏の手元にあるナイフに目をとめると、唇を噛み、思い切ったようにそのナイフに手を伸ばした。
佐野がナイフを手からもぎ取る時も、蕾夏は無反応だった。視線も、ナイフを追うことなく、自分の血に染まった手を見下ろしたままだった。その様子に、まるで傷を抉られたように顔を歪めると、佐野は今度こそ立ち上がって、由井の横をすり抜けて出て行った。
佐野が出て行った途端、由井の緊張の糸が切れた。
足が震える。詰めていた呼吸も、乱れて苦しくなる。それでもなんとか地面に膝をつくと、途中、転んだせいで打ち付けた膝がズキンと痛んだ。その痛みに唇を噛みながら、由井は学生服を脱いで、半裸状態の蕾夏の肩にそれをかけてやった。
「藤井…?」
蕾夏の顔を覗き込む。
「藤井。オレだよ?」
けれど、蕾夏の目は、由井の目を見返してはくれなかった。光を失った目で、何の感情も表さないまま―――まるで人形のように、どこか遠くを見ていた。
「オレが、見えないの…?」
見えていない。
どんなに呼んでも、どんなに見つめても、蕾夏には届かない。
ここに、蕾夏は、いない。
耐え切れない涙が、由井の目から溢れた。いたたまれなくなって、由井は、かけてやった学生服ごと蕾夏を抱きしめた。
「ごめん―――! 藤井、ごめん…! オレ、お前を守ってやれなくて…!」
後悔しても、どれだけ後悔しても、足りない。
何を? 佐野に殴られている事を話さなかった事を? もっと早く蕾夏の身に迫っている危険に気づけなかった事を? いつものように一緒に帰らなかった事を? 守るだけの力もないのに、蕾夏の友達でい続けた事を?
その全部かもしれないし、もっと別のことかもしれない。後悔があまりに大きすぎて、何を後悔してるのかすら、今の由井にはわからなかった。
でも、確かな事は、ただ1つ。
それは、蕾夏がここまで酷い目に遭ったのは、由井を守ろうとしたがためだった、という事。
必死に駆けつける途中、由井は、確かに聞いた。まだ随分距離があるというのに、微かに届いた、「来ては駄目だ」という蕾夏の悲鳴みたいな叫び―――あれは間違いなく、必死に由井を守ろうとする声だった。
「頼むよ、藤井―――オレを見てよ…」
肩を震わせて泣く由井の腕の中で、どんな暴力にも涙を見せなかった蕾夏の目から、涙が一筋、流れ落ちた。
***
あの頃の2人は、まだ、中2の子供にすぎなくて。
秘密を託せるだけの、信用できる大人は、ほとんどいなくて。
だから、逃げ込む先は、1つしかなかった。唯一知っている、秘密を守ってくれる筈の、信用できる大人のところ―――そう、辻のところ。
でも―――時が経つにつれ、由井は、ある考えが、頭から離れなくなった。
あの時。もし自分が、辻のところ以外へ蕾夏を連れて行ってたら―――その先のストーリーは、どうなっていただろう?
ドミノ倒しに、時として「支線」が作られるように、もしかしたらどこかにターニングポイントがあったんじゃないか? …そんな、考えが。
返却されたビデオを整理しながら、由井はチラリと目を上げた。
CDの試聴コーナーから戻ってきた瑞樹と一緒に、蕾夏が洋画のビデオを選んでいる。昔は誰にでも見せたあの無邪気でまっすぐな笑顔を、ただ一人、瑞樹にだけ見せて。
今日、あの笑顔を再び見れたことで、由井の抱える傷は、少しだけ癒された。
…けれど。
―――藤井。
お前がその笑顔を成田さん以外にも見せられるようになる日って、いつか、本当に来るんだろうか…?
二度と、来ないのかもしれない―――そんな気がして、由井の胸は、また鈍く痛んだ。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |