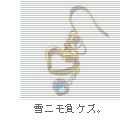| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
「ええい、なんで封鎖なんだ、こんな程度の雪で! この根性なし!」
「久保田さん、道路に根性なんて求めちゃダメですよ」
「うるさい! 中央道は根性が足りん! 北陸道を見習え!」
「北陸道も封鎖ですよ」
久保田にかかれば、日本中の道路が「根性なし」のレッテルを貼られるだろう。苛立ちながらも、久保田はラジオのスイッチを入れた。
既に2月も終わりだというのに、記録的寒波の影響でいきなり雪が降ってきて、その日仕事で山梨まで車で出かけていた久保田と和臣は、中央道が封鎖される、という事態に見舞われた。いや、実際には、最初は中央道を走っていたのだが、途中でいきなり通行止め、次のインターで強制的に降ろされたのだ。
行きは晴天だったくせに、と怒っても仕方ない。相手は自然界なのだから。
「…ああ、こりゃ事故だな。路面が凍ってたんで、ダンプカーがスピンして転がったらしい」
ラジオから流れてくる情報に耳を傾け、久保田は軽く舌打ちをした。
「しゃーない。暫く復活しそうにないから、下道行こう」
「運転代わりましょうか」
「いや、いい。もう少し走ったら夕飯食おう。そこで交替すりゃいいだろ。それより、下道慣れてないんだから、ナビをしっかり頼むぞ」
「はーい」
ロードマップの該当ページを既に広げていた和臣は、素直に返事をした。しかし、常にワイパーを動かしていないとすぐにフロントガラスを覆ってしまうほどの細かい雪に、果たして看板を見落とす事なく走れるかな、と一抹の不安を感じないでもなかった。
***
1時間も走ると、うまい具合にファミリーレストランの濫立する地帯にさしかかった。
和臣が「魚はダメですよ、肉も豚肉はダメです」とわがまま放題言うので、一番文句が出そうもないステーキハウスに入った。偏食な和臣と出かけると、いつも食事場所に苦労する。
注文を済ませたところで、久保田は時計を確認し、席を立った。
「あれ? どこ行くんですか?」
「ちょっと電話してくる」
キョトンとする和臣を席に残し、久保田は店の外に出た。
雪は、先ほどより若干小降りになっている感じがする。が、気温が下がってきていることもあって、地面は余計に凍結の危険をはらんでいる。この場所から、いつもなら1時間程度で事務所まで帰れるのだが、今日はもう少しかかることを覚悟した方が良さそうだ。
―――ったく、何も今日に限ってこんなトラブルに巻き込まれなくても…。
思わず顔を顰めつつ、久保田は携帯を内ポケットから取り出し、電話をかけた。
呼び出し音が、やたら長く感じる。3コール目の途中で、相手が出た。
『はい』
「佐々木か?」
『久保田? お疲れ様』
心なしか、佳那子の声が嬉しそうに聞こえる。その分、これから伝えなくてはならない内容を思うと、ちょっと胃が痛くなる。
『今、どこよ?』
「東京に入るちょい手前だ。雪で事故が発生したとかで、中央道が封鎖されちまったんだよ」
『あらら…それはご愁傷様』
「お前は今どこだ?」
『まだ会社よ。もうそろそろ終わりそうだから、日報書いてたところ』
「そうか…」
『気にすることないわよ。ゆっくり帰ってくれば』
そう言う声が、どことなくトゲトゲしい気がする。久保田の顔が僅かに
「い、いや…、そういう訳にもいかんだろ」
『マスターには私だけになったって断り入れておくから』
「ダッシュで帰れば、なんとか今日中に間に合うと思うんだがなぁ」
と食い下がったが、佳那子はあくまでクールだ。
『そんなに1人で待てないわよ。第一、雪道でダッシュなんてしたら危ないでしょう。私の事はいいから、事故らないように慎重に帰ってきなさいよ』
「……」
『いいわね?』
「…はい」
電話だったのが幸いだ。いくら佳那子が身長167センチと女性にしては背が高めだとはいえ、身長185センチ強の大男が「いいわね?」「はい」と言いくるめられている絵は、男として楽しい絵とは言い難い。
―――ちっくしょーっ、中央道のヤロー。事故位で止まるんじゃねーよ。日本の交通機関は、だいたい雪や台風に弱すぎるんだ。
怒りの矛先がまた中央道に向いたところで、久保田は忌々しげに携帯を切った。
***
「前から訊こうと思ってたんですけど」
「んー? なんだー?」
「久保田さんと佳那子さんて、どういう関係なんですか?」
久保田が膝の上で開きかけていたロードマップが、ばさり、と音を立てて落ちた。和臣は運転中なので、助手席に座る久保田の顔をしっかりとは見られなかったが、久保田が硬直してる気配は感じ取れる。
「…どういう、って?」
「いや、なんか、親しげというか、とっても深い信頼関係にあるというか」
「ははは、まーなぁ。同期で、飲み仲間とくりゃあ、そりゃ他の連中よりは気心が知れてるさ」
言い慣れている口上なのか、妙にスラスラとそう答える。
「でも、佳那子さんて、美人ですよねぇ」
「…そうか?」
「美人じゃないですか? きりっとしてて、宝塚の男役とかできそうですけど。同期で憧れてる奴、結構いますよ」
「ほーお…本人にその自覚はなさそうだな。教えたらきっと喜ぶぞ」
「なのに、佳那子さん、彼氏とかいないですよね」
久保田さんが彼氏なんじゃないの、という本音は一応隠して、そう言ってみる。でも、この言葉に対する久保田の反応もよどみなかった。
「佐々木の眼鏡に適う奴がいないんだろ」
「…じゃ、久保田さんも、お眼鏡に適う女性がいないから、彼女作ったりしないんですか?」
「は?」
「義理チョコ以外に5個も貰ってるのに」
「…まぁ、俺にはいろいろあるんだよ」
急に、久保田の声色が不機嫌になる。いろいろ、が具体的に何を指すかは不明だが、とりあえず「眼鏡に適う女性がいないから彼女を作らない」訳ではないらしい。
「怪しいなぁ」
「お前だって10個以上貰って、彼女いないじゃねーか」
「オレは奈々美さん一筋ですもん。何百個貰っても、奈々美さん以外の恋人なんて出来ませんよ」
「…あ、そ」
憮然とした表情で再度ロードマップを開く久保田を横目で眺め、こりゃもういくら訊いても無駄だな、と和臣は悟った。
視界が悪くなってきたので、ワイパーを動かす。現在位置からすると、もう運転交替せずに和臣の運転で通した方が良さそうだ。
「どこも寄らずに、このまま会社まで戻っちゃえばいいんですか?」
「いや、新橋で一旦停めろよ。お前、神田だろ? そのまま帰っていいから」
「はぁい―――雪、まだ止みませんねぇ…」
雪は、中央道を下ろされた時よりはかなり小降りになっていたが、まだ時折ワイパーを動かさないとまずい位には降っている。視界があまり良くないせいで、一般道もスピードが落ち、通常なら考えられないような渋滞を起こしている。
時計を見ると、午後10時を過ぎていた。
***
「おらおら、さっさと降りろ」
新橋駅前で、久保田は率先して助手席を降り、運転席の窓をコツコツ叩いた。
慣れない雪の中での運転に疲労
「酷いなぁ、久保田さん。コート着る間位待って下さいよ」
「じゃあさっさと着ろ」
やたらと急かす久保田を不審に思いつつも、和臣はコートを後部座席から引っ張り出して、なるべく急いで着込んだ。
「忘れ物ないか? 鞄も持ってるな。よし、じゃ、おやすみ」
「あ、お疲れ様でしたぁ」
和臣の挨拶もほとんど聞かないまま、久保田は即座に車を発進させた。
時計は午後11時を回っている―――急げば、なんとか間に合いそうだ。
雪は完全に止んでいて、星空までもが覗いている。最終電車が不通になるような事態だけは避けられそうで、久保田はほっと胸を撫で下ろした。
車を会社の方面に向けて走らせ、とあるビルの前に車を停める。本当は駐車禁止だが、急いで戻れば大丈夫なのは過去数度の駐車経験で実証済みだ。大急ぎで車から出ると、久保田はその古びたビルの非常階段を駆け上がった。
3階にある馴染みのバーのドアを開けた時、時計は午後11時30分を指していた。
「よ、久保田君、いらっしゃい」
口ひげをたくわえたマスターが、来ると思ってたよ、という表情で笑いかける。久保田も力なく笑い返し、店内を見渡した。
「佐々木、来てる?」
「佳那子ちゃんなら、そこ。仕方ないから、僕が祝杯の相手してあげたよ」
マスターが指さす先を見ると、カウンターに突っ伏した状態で、佳那子が眠っていた。
―――やっぱり待ってたんじゃねーか。
大きくため息をつくと、久保田は佳那子のすぐそばに立ち、内ポケットの中を探った。慌てたから潰れてしまったんじゃないかと心配したが、買った時と同じ形を維持した、青い色の小さい箱が出てきて安堵する。
「ギリギリ、セーフ」
苦笑しつつ、久保田は佳那子の耳元に囁いた。
「佳那子―――26回目の誕生日、おめでとう」
***
「佳那子ちゃーん、起きようね。終電間に合わなくなるよ」
マスターの声に、佳那子はようやく眠りから覚めた。見計らったように、マスターが水の入ったグラスを差し出してくれた。
「あー…よく寝た。疲れてたから、あっさり酔っちゃったみたい」
「早くシャキッと目を覚ましなよ? 今日は祝杯あげちゃったから、僕も送れないからね」
目をこすり、水を一口飲んだところで、佳那子はふと、自分の手元に置いてある青い箱に気づいた。
「―――マスター、久保田、来たの?」
「来たよ、30分くらい前に。車を違法駐車してるからってんで、すぐ飛んで帰ったけどね」
「そ、っか」
ふっと口元をほころばせ、佳那子は青い箱を開けた。
―――なんで毎年ピアスなのかなぁ? あいつなりのポリシーなのかしら。
時計を見ると、ちょうど日付が変わったばかりだった。佳那子は、昨日までつけていたピアスを外して、新しいピアスを身につけた。
「…この1年も、お互い、いい1年でありますように」
傍らにいない久保田を相手にグラスをかざし、佳那子は水の入ったグラスで乾杯した。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |