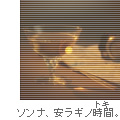| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
やっと全てのテストデータのプリントアウトが終わって、やれやれ、といった感じで、佳那子は大きく伸びをした。
コンビニで買ってきたサラダの最後のレタス1枚を口に入れると、ガサゴソ音をたてて散らばった紙くずやビニール袋をかたづける。時計に目をやると、既に午後9時。社内に残っている人数もぐっと減っていた。
「おっ、佐々木、終わったか?」
パーティションの向うから、久保田が顔を覗かせる。ちゃんと背広の上着を着ているところを見ると、ちょうど帰るところのようだった。
「ん、これで終わり。あー、肩凝っちゃった」
「もう帰るんなら、ちょっと付き合わないか?」
「なあに、どこ?」
「ふっふっふ、この間のリベンジだ」
久保田がニヤリ、と笑う。その表情を見て、ああ、と佳那子は片眉をつり上げた。先週、久保田が「いい店を見つけたんだ、付き合え」と言うのでついて行ったら、前に佳那子が紹介した店だったのだ。「あんた、ボケるにはまだ早いんじゃないの」と言う佳那子に、久保田は反論できなかった。意味不明に「ちくしょーっ、リベンジしてやるっ」と叫んでいたが、どうやら久保田が言っているのはその時のことのようだ。
「まーた前に行った店だったりしないでしょうね? おじいちゃん」
「誰がおじいちゃんだ、誰が! 今度は絶対大丈夫。佐々木好みの店間違いなし」
「何置いてるの」
「バーボンもカクテルもほぼ網羅」
「…行く」
「よっしゃ」
久保田はそう言って、佳那子の肩をポンと軽く叩いた。
***
問題の店は、目立たない裏通りのビルの10階に存在していた。看板も地味なので、一見、そこに洒落た店があるなんて誰も気づかないような感じだ。
「会社から近いのに…全然知らなかったわ」
「だろ?」
店のドアを開けると、50年代のジャズが店内から流れてきた。入口の看板を見ると、ジャズ・バーであることがわかった。少し落とし気味の照明と、席と席の間をかなりゆったりとっているところが、佳那子の好みにマッチしていた。
どの店に行っても、2人だけの時はいつもカウンター席に座る。示し合わせたかのように、久保田と佳那子は奥のカウンターに進み、真ん中あたりに腰掛けた。
「何になさいますか?」
「えーと、俺は、ターキー10年のダブル」
「ジン・トニック」
ひとまず、それぞれの定番を頼んで落ち着く。
さほど広くはない店内は、平日だというのにそれなりに席が埋まっていた。店の雰囲気に酔うように、壁面に並んでいる酒瓶を眺めていた佳那子だったが、ふと何かに気づいたように、久保田の方を見た。
「…アナログ盤?」
「お、やっと気づいたか」
嬉しそうに、久保田が笑った。
流れてくるジャズの音色に混じって、時々プチプチという音が入っていたのだ。CDとは違う、なんとなく泥くさい音色―――懐かしのLP盤の上を、針が滑る音。
「しかもな、50年代のレコードプレーヤーをそのまま使ってるんだ、ここ」
「うわ、こだわってるわね」
「スピーカーも、アメリカから運んだらしいぜ。なんかこう、隠れ家的存在で、なかなかいいだろ」
「うん、まさに私好みだわ」
運ばれてきたバーボングラスとカクテルグラスをそれぞれ手にとり、軽く乾杯する。仕事で疲れた体に、アルコールが気持ちよく染みていった。
「あー…やっぱり、アナログ盤はいいよなぁ。音が優しくて」
久保田はこう見えて、意外と音楽にはうるさい。佳那子とジャズ談義で盛り上がれるのは、社内では久保田位のものだろう。家にも凝りまくったアンプやデッキがズラリと並んでいるらしい。まだ見たことはないが、いずれそのデッキで自慢のジャズピアノ名盤を聴かせてもらおうと佳那子は思っていた。
「……あら?」
「ん? なんだ?」
「あれって、成田じゃない?」
佳那子の視線を追うように、久保田も店の奥の方を見た。
カウンター席からかなり離れた席に、丸いテーブルを挟むようにして座っている一組の男女がいた。その片一方は、佳那子が言うように、瑞樹だった。
別に向うがこちらに気づいた訳じゃないが、なんとなく久保田も佳那子も頭を低くし、こそこそと話し出した。
「ほんとだ。向かいのあの女、誰だよ」
「見覚えあるわよ。多分1階のファミレスの子だと思う。なんかナナが、あの店に成田狙いの美人ウェイトレスがいるって言ってたけど、その子かしら」
「美人ウェイトレス?」
その言葉に反応して、久保田がちょっとだけ首を伸ばす。
「…派手な女だな。美人かどうか、ちょっと判別難しいぞ」
「…そうとも言うわね」
久保田が言う通り、相手の女性は派手だった。不健康そうな色の髪に、どう見てもそりゃつけ
一方、代わり映えのしないモノトーンチェックのシャツを羽織った瑞樹の方は、ソファに深々と背中を預けて腕組みしたまま、たまに頷く程度で、何かを喋っている様子は全くない。長年こうしたシチュエーションには慣らされているので、一応微笑らしき表情は作っている。が、その感情を表すかのように、ブラックジーンズにスニーカーという足もとが、時々苛立たしげに揺すられる。話が回りくどい時などに、焦れた瑞樹がよくやる仕草だった。
「あーあ…つまんなそうだなぁ、あいつ。一番嫌いなタイプ相手じゃ、無理もないか」
「まさか、新しい彼女、ってことはないわよね?」
「瑞樹に“彼女”なんて、一度もいたことがないよ。“彼女になりたい女”は切れたためしがないけど」
口にくわえた煙草に火をつけ、煙を吐き出しつつ、久保田が言った。
「大学時代も“彼女”っていなかったの?」
「“彼女”と呼べるシロモノじゃないよなぁ、どいつもこいつも」
久保田は、瑞樹の大学の1年先輩にあたる。同じ教授の講座に在籍していた縁もあって、久保田が卒業する前の2年間は、結構親しくしていた。
卒業する時久保田は「来年は俺の会社に就職しろよ! 至上命令だ、絶対来い!」と瑞樹に言い残した。瑞樹は別にその言葉を律儀に守った訳ではないが、たまたま職種が希望したものだったし、通勤に便利だったし、求人枠もあったので、結果的に久保田の命令通りになったのだ。
「あ、帰るみたいよ」
佳那子が、更に声を小さくした。見ると、瑞樹の方は相変わらず座ったままだが、彼女の方は席を立ち、何か挨拶らしきものを瑞樹に対してしているようだった。手を振る彼女に、瑞樹も一応手を振り返している。そして彼女は、久保田と佳那子の2メートルほど後ろを通り過ぎ、精算を済ませて店を出ていった。
ほどなくして、瑞樹の方も立ち上がる。
そして何故か、真っ直ぐに久保田と佳那子の方へと歩み寄ってきた。
「―――…」
まるで打ち合わせでもしてあったかのように、久保田と佳那子はくるん、とカウンターの方に向き直り、頭を下げた状態のまま、バーボンとジン・トニックに口をつけた。だが、そんなことで逃げおおせる筈もない。やがて、2人の頭の上に、瑞樹の
「……あんたら、見え見えなんだよ。それで隠れてるつもりか?」
「…ははは、まいったなー。瑞樹、気づいてたのか」
久保田が引きつった笑いを見せて振り返ると、瑞樹は、彼の頭の上の拳骨をぐりぐりと頭にめり込ませる。
「あ、あいたたたた…」
「気づいてたんなら声かけろよ。こっちは、いやいやバカ女に付き合ってたんだから」
「ば、バカ女…」
ざくっとした物言いに、さすがの佳那子も、思わず顔が引きつる。瑞樹がここまで容赦ない物言いをするとは、正直気づいていなかった。
「あー、畜生、まずい酒だった。隣で飲みなおさして」
極めて不機嫌な顔で、瑞樹は久保田の左に座った。佳那子は久保田越しに瑞樹を見ることになったが、久保田という壁を隔ててでも、瑞樹の「スペシャル級不機嫌オーラ」は十分拝むことができる。
「マスター、こいつにハイネケン」
久保田が勝手に頼むと、瑞樹が抗議するように睨む。
「なんでハイネケン? こんな店来てまで、水みたいなもん飲む気ねーよ」
「佐々木の前で醜態さらしたくないだろ?」
「…酔う訳ねーのに」
本人の言う通り、確かに瑞樹は酒に滅法強い。が、今は特に酔いたい気分でもないのだろう。不満そうにしながらも、瑞樹は出されたハイネケンを大人しく口にした。
「さてはお前、うちの社員が大勢帰宅してるところを狙われたな?」
「…当たり。1階で待伏せしてて、強引に抱きついて、引きずってきやがった」
先ほどの派手女に抱きつかれて社員の視線を一斉に浴びている瑞樹を想像し、佳那子は吹き出しそうになるのをなんとか堪えた。
「ところで、なんで彼女一人だけ帰ったの?」
佳那子が訊ねると、瑞樹の眉が、余計不愉快そうに顰められた。
「―――そろそろ“次”、行きましょうか、って言われたから、断っただけ。“次”が飲み屋とかじゃないのは雰囲気でわかったから」
「…ああ、そういう事ね…」
“次”がどこかを考えて、佳那子の背中に嫌な汗が伝う。
「でも、成田、よくこんな店知ってたわね? 私、今日久保田に連れてきてもらうまで、こんな店あったなんて全然知らなかったわよ」
「俺も知らなかったよ。さっきの女に拉致られた先がここだったんだ」
「…彼女が知ってる方が、もっと意外だわ」
「見事なまでに、瑞樹が嫌いなタイプだったよな。途中でテーブルひっくり返すんじゃなかって、見ててハラハラしたぞ」
久保田も佳那子の言葉に頷きつつそう言う。すると瑞樹は、軽く片眉を上げて久保田を一瞥し、またグラスを手にした。
「―――ま、もう声かけてこない筈だから、いいけど」
「お、自信ありげだな。何故そう言いきれる?」
「全部、向こうにおごらせたから」
「……」
まだ不機嫌さを残した顔でハイネケンをあおる瑞樹を、久保田と佳那子は無言で見つめるしかなかった。
―――明日にはおそらく、「公衆の面前で抱きつかれ拉致された仕返しに、女に全部おごらせた男」って噂が流れるんだろうなぁ…ファミレスの従業員の間で。
何と返して良いやらわからないので、久保田と佳那子も、大人しくそれぞれの飲み物を飲むことにした。
と、その時、どこかから携帯電話の着信音が鳴り響いた。
佳那子の音でも、久保田の音でもない。2人の視線は、自然、瑞樹の方に向けられる。
瑞樹は、素早く携帯を取り出すと、そのディスプレイに視線を走らせた。そしてその名前を確認した途端―――ふっ、と口元に笑みを浮かべ、通話ボタンを押した。先ほどまでの不機嫌100パーセントな表情が一瞬にして緩んだので、久保田も佳那子も少なからず驚いた。
「もしもし。―――うん、俺」
つい1分前とは別人みたいな、穏やかな声。僅かながら笑みまで口元に浮かんでいる。こんな顔、会社でだって滅多にお目にかかれない。久保田と佳那子は、電話する瑞樹を信じられない思いで凝視した。
「今? 女に拉致されて、やっと解放されたから、会社の仲間と飲んでる。そっちは? ―――あ、ちょい待って」
携帯を肩と耳で挟むようにすると、瑞樹は財布から五百円玉1枚を取り出し、久保田の手元に置いた。
声には出さずに「ハイネケン代」と言うと、じゃ、という感じに手を挙げる。つられて、久保田も、じゃ、という感じに手を挙げた。それを見届け、瑞樹は、携帯を改めて握り直し、早々に席を立った。
「―――お待たせ。で? 何、自宅謹慎って。―――…はははは、お前らしー。いいじゃん、どんどん殴れよ。俺が許す」
何やら物騒な事を喋りながら、瑞樹は店を出て行ってしまった。が、その物騒な話をしている最中も、瑞樹の表情はいたって穏やかで楽しげで、久保田ですらこんな瑞樹は見たことない、というほどだった。
「……見た?」
呆然と、佳那子が視線を久保田に向ける。久保田も、まだ信じられないという顔で、佳那子の方を見た。
「見た見た。電話の相手、何者だよ。あの瑞樹に、あんな顔させられるなんて」
「恋人か何かかしら―――でも“殴れ”とか言ってたわよねぇ?」
いろんな可能性を考えてみるものの、結局しっくりくる相手が思い浮かばず、2人とも首を傾げるしかない。
「ま…なんにせよ、あいつにとっちゃ、酒よりあの電話の方が、憂さ晴らしにはなってるみたいだよな」
「成田にとっての“隠れ家”ってところね」
「ははは、言えてるかも」
人であれ酒であれ音楽であれ―――とにかく、ああして、日頃の鎧かぶとを脱ぐことができる場所があるのはいいことだ。瑞樹は昔から、何かのカプセルに覆われてるみたいに自分を全く
「あ、これ、ナット・キング・コールじゃない?」
続いて流れてきたジャズのスタンダード・ナンバーに、佳那子の表情が緩んだ。彼女の一番好きなジャズ・シンガーなのだ。
「ああ、ほんとだ。“アンフォゲッタブル”かな」
コールは、久保田も好きな歌手の1人だった。久保田は目を閉じて、その声に聴き入っているようだ。
手元のバーボングラスは、ほぼ空になっている。佳那子のグラスもあと一口といったところだ。
―――次は久保田は、I.W.ハーパーあたりを注文するかな。じゃあ私もそろそろバーボンに移行して、フォア・ローゼスあたり頼もうかな。
そんな計画をたてつつ、佳那子も目を閉じて、コールの歌声に酔いしれた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |