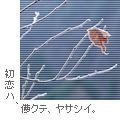| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
ノックの音に振り向くと、留袖姿の母が入ってきた。
「
ウエディングドレスの裾がひっかからないよう気をつけながら、立ち上がる。15センチもあるヒールを履いた私は、25年間で初めて母を見下ろす形になった。
「緊張してない?」
「うん、大丈夫。お父さんは?」
「緊張してるみたい。さっきから熊みたいに廊下をウロウロしてるわよ」
「バージンロードで転ばないように、お母さん、リラックスさせてあげてよ」
「わかったわ」
母がニコリ、と笑う。若い顔立ちの母は、留袖を着ても老けはしなかった。私の20年後もあんな感じだろうか…と、ふと思う。鏡の中の自分の顔は、若い頃の母に瓜二つと言っていいほど、似ていたから。
深呼吸を2、3回繰り返し、私は控え室の窓から外を見た。真夏らしい、くっきりとした鮮やかな青空が見える。
今だけ、彼の事を思っていよう。今なら、誰にも邪魔されない。ゆっくり思い出に浸ることができる。
彼―――11年、会っていない「兄」。私の中で、彼は今も、15歳の少年のままだ。
***
兄との一番古い記憶は、私が幼稚園の時―――仮面ライダーごっこをしていた近所のガキ大将が、私にライダーキックをして泣かせた時の事だ。
普段物静かな兄が、自分より年上のガキ大将を叩きのめすのを、私は見た。体の大きさも違うのにどうやったのか、今もそれはわからない。とにかく、気がついたら、ガキ大将がわんわん泣いていた。
「海晴。痛いとこ、ないか?」
ペタン、と座り込んでいた私に差し出された、兄の右手。擦り傷と泥で汚れたその手は、私の手と変わらない小さな手だったけれど、とても温かくて、優しかった。
私は男の子からよく苛められたけど、いつも兄に助けられた。注意力が散漫なのかよく転んだりドジを踏んだりして怪我をしたけど、大声で泣けば、兄がとんできて傷の手当てをしてくれた。幼稚園の送り迎えも兄がしていたし、小学校にあがってからも兄に手を引かれて登下校していた。
「海晴ちゃんのお兄ちゃんは、まるで雛を育ててる親鳥みたいねぇ」
友達のお母さんがそう言って感心するとおり、兄は、兄というより、私の親だった。
両親は共働きで、しかも休みが合わなかったので、家族4人が揃う事など滅多になかった。家にはいつも、私と兄の2人だけ……そんな生活が、物心ついた頃からずっと続いていた。両親との思い出は希薄だけれど、その隙間を埋めるかのように、たくさんの兄との思い出がある。春も夏も秋も冬も―――私は兄に守られて過ごしてきた。
だから、かも、しれない。
ある程度の年齢に達した時、私はふと気がついた。普通ならあって当然の記憶が、私から抜け落ちていることに。
私は、母と過ごした記憶がほとんどない。私の知る母は、会社から帰ってきて、慌しく食事を作る姿―――それ以外の記憶は、全くないのだ。
***
兄が小学5年生、私が小学4年生の時、私の一家は、父の仕事の関係で横浜から神戸へ移り住んだ。
「学校に行きたくない」
それが、この頃の私の、朝食の席での口癖。関西弁に慣れない私は、学校に馴染むのに時間がかかっていた。
「なんだ、海晴。言葉の事で苛められたりしてるのか?」
「ううん。でも、みんな遠慮してるみたい」
父の問いかけにそう答えた。直後、コーヒーを淹れていた母が、驚くほど大きなため息をついた。
「ほらね。だから私は嫌だったのよ、転勤なんて」
「おい、
「海晴は人見知りが激しいから、絶対苦労すると思ってたのよ。私だって会社に無理言って転勤するしかなかったし」
不満げな母の声を遮るように、突如、ダン! という大きな音が響いた。びっくりして両親と私が振り返ると、そこに、手に持ったマグカップをテーブルに叩きつけるように置いた兄の姿があった。
兄の眼は、冷徹で、無表情だった。軽蔑しきったような眼で、母を見つめていた。
「…海晴。行くぞ」
「う…うん」
立ち上がった兄に促されるようにして、私は慌てて立ち上がった。
振り返った肩越しに見えた母の顔は、罪悪感と気まずさの入り混じった、複雑な表情だった。
いつからだったかは、定かではない。
母は兄の顔を見ないし、兄も母の顔を見ない。2人が挨拶や短い言葉以外の会話を交わすところなど見たことがない。たまに母を見る時、兄の眼はいつも冷たかった。
「今日ってお母さん、お休みなんでしょ? どうしていないの?」
昔、兄によくそう訊いた。でも、兄の返事はいつも決まっていた。
「お母さんも忙しいんだよ。お母さんいないと寂しいか?」
「…ううん。別に。いつもいないもん」
事実、母はいつもいなかった。でも寂しくなかった。日曜日には父がいたし、それ以外には兄がいた。ううん―――兄さえいれば、誰もいなくたって、寂しさなんて感じなかったのだ。あの頃の私は。
***
兄は、小学6年の1年間で一気に背が伸び、元々無口だったのが更に無口になった。
子供らしい輪郭がだんだんシャープになってきて、幼さの残っていた目元も、少し憂いを帯びたような“大人”を感じさせるものに変わっていった。
すると、たまに私の忘れ物などを届けに来る兄を、クラスメイトの女の子が意識するようになった。背中に彼女たちの視線を感じながら、私はいつも優越感と焦りを感じていた。
兄が私より1年早く卒業してしまうと、焦りは更に増した。私の知ることのできない兄の時間が、日に日に増えていく―――とても我慢ができなかった。
―――お兄ちゃんを、他の女の子に取られちゃうかもしれない。
早く大きくなって、兄と同じ中学に通いたい。そんな思いばかりが空回りした。
でも、運命は残酷だった。
兄が中学1年、私が小学6年の冬の、ある朝。母と父は私と兄をリビングに呼びつけた。父は、極めて穏やかにこう言ったのだ。
「お父さんとお母さんは、離婚することになった。海晴はお母さんについて行きなさい」
私はびっくりして、父と母の顔を何度も見比べた。母は無表情で、父は普段となんら変わらない顔をしている。最後に兄を見たが、兄の顔は、そむけられていてよく見えなかった。
「…お兄ちゃんは? お兄ちゃんも、お母さんについて行くの?」
「…俺はここに残る」
ぼそり、と兄は呟いた。
***
「ねーねー、八代さん」
「なぁに?」
「今からバスケ部の練習見に行くけど、一緒に行くでしょ? 成田先輩にエールを送りに行かないと!」
心臓が一瞬、止まりそうになった。
「…うん、行こっかな」
「またまたぁ、八代さんだって、成田先輩の熱狂的ファンのくせにぃ」
ばしっと私の背中を叩く友達に、私は曖昧な笑いを返すしかない。
放課後の体育館は、誰目当てなのか、いつだって何人もの女子生徒がたむろしている。体育館の入口付近は女の子特有の高い声に占領されていた。
「成田せんぱーい!」
私の隣で、初っちゃんが歓声を上げる。背番号12が、一瞬こちらを見たが、特に応えるでも笑いかけるでもなく、すぐゲームに集中してしまう。
「クールだよねー、ああいうとこ。バスケ一直線て感じで、硬派でイケてるわ〜」
―――知らないんだよね、初っちゃんは。中学は全員どこかの部活には所属しなくちゃいけないから、「ラフプレーや乱闘があって面白そうだ」なんて無茶苦茶な理由で、バスケを選んだんだよ。なんで写真部が無いんだって愚痴りまくってたんだから。
でも―――コートを走り回る背番号12は、確かにかっこいい。シュートを決めたら、背後からも黄色い歓声が飛んだ。
こんな時、私の心の中には、どす黒い嫉妬心がわきあがる。
私の方がずっとずっと好きなのに。
もっともっと前から、大好きなのに。この人以外、好きになれないのに。
ただ「妹」であるというだけで、私は負けているのだ。世界中の女の子に。
私、八代海晴は、成田瑞樹の妹だ。でも、その事を、ここにいる誰も知らない。
***
本来なら私は、この中学に通えなくなる筈だった。母が家を出るのに伴って、私も家を出なくてはいけなかったからだ。
両親が離婚することなんて別に痛くも痒くもなかったけど、兄との接点がゼロになることは耐え難い。渋る母を説得するため、私は3日間のハンガーストライキをした。4日目の朝、ついに母は折れ、兄と同じ中学に通えるギリギリの場所に、新しいアパートを借りることを約束してくれた。
入学してみて、わかったこと。それは、周囲の誰も兄と私が
私と兄は、全然似ていない。兄が極端な父似、私が極端な母似であることが理由だ。この外見の違いと苗字の違い、更に、通っていた小学校からこの中学に上がる人数が極めて少ない(大半は隣の中学に上がる)ことも手伝って、私たちが兄妹だとは、先生たちですら気づいていなかった。
だから、友達の初っちゃんも、よく平気でこんな事を言う。
「海晴って可愛いよねー。よく男の子に告白されてるでしょ。あー、あたしが海晴位可愛ければ、成田先輩にすぐアタックするんだけどなー」
彼女に罪はない。
でも私は、そんな無邪気なセリフを口にする彼女に、その瞬間は殺意すら抱いた。
兄は、私が想像していた以上に、女の子に人気があった。
無口で無愛想で滅多に笑わない“成田先輩”―――まるで周囲の色に染まるのを拒否してるみたいに、周りの人間と微妙に距離を置いている感じのある兄は、どこかミステリアスなムードを持っている。極稀にふわりと笑ってみせることがあるが、その笑顔に胸をしめつけられる女の子は意外に多い。他にも人気のある男の子は大勢いたけれど、兄もかなりの人数の目を惹いていたようだ。
バスケの練習を見学に来る生徒の半分位は、兄目当てで来ている。黄色い歓声をあげる集団に、彼は目もくれない。興味なさそうに一瞬こちらを見、うるさいから帰れ、とでも言いたげに、ぷいと背を向けてしまう。そんな集団の中に、私もいつも混じっていた。兄が背を向ける度、心臓を切り裂かれるような痛みを感じる―――なのに、気づけばまた見に行ってしまう。
一瞬だけこちらを見る瞬間、僅かに覗くその深い灰色の瞳を見たい…ただそれだけのために。
楽しみにしていた中学生活で思い知った事。
私は、兄に「恋」をしている―――思い知れば思い知るほどに、ただ、辛かった。
***
私と母の関係は、父との離婚後、濃密になった。
濃密にならざるをえなかったのだ。家に2人しかいないということは、当然家事は母と私でこなさなくてはいけないのだから。親子というよりは姉妹みたいに、私たちは2人きりの生活を協力して営んだ。
慣れてみれば、母との生活は、案外楽しいものだ。外見が似ているように、母と私は中身も似ている。それが理由で衝突することもあったけれど、お互いわかりあえる点が日々増えていき、気づけば「ああ、お母さんに引き取られて良かったんだな」と思える位になっていた。
二人暮らしにも慣れた中学2年の冬、母が一人の男性を家に連れてきた。
窪塚という名のその男性は、母より4つ年上で、笑顔が優しい、気さくな人だった。初対面にもかかわらず私はすぐに慣れてしまい、3人で食事をとる間、ずっと笑顔でいられた。
「実はね。プロポーズされてるのよ」
窪塚さんが帰った後、母が恥ずかしそうに言った。
その言葉を聞いて、なんとなく察した。そうか、あの窪塚さんが、離婚の原因か…と。
「お母さん、再婚するの?」
「…海晴が許してくれるんならね」
一瞬、
まだ、父との離婚から2年も経っていない。父の事は大好きだったし、父以外の人を心から「父」と呼ぶのは無理だと思う。
でも―――…。
「―――うん。私はいいよ。窪塚さん、気に入ったから。お父さんは好きだけど、窪塚さんも悪くないよ」
母は、少し驚いたような顔をした。
「本当に、いいの?」
「…うん」
だって私は、許されない恋の苦しさを、身をもって知っているもの。
離婚の原因が窪塚さんだとしたら、母はずっと不倫をしてた、ということになる。きっと母も、許されない恋に苦しんでいただろう―――今、私が苦しんでるみたいに。
子供の立場としては、許せない話だし腹も立つけど、同じ“女”として―――母が、味わった苦しみの代価として幸せを勝ち取れるなら、勝ち取らせてあげたい。今の私には、そう思うことができた。
「お父さん、て呼べるかどうかわからないけど…お母さんの新しいパートナーとしてなら、窪塚さんを認めること、きっとできる。いいよ、再婚しても」
「…ありがとう。本当に、ありがとう、海晴」
母はそう言って微笑み、私を抱きしめた。こんな事をされるのは初めてだったので、妙に照れてしまった。そう言えば抱きしめてもらった記憶もないな―――そんな事をぼんやり考えていたら、母が最後に、こう呟いた。
「お兄ちゃんに、感謝しないと、ね」
「…え?」
―――どうして、お兄ちゃんに?
それきり母は、何も言わなかった。
でも、私は、問いただす事をしなかった。
もし、私が知らない“何か”を私が知っていたら、こんな風に母の結婚を祝福できなかったのではないだろうか。いずれ母が窪塚さんと再婚する事を、兄は予見していたのかもしれない。その時、私が素直に彼を受け入れられるように、兄は私には何も話さなかったのかもしれない。…なんだか、そんな気がする。
あの兄が―――ずっと私を守ってくれていた兄が「海晴には知らせるべきではない」と考えてくれた事ならば、私はずっと目を瞑っていよう。そう、思った。
***
年が明けて、バレンタイン・デー。
私は約2年ぶりに、かつて住んでいた私たちの家に向かった。
実はこれまでも、家の前までは何回か行っていた。でも、怖くて呼び鈴を鳴らせなかった。学校で会っても、他の女の子の目もあるので一切言葉を交わした事がないのだから、怖いのは当然だろう。
でも、今回だけは―――どうしても、兄と話したかった。
外は、粉雪が舞っていた。陽もすっかり落ちた神戸の街を、兄に渡すビターチョコレートを抱え、手に息をふきかけながら歩く。髪に細かい雪がへばりついて、余計体が冷える気がした。体を温めるかのように、兄の優しかった手を思い出す―――あの手は、もう届かない所にある。それを実感して、少し悲しくなった。
かつての家は、2年前のままだった。灯りが点いている―――兄は、家に帰っているようだ。
震える手で呼び鈴を押すと、暫くして、玄関が開き、まだ学生服姿のままの兄が顔を覗かせた。
「…海晴? どうした?」
2年ぶりに聞く、兄が呼ぶ私の名前―――声が低くなって、なんだか違う人みたいだ。
背も、伸びた。ドアを押えている手も、2年前より大きくて骨ばっている。毎日のように見ているのに、全然気づかなかった。だって、遠くから見てるだけだったから―――いつも、いつも。
「…“成田先輩”に、チョコレートが渡したくて来たの」
精一杯の笑顔で、チョコレートの包みを差し出した。
「甘いの苦手なの知ってるから、思いっきり苦いのにした。これなら、“成田先輩”でも大丈夫だと思うから―――お願い、私の気持ち、受け取って」
兄は訝しげに眉をひそめた。一緒に住んでいる時ですらあげたことが無かった、バレンタイン・チョコ。兄が甘いものを食べないことを知っているから、悲しいけどあげられなかったのだ。だから余計、何故今更こんなものを渡しに来るのか、兄は不思議に思っているのだろう。
私は、一呼吸おき、これまでの思いのたけ全てを込めて、口を開いた。
「“成田先輩”―――好きです」
兄の目が、丸くなった。
「ずっとずっと―――まだ私があなたの妹だった時から、好きでした」
「海晴…」
「…お母さんね、窪塚さんと結婚するの」
その言葉に、兄の表情が少し固くなる。“窪塚”という名前に反応しているようだ。
「九州に、行くの。私もついてくの、春休みに。だから―――これが、最後のバレンタイン・デー。私の初恋だから…受け取って、欲しいの」
兄は視線を落とし、暫し黙っていた。
それから、ふいに顔を上げ、私が差し出したチョコレートを、両手でちゃんと受け取ってくれた。
「―――海晴は、今だって俺の妹だよ」
兄は、そう言ってふわりと微笑んだ。
「いつも練習見に来てただろ。友達と一緒に元気そうにしてたから、それ見て毎日安心してた」
―――見てて、くれてたの? 私のこと。
気づいてすらいないと、思ってた。だって、一度も目を合わせてくれなかったから。
「何千キロ離れても、海晴は俺の妹だし、俺は海晴の兄貴だから―――それだけは、忘れるな」
「…お兄ちゃん…」
それは、優しい拒絶―――そして、優しい許容。
思わず、抱きついてしまった。小学生の頃みたいに。
こんな馬鹿な妹なのに。ただ守られてるばっかりで、何も役に立てない妹なのに。勝手に恋して、世界中の女の子に嫉妬してる、どうしようもない妹なのに―――優しく拒絶しながら、妹として受け入れてくれる。
「―――俺はいつだって、海晴の幸せを願ってる」
その言葉に、心の中でこんがらがっていたいろんなものが、解けていく気がした。
***
不思議だ―――兄との思い出は語り尽くせない位あるのに、こうしていると、思い出すのはたった1つの場面。
兄にチョコレートを渡した帰り道―――来た時と同じように粉雪が降っていて、やっぱり手が
兄との思い出なのに、そこに兄の姿はない。でも、その場面が、私にとっての兄を象徴している気がした。
今だって、兄の優しさは、私の頭上に、肩に、いつだって降り積もっている―――私には、それがわかる。
お兄ちゃん。私もいつだって、あなたの幸せを願ってる。
真夏の空に別れを告げて、私は、タキシード姿で待つ彼のところへ向かった。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |