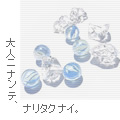| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
真新しいセーラー服を身にまとい、最初に思ったことは「まるで軍隊みたいだ」ということだった。
アメリカのジュニア・ハイは私服だったから、日本の中学が制服を義務付けているなんて想像したこともない。全員この服で登校し、この服で授業を受け、この服で帰宅するのか…なんだか、妙な気分だった。
実際に登校して思ったことは、「どれが誰だかさっぱりわからない」ということだった。確かに顔は全員違う。でも、服装が同じなので、判別する要素が少ない。後姿で判別するなんて至難の業だ。
同級生の女の子とは、馴染める要素が少なかった。教室移動もトイレに行くのもお弁当を食べるのも「みんな一緒」。話すことと言えば、かっこいいと評判の男の子の噂話やテレビアイドルの話。音楽は邦楽中心だし、映画も内容より誰と行くかに興味が集中してるし。同性なのに、なんだか宇宙人と会話している気分に、よく陥った。
だから自然と、男の子と話す時間の方が長くなった。ちょうど彼らが、映画や洋楽に興味を持ち始める年代だったからかもしれない。同じ話題で盛り上がれる仲間。ただそれだけのこと。「男だから」とか「女だから」とか、そんな言葉は関係ない。
なのに―――何故みんな、男と女を分けたがるんだろう?
大人になることが、イコール男と女を分けることなら、私は大人になんてなりたくない。
私は自分を「女」だなんて思いたくない。私はただの「藤井蕾夏」―――それだけの存在でいたい。
***
『カズが藤井さんを貸せ貸せとうるさいので、応援を頼む。 / HAL』
毎度お馴染みの簡潔なメールに苦笑しつつ、蕾夏はキーボードを叩いた。
『仕事が終わったら電話します。もし連絡がなかなかない場合は、そちらから電話して下さい。 / rai』
同じく簡潔なメールを書き、送信ボタンを押した。
―――会社で書くメールって、いつも短くて事務的だよなぁ…なんでなんだろう?
過去にやりとりしたメールを見ると、それが家からのものか会社からのものかがはっきりわかる。文の調子がまるで違うからだ。頭が仕事モードに入ってるせいもあるだろうし、他人に覗き見された場合を無意識に考えているのかもしれない。
「あ、藤井さーん」
営業補佐の水口の声に、蕾夏は顔を上げた。
水口は、蕾夏の会社では数少ない女性の1人だ。年齢的にも蕾夏の1つ下で一番近い。ただ、同じ女性でも、中身も外見も笑ってしまうほど逆方向に向いている2人なので、あまり仲は良くない。それでも、他に相手もいないので、ほぼ毎日一緒に昼食をとっている間柄だ。
「今晩って暇してない?」
たまにこういうお誘いがある。大抵はコンパだが、蕾夏はほぼ100パーセントに近い割合で断っている。その都度、断り方に苦労しているのだが、今日は楽勝だ。
「あー…、ごめん。たった今、予定が入った」
「えっ、そうなの? なんだぁ、今日コンパがあるから、協力してもらおうと思ってたのにぃ…。困ったなー。藤井さんの予定って、キャンセルできないんだよね?」
「ん、ちょっと大切な用事だから」
蕾夏が言葉を濁すと、水口はピンときた、といった感じで手を叩いた。
「あ! わかった! 男でしょ!」
「え!?」
思わず素っ頓狂な声を出してしまう。確かに男には違いないが、水口が言ってる「男」とは、単なる性別の話ではないだろう。
「なんだぁ、藤井さん、カレシ出来たんだぁ。じゃあ邪魔しちゃ悪いわよね。うん、誰か適当に見繕うわ。がんばってね」
―――いや、その…全然違うんだけど…。
そう言いたかったが、水口は一人勝手に結論を出してしまい、ヒラヒラと手を振りながら去っていってしまった。
―――まぁ、コンパに誘われずに済んだみたいだから、別にいいか。
そう思いながら水口の背中を見送った蕾夏は、ふと視線を感じて、振り返った。
ちょっといつもより暗い目でこちらの様子を見ていたのは、野崎だった。片肘をついて、微かに笑みを浮かべている。目が暗いのに微笑んでいるとは、なかなか複雑な表情だ。こういう場面では、暗い顔をされる以上に、こうやって笑顔を見せられる方が怖い。
「彼氏が出来たって?」
「…あの、えーと…」
肯定すべきか否定すべきか咄嗟に判断できず、蕾夏は、誤魔化すように曖昧な笑顔を作った。とりあえずこの話題は避けたい。野崎に“日常レベル”で口説かれるのだけは勘弁して欲しい。
「あ、あははははは、えーと、こっ、コーヒー! 野崎さん、コーヒーいりませんか?」
「ははははは、別にいらないよ」
「…ですよね」
―――ちょっと、泣きたいかも。
ともかく、その視線には耐えられないので、蕾夏は席をたち、自分の分だけのコーヒーを淹れに向かった。
***
仕事は、少し長引いたものの7時半には終わった。日報を書き終わったところで、廊下に出て、瑞樹に電話をかけた。
「仕事終わったよ」
『俺の方はまだ。カズももう少し仕事あるらしい』
「そっか。じゃあ適当に時間潰すから、終わったら電話して」
二言三言交わして、電話を切る。今の雰囲気だと、ゆうに1時間は暇になってしまいそうだ。本でも買って、お茶を飲みながら読んでようかな、と考え、蕾夏は事務所に戻りかけた。
「藤井さん」
ドアノブに手をかけたところで、背後から呼び止められた。
振り返ると、野崎が、ダンボール箱を抱えて立っていた。その後ろにも、いくつかダンボール箱が積まれている。そういえば、野崎は午後から別のビルにあるショールームの作業に駆り出されていた。その関係の荷物のようだ。
「もう帰る? 時間あるなら、これ、書庫まで移動させるの、手伝ってくれないかな」
「あ、はい、いいですよ」
答えてから、しまったかな、という思いが一瞬よぎる。でも、あれだけの数のダンボールを1人で運ばせるのは気の毒だ。何か訊かれたら、適当に誤魔化そう。そう考え、蕾夏は野崎からダンボールを受け取った。
ダンボールは、案外軽かった。廊下の突き当たりの書庫に先に着いた野崎が、そのドアを開けて押えておいてくれた。
「これ、どこに置けばいいんですか?」
「藤井さんが持ってるのは、空になったリングファイルだったな…じゃあ、奥の棚に入れといて」
そう言う野崎の持っているダンボールの中身は、どうやらストックフォームのようだった。軽い荷物を選んで渡してくれたらしい。こんな時はしみじみ、いい人だなぁ、と思う。
「―――昼間の話だけどさ」
棚に空きスペースを作りながら、野崎がそう切り出す。
「彼氏が出来たって話。―――あれ、もし本当なら、諦めるよ」
ちょっと身構えていた蕾夏は、思わぬ話の流れに、ダンボールを押し込む手を止め、思わず野崎を振り返った。
「…本当ですか?」
「ホント」
野崎は、昼間同様、薄く微笑んでいた。頭の片隅で、危険信号が点滅する。蕾夏は、更に慎重に野崎の様子を窺った。
「きっぱり、諦める。約束するよ。その代わり―――」
“その代わり”?
その言葉に不安を覚えて身体を強張らせた瞬間、野崎の手が、蕾夏の腕を掴んだ。
「! の、野崎さ―――…」
ぐいっ、と腕を引かれたと思った次の瞬間、野崎の唇が、耳元を掠めていった。襟元ギリギリのところに生温かい唇の感触を覚え、一瞬ゾクリとした嫌な感じが背中を這い上がった。
続いて襲ってきた、鋭い、痛み。
「や―――やだっ!」
悲鳴に近い声を蕾夏があげると、野崎はパッ、と手を離した。
「今のが、交換条件」
ホールドアップの要領で両手を軽く挙げた野崎は、そう言ってニッ、と笑ってみせた。頭に来る位、余裕の表情。
が、蕾夏の方はまだ頭がパニック状態から脱しない。シャツの襟元を必死に掻き合わせ、野崎との距離を少しでも取ろうとするように、書庫の扉にくっつく位後ろにさがった。
―――ちょ…ちょっと、今の、何!? 野崎さん、何したの!?
ほんの数秒の出来事だったが、心臓が暴れまくり、手足が小刻みに震える。首筋が熱を持ったみたいにズキズキ痛んで、思わず顔を顰めた。
「あー…、ごめん。痛かったかな」
ごめん、と言いながら全然反省した顔ではない野崎を、蕾夏は信じられないという顔で凝視した。
「なっ…何なんですか! 今のっ!」
「藤井さんの彼氏への、メッセージ」
「…は!?」
「―――ま、キミにはわからなくても、別にいいよ」
本気で何をされたか全くわかっていない様子の蕾夏に、野崎は苦笑した。
「土日2日間かけて徹底的に落ち込んで、月曜日からはいつもの僕に戻れるようにしとく。だから、心配しないで」
「…なんで、こんな事…」
馬鹿な質問だと、自分でも思う。が、無意識のうちに、そんな言葉を口にしていた。野崎は、その質問に、軽く肩を竦めた。
「好きな女を取られた腹いせ、かな」
“好き”。
その言葉に、鈍い痛みとぞっとするような嫌悪感を覚え、蕾夏は思わず、自分で自分の腕を抱いた。
「…さて。残りのダンボール、さっさと運んでしまおうか」
そう言う野崎の笑顔は、やっぱり余裕ありげに見える。が、蕾夏は気づいていた―――眼だけは、演技できていない、と。いくら笑顔をみせていても、やっぱり昼間見た暗い眼が、そこにあった。
微かな罪悪感に、胸が痛んだ。
***
結局、3人が顔を揃えることができたのは、午後9時を大幅に回ってからだった。
「なんか、疲れた顔してんなぁ、お前」
コンビニでピスタチオナッツの袋を手に取っていたら、瑞樹にそう声をかけられた。
確かに、疲れている。煙草を押しつけられたみたいなあの首筋の痛みはもう消えていたが、野崎の暗い眼を思い出すと、全身が水を吸ったみたいに重くなる。月曜日、顔を合わせるのが怖い。
瑞樹たちと合流するまでの間、喫茶店で窓の外を眺めながら、ずっと考えていた。
―――何故、いい先輩といい後輩のままじゃ駄目なんだろう。
「好き」って、一体何なんだろう? 野崎さんは一体、何を私に求めてたんだろう?
「好き」―――その言葉を聞くと、どうしても思い出してしまう。好きだと言いながら、私にいまだ癒えないほどの傷を負わせた人。好きだと言いながら、私を人形みたいに束縛し続けた人―――あれが「好き」という感情なら、私は絶対、誰も「好き」になんてなりたくない。
野崎さんは、私を傷つけたかったんだろうか。それとも、束縛したかったんだろうか。
それとも―――私の知らない「好き」が、この世の中にはまだ、あるのかな…。
「…ちょっと、色々とバタバタしてたからね、今日は」
本当は、いつもみたいに「実は野崎さんが」と愚痴ってしまいたかったが、和臣もいるのでそれはできない。また別の機会にでも愚痴ればいいか、と思って、蕾夏は曖昧に言葉を誤魔化した。
「そう言う瑞樹も、なんか疲れた顔してない?」
実際、瑞樹は疲れたような顔をしていた。まあ仕事帰りだからエネルギー切れかけ状態でもおかしくはないが、今日は妙にだるそうに見える。指摘を受けて、瑞樹は不機嫌に眉を寄せた。
「俺も今日は、朝からバタバタしてたんだよ。疲れもするさ」
「なぁ、成田。カクテルバーって、どれがおいしい?」
和臣に腕をぐいぐいと引っ張られ、瑞樹は飲料品の並ぶ冷蔵庫の方を振り返った。
「そんなの、個人差あるだろ」
「オレ、カクテル飲まないからわからないんだよ」
「なら、他のもん飲め」
「嫌だ。このおシャレな瓶が気に入った。どうしても飲んでみたい」
「…お前は瓶で酒を選ぶのかよ」
呆れたような声を出しながら、色とりどりのカクテルの味を和臣に説明している瑞樹を何気なく見ていた蕾夏は、ふとあるものに気づいた。
瑞樹が少し膝を折って冷蔵庫を覗き込んでるからこそ気づいた、際どい位置の、キスマーク。
見つけた瞬間、心臓がドクン、といって、止まってしまったような気がした。
言葉にならないショックが、じわじわと胸をしめつける。蕾夏は目を逸らし、なるべく瑞樹の方を見ないようにした。
***
テレビの画面には、ヒッチコックの名画が流れている。が、蕾夏の頭にはほとんど何も入ってきていなかった。
膝を抱え、その上に顎を乗せた姿勢で、ため息をつく。背後では、瑞樹と和臣が床に転がって眠っている。蕾夏はなんとなく、背後に眠る2人の方を振り返った。
本当は一刻も早く眠りたいのに、一向に眠気に襲われる気配はない。アルコールの力も借りたのに、今日に限って気持ち悪くもならなければ眠くもならないのはどういう事なんだろう? 疲れ果てたように眠っている瑞樹が、ひどく羨ましく思える。
蕾夏は膝歩きで瑞樹のそばに行き、その寝顔を、間近から見下ろした。
―――目、閉じてると、瑞樹って案外、子供みたいな顔してるんだなぁ…。
瑞樹のあの灰色がかった黒い瞳に真正面から見据えられると、蕾夏はいつも少し緊張してしまう。別に目つきが鋭い訳ではない。むしろ、人なつっこい犬みたいな目と表現した方がいい位だ。でも、人の目をまっすぐに見返す瑞樹の視線は、猟犬などに例えられそうな位、静かで、でも好戦的だ。寂しがりやの野良犬みたいな部分と、獰猛な肉食獣みたいな部分を兼ね備えた目―――瑞樹はかなりモテるようだが、案外みんなあの目に惹かれてるのかもしれないな、と蕾夏は思った。
でも、その目を閉じて眠り込んでしまった瑞樹の顔は、まるで子供だ。なんだか拗ねてるみたいな口元も、日頃は前髪で隠れてるのに今はあらわになっている額も、隣で眠る和臣以上に子供っぽい。
こんな顔、どこかで見たよな、と思ったら、喧嘩をした後の瑞樹の顔だった。お前なんか知るか、という風に強情そうに口を引き結びながら、どこかしら後悔してるような顔。そうそう、喧嘩の時も子供みたいだよなぁ、と思い出し、蕾夏は思わずクスクス笑った。
笑ったら、少し気分が晴れた。もしかしたら眠れるかもしれない。そう思った矢先、偶然、瑞樹が着ているシャツの襟元に目が行ってしまった。
途端、和み始めた気持ちが、一気に凍りついた。
偶然見つけてしまった、生々しいキスマーク。
瑞樹がモテるのは知ってたし、深い関係になる事だってあるだろう、位の想像はついていた。でも、想像するのと、その証拠を目にするのとでは、意味が全然違っていた。
それを見た瞬間、ひどくリアルに感じてしまったのだ―――瑞樹も、野崎と同じ、「男の人」なのだ、と。
その時感じた、身体の芯から凍りついてしまうような冷たさを思い出し、蕾夏は思わず身を震わせた。慌ててテレビの前に戻り、また膝を抱える。
―――痛い、なぁ…。
寂しい、とも、怖い、とも違う。痛い。どこが、なのかは自分でもわからない。でも、キリキリと痛む。
瑞樹のそばにいると、蕾夏はいつも、ただの「藤井蕾夏」でいられる。他の人には見せられない子供な自分を、当たり前のように見せられる。瑞樹の前では、「女」である自分に振り回されずに済む。ただあるがままの蕾夏を、瑞樹が受け入れてくれるから。ストレートにぶつけた感情を、瑞樹もストレートにぶつけ返してくれるから。そんな関係は、とてつもなく心地よい。
でも―――…。
「…瑞樹―――私、ここにいてもいいのかなぁ…?」
蕾夏は、画面を見たまま、小さく呟いた。
瑞樹に恋人が出来たのなら、自分は今のこの場所を失う。それを今日、痛切に感じてしまった。
一度知った心地良さを、果たして自分は潔く手放すことができるだろうか―――蕾夏は、そのことを考え、一晩中眠ることができなかった。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |