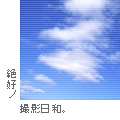| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
『今週末、ボク、東京行くんやけど、ハル時間空いとる?』
珍しい人物からの突然の電話は、内容も藪から棒だった。
「…今んところ、空いてるけど」
『よっしゃあ。実はな、大学時代の先輩が、仲間何人か集めて写真の個展やるらしいんや、東京で。ハル、写真好きやろ? 一緒に行かへん?』
「へーえ…何、プロ?」
『いや、アマチュアのクラブ。こないだ電話した時チラッとハルの話をしたら、えらい興味持ちおってな。絶対声かけぇよ言われててん』
要するに、アマチュアクラブの勧誘だろう。社会人になってからは、そういった団体に属したことがないので、アマチュアのレベルを確認する意味でも結構意義があるかもしれない。
「わかった。行く」
『おおきに。助かるわ。断られたらどうしよかと思ってた。…あ、そうそう』
さもついでに、といった感じに、"猫柳"は付け足した。
『ライも誘ってるから。ミニオフやなー。楽しみ楽しみ』
―――お前のメインはそっちなんじゃないか?
妙に嬉しそうな声に、瑞樹はそう突っ込みを入れた。
***
"猫柳"とは、5月のオフ会に1度会っただけだが、蕾夏を除けば、唯一チャット以外の交流のある人物である。
同い年であること、瑞樹が関西圏に長く住んでいたため共通の話題があること、非常に親しい先輩がアマチュアカメラマンであること、などの理由で、オフ会で一番話の合ったのが、この"猫柳"だった。外見がかなり異様ではあるが、中身は能天気でふっきれた性格である。誰もが彼を気に入ったらしく、オフ会が終わる頃には、すっかり「猫やん」の愛称で呼ばれるようになっていた。もっとも、その愛称のせいで、肝心の本名の方は全員の頭からすっぽり抜け落ちる羽目になったのだが。
このところ瑞樹は、せいぜい週に1回程度しかチャットルームに参加していないが、"猫柳"とは結構頻繁にメールのやりとりをしている。蕾夏も同じのようだ。
『猫やんから? うん、メールで連絡あったよ。写真展がどうのこうのって』
その日の夜、蕾夏に電話で確認したところ、そんな返事が返ってきた。
「行くのか?」
『うん。週末暇だし。あ、でも…カズ君と奈々美さんの秋葉原での店頭デモも、今週末だよね』
「まあな。1日中やるらしいから、猫やんと会う前に顔出せばいいんじゃない?」
『そっか。じゃ、両方行こっと』
蕾夏は楽しげにクスクスと笑うと、
『3人だけだけど、これってちょっとしたミニオフだねー』
と言った。
―――お前もそっちがメインかよ。
また突っ込みを入れつつも、案外自分もそっちがメインかもな、と瑞樹は苦笑した。
***
「おーっ、本物のハルや! おひさおひさ」
5ヶ月振りに会う"猫柳"は、やっぱり不可思議な出で立ちで2人を出迎えた。
アロハはさすがに季節感がないと思ったのか、
「ライも相変わらずちっこいなー」
「猫やんが大きすぎるんだよ」
はるか上空から見下ろされて、蕾夏は露骨にむくれた。"猫柳"は190近い身長だから、まさに「見下ろされている」といった感じだ。
「何や、今日、サングラス大会でもあったの? 2人してサングラス持ってるけど」
"猫柳"に指摘を受けて、瑞樹と蕾夏は引きつり気味の笑顔を浮かべた。本当は、この直前に寄ってきた奈々美の店頭デモを見学する際の変装小道具だったが、一発で瑞樹と蕾夏だとバレてしまい、ほとんど意味がなかったのだ。
「なんだよ、サングラス大会って」
「ボクも知らん」
「…とにかく、猫やんとペアルックしたかった訳じゃねーから、そこだけは間違えるな」
「おうっ、わかっとるで。グラサンといえばレイ・バンと決まっとる。さすがはハルや。それに比べて、なんや〜、ライのその丸眼鏡はぁ。おのれはラスト・エンペラーかいっ」
随分と古い映画を引き合いに出されて、更に蕾夏はむくれた。
「で!? 猫やんの先輩たちの個展って、どこよ」
「このギャラリーの2階らしいで。どうせ客なんてほとんど入ってへん筈や。とっとと見て、とっととミニオフになだれ込もう!」
やっぱり"猫柳"は、そっちが主目的だったようだ。苦笑しつつ、2人は"猫柳"の長身の後に続いた。
***
ギャラリーの2階には、ざっと40点ほどの写真が展示されていた。8名のサークルなので、1人あたり5点程度という計算だ。
"猫柳"の先輩という人は、"猫柳"とは正反対に、背が低く温厚そうで大人しい感じの人である。ベタベタな関西弁の"猫柳"に対し、この先輩は何故か標準語を喋る。不思議に思ったら何のことはない、地元密着型な"猫柳"だが、大学時代だけ東京で下宿し、東京の大学に通っていたのだそうだ。東京に友人が多いと言っていたのも、これで納得がいった。
「君がハル君かぁ。
「…はあ、どうも」
なんだか仰々しい名前が続いて、瑞樹と蕾夏は面食らった。どうやら、"猫柳"の本名が「中尊寺」で、この先輩の名前が「勅使河原」らしい。どうもピンとこない。"猫柳"が、この風体で「中尊寺」とは詐欺だ。
「こっちの女の子は、えーと、ライちゃんだったかな?」
先輩が確認するように"猫柳"の方を見る。"猫柳"は、うんうん、と頷いていた。どうやら蕾夏の話もしているらしい。どんな紹介の仕方をしたんだろう、と、蕾夏は少々不安になった。5月のオフ会が、瑞樹以外の全員が「"rai"って女だったのか!」と驚愕したところからスタートしているだけに。
「君も写真撮るの?」
「いえ、私は見るの専門です」
「そうかぁ。じゃ、とりあえずどんどん見てって」
展示されている写真は、人物像がほとんどだった。子供の写真、老人の写真、おそらくは恋人の写真、家族の写真―――いずれも、プロのモデルではないらしい。スナップ写真もあるが、大半は、ポーズを取ったいわゆるポートレート写真だ。
「人ばっかりですねぇ」
蕾夏が素直な感想を述べる。
「うん。うちは、ポートレートを好む連中の集まりなんだ。僕が撮ったのは、そこの5点ね」
女性ばかり5点のポートレートを指さし、先輩はにっこり笑った。瑞樹の目から見ても、そこそこのレベルに達している写真だ。
「どう? ハル君も、うちに入って、一緒に撮ってみない?」
「あ、いや、俺、ポートレートは撮らないんで」
「え、そうなの? なんで?」
不思議そうにする先輩に、瑞樹は曖昧に笑ってお茶を濁した。
「もしかして、苦手意識があるとか? だめだなー。なんでも撮ってみないと。今日カメラ持ってきてる?」
「ええ、まぁ」
いつもの習性で、デイパックには愛用のカメラが入っている。素直に肯定してしまったが、次の言葉を聞いて、肯定したことを瑞樹は激しく後悔した。
「よし! じゃあ、今から撮りに行こう!」
「は!?」
「ほら、ここに被写体もいるし! 目の前は公園だし! 天気はいいし! 青空写真教室だよ、どう?」
そう言って、先輩は“被写体”の蕾夏の肩をポン、と叩いた。
***
10分後、一行はギャラリーの向側にある公園に出ていた。
青空写真教室の名のとおり、初秋の空は真っ青に晴れ渡っていて、絶好の撮影日和である。小さな公園には他に人もいず、何の撮影会だ、と好奇の目で見られることはなさそうで、被写体役の蕾夏はひとまずほっとした。
「おおっ! ハル君の愛用機はライカM4か! 渋いなぁ」
瑞樹のカメラを見て、先輩が嬉しそうな声をあげた。瑞樹は、日頃会社に行く時は一眼レフを、休日は愛用のライカM4を持ち歩く癖がある。初めてライカM4を見せてもらった時には「これが私の名前の由来のカメラかぁ」などと妙な感動を覚えた蕾夏だったが、改めてその名を耳にすると、なんだか自分の名前を呼ばれているようで落ち着かない。
「猫やんがモデルになりなよ…私はいいよ」
蕾夏はそう"猫柳"に小声で頼んだが、"猫柳"はにんまりと笑い、
「あかん、勅使河原先輩は女性専門のカメラマンや、ライ以外ここに女はおらんのやから、諦めい」
と斬って捨てた。
「撮るのはハルじゃん…」
「ハルかて男撮るより女撮る方が楽しいに決まっとるわ」
―――そうでもない気がするけどなぁ。
見る人が見ればやる気ゼロとすぐわかる瑞樹の様子を窺いつつ、蕾夏は小さくため息をついた。蕾夏自身、あまり写真に撮られるのは好きではない。父がカメラマニアだったので随分写真は撮られたが、あれは家族だからできた事だ。カメラを向けられると極端に緊張してしまう
「えーと、まず被写体の気分をリラックスさせないとね。ライちゃん、リラックスリラックス」
先輩は笑顔でそう言うが、言われてリラックスできるのなら苦労はない。どうやってリラックスしろと言うのだ。
「ハル君。僕、レンジファインダーのカメラって使った事ないけど、こういう撮影って問題ない?」
「…ない、ですが」
「じゃ、とりあえず僕が先撮らせてもらおうかな。ライちゃーん、こっち向いて」
本人たちは全然やる気が無いのに、何故周囲はこんなにやる気満々なのだろう―――蕾夏は仕方なく、先輩と瑞樹の方を向いた。
「無理に笑う必要はないからね。自然に自然に」
「は、はぁ…」
自然に、と言われても、自然にしてると笑えないのだ。カメラがこちらを向いているから、どうしても緊張してしまうから。
笑ってるような、困ってるような表情を浮かべると、先輩の後ろで見ていた瑞樹がくっと笑った。
「…何よ」
「いや、面白いと思って」
「ひっどい。何それっ」
「まーまー、自然に言うても、急には無理やんな」
とりなすように"猫柳"が間に入った。先輩も苦笑し、カメラを構えた。
「へー、ライちゃんて髪が綺麗だねぇ。ちょっとくるっと1回転してみて」
「え? えーと…こうですか?」
請われるままにくるり、と1回転する。すると、カシャカシャとシャッター音が連続した。
「は!? 撮ったんですか!?」
まさか回転してる間に撮られるとは思っていなかった蕾夏は、驚いたように先輩に言った。が、先輩はニコニコと温和に笑うばかりだ。
「撮っちゃったよ。どう撮れてるかは現像しないとわからないけどね。動きがあっていい写真になってると思う」
一体自分がどんな顔をしてたのか、どんな格好で回ってたのか、さっぱり思い出せない。現像の結果が不安になってきた。
「でもライちゃん、カメラ映えするね。ハル君も撮ってあげれば? 景色もいいし、いい記念写真になるよ」
「…俺は、いいですよ」
先輩に促されるも、やはり瑞樹は乗り気ではなかった。何かポリシーがあるのか、人物写真を撮ることを極端に嫌がっている感じがする。無理強いは良くないんじゃないだろうか、と、なおもしつこく撮るよう迫る先輩を見て、蕾夏は眉をひそめた。
「別に、ポートレートじゃなくてもいいよ。ハル君、スナップ撮りが得意だっていうから、スナップとして人物撮る事はあるんだろう? それでいいじゃないか」
先輩がそう言うと、瑞樹は少し表情を変え、チラリと蕾夏の方を見た。目が合って、蕾夏の方が少々焦る。慌てて、瑞樹から目を背けた。
瑞樹は、カメラを構えると、レンズを蕾夏の方に向けた。意を決したように、ファインダーを覗く。
その瞬間―――蕾夏は、何かを感じた。
ゾクッとする、なんだかわからない高揚感。
何故だろう…先ほど先輩がカメラを向けた時とは、何かが違っていた。瑞樹の方は見ていないので、蕾夏にはカメラを構える瑞樹の姿は全く見えない。なのに、自分の横顔を捉えるファインダー越しの視線を感じてしまう。心臓が、にわかに鼓動を早めた。
「わ、私、どうしてればいい?」
「別に。猫やんとでも話してて」
視界の外から、瑞樹の声が聞こえる。
「猫やんと話してれば、それでいいの?」
「うん」
話せ、と言われるとまた困ってしまう。"猫柳"と顔を見合わせ、何喋ればいいんだろう、という顔をした。
「…そういえば猫やんて、カメラ向けられてもニッコリ笑えるよね」
「え?」
「オフ会の時、お店の人に集合写真撮ってもらったじゃない。猫やんだけすんごいニッコリ笑ってて、やたら目立ってた」
「ああ〜、あれか。できるで。笑うのなんか造作ないわ。ボクの特技、笑顔やもん」
「特技が笑顔???」
「バリエーション豊富やで。褒められて嬉しい笑顔、お腹一杯食べられて幸せな笑顔、デバック完了後の疲れた笑顔。全部再現できるわ」
「ふーん。凄いね」
「実演したろか? じゃあ、ライ、なんかボクの事褒めてみたって」
わくわく、という顔をして、"猫柳"がそんな事を言った。話せ、と言われて困った蕾夏だが、褒めろ、と言われるのも結構困る。一体何を褒めればいいだろう、と、"猫柳"をつま先から頭のてっぺんまで眺める。
「―――そうだなぁ…」
「…なんや、褒めるとこ、あらへんのか」
「え? ううん、そんな事ないよ。あるある。猫やんのそのTシャツ、凄くカッコイイ。売れてないロックミュージシャンとか着てそう」
"猫柳"が笑う前に、少し離れた場所にいる先輩が吹き出した。
「なっ、なんやそれっ! いっこも褒めてへんやんかっ!」
「カッコイイって褒めたじゃん。はい、笑ってみてよ」
「あー、そーかいそーかい。わかったわ。あああ、嬉しいなあ」
そう言って笑った"猫柳"の顔は、見事なまでの「泣き笑い」だった。まるでマンガにでも出てきそうな完璧な泣き笑い状態に、蕾夏も思わず吹き出した。
「あはははは! 猫やんって、やっぱり面白い!」
大笑いした瞬間、微かなシャッター音を耳にした気がして、蕾夏は慌てて瑞樹の方を見た。
「えっ…」
「―――なんだよ」
ファインダーから目を離した瑞樹が、少し不貞腐れたような顔をしていた。
「え、いや、あの、…撮った?」
「撮った」
―――思いっきり大口あけて笑ってるところを撮られた気がする…。
もうちょっと普通の顔をしているところを撮って欲しかった。蕾夏はガックリと肩を落とした。
「まぁまぁ、そう落ち込まんと。あとで勅使河原先輩に美人に撮ってもらえばえーって」
復讐のつもりなのか、"猫柳"がケラケラと笑いながら蕾夏の背中をバン! と叩く。その言葉は、今の写真が失敗だったことを重ねて証明しているようで、なおさら蕾夏を落ち込ませた。
***
「いい表情が撮れたねぇ」
まだ"猫柳"とドタバタやっている蕾夏を眺めていた瑞樹に、先輩が声をかけた。温和そうな笑顔はそのままで、何を考えているのかいまいちわからない。瑞樹はカメラを下ろし、苦笑した。
「本人はそうは思ってないみたいだけど」
「プリントしてみれば、ライちゃんも納得するよ、きっと。子供みたいな、無邪気でいい笑顔をしてた」
「―――なんであんなに、撮らせようとしたんですか」
実際、先輩はしつこかった。もう放っといてくれ、と言いそうになるほどに。それでも、撮らせようとする先輩の目に何か意味を感じたからこそ、スナップとはいえ“人”を撮る事に同意したのだ。何故ああもしつこく迫ったのか、やはり確認したかった。
「別に、理由らしい理由なんてないよ」
先輩は、あくまで穏やかな調子でそう言った。
「ただ―――ハル君、被写体が“人間”だってだけで、カメラを向けるのを嫌がってるように見えたんだよなぁ。君の隣にいるライちゃん、ずっと楽しげに笑ってるのに…僕ならあの表情、絶対撮るのになぁ、と、ギャラリーに入ってきた時から、ずっと思ってた。せっかくいい被写体を友達に持ってるんだから、ハル君が撮り始めるきっかけになればいいと思った。それだけだよ」
「…別に特に、嫌がってる訳じゃないですよ。好きじゃないだけで」
「そうかな?」
ポケットから煙草を取り出しつつ、先輩は意味深な目を瑞樹に向けた。
「でも、君は、僕なら絶対シャッターボタンを押すっていう絶妙な瞬間に、ちゃんとシャッターを切ったよ。好き嫌いは別にして、ハル君の目はちゃんと人間ていう被写体を理解してる。なのに、勿体無いよ」
「―――スナップなら、撮りますけどね」
でも絶対に、ポートレートは、撮らない。
先輩に穏やかに言葉を返しながら、心の中でもう一度言い聞かせる。そんな瑞樹の様子に、先輩は諦めたように苦笑した。
「しょうがないなぁ。君をうちのサークルに誘うのは、無理そうだね」
「風景専門サークルにでもなったら、また誘って下さい」
瑞樹は薄く笑い、カメラを公園にひっそり佇むオブジェに向けた。
「なーなー、ハル」
いつの間にやらすぐ背後に来ていた"猫柳"が、ポン、と瑞樹の肩を叩いた。
「さっきのライの写真、現像したら、ボクにも送ってな」
他の2人に聞こえないように、瑞樹の耳元に囁く。
「は?」
「ええ顔してたやん、ライ。あれ見てると癒されるわ。部屋に飾っといて、へこんだ時にでも拝もう思って」
そう言う"猫柳"は、ごますりモードの笑顔を満面にたたえている。自分が撮った蕾夏の写真が"猫柳"の部屋に飾られたりするなんて、想像しただけで背筋が寒くなる。
「“現像したら”な」
―――誰がするか。
瑞樹は軽く眉を上げ、カメラのレンズキャップを少々乱暴に嵌めた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |