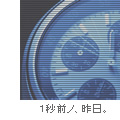| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
東京駅構内の喫茶店で、瑞樹と蕾夏は、2人同時にくしゃみをした。
「あー…思いっきりやられたな」
「ほんと大丈夫? 新幹線、自由席なんでしょ?」
「新幹線は大丈夫。いざとなりゃ床にでもどこにでも座るから。むしろ帰ってからがヤバいかも…。お前こそ大丈夫か」
「私は1時間ちょいだし、在来線1本だしね。―――そろそろ出よっか」
「そうだな」
そう言って、2人はだるそうな表情で立ち上がった。
今日は12月31日―――大晦日。
クリスマス・イブの計画は無事成功し、大いに気を良くして2人だけの盛大なパーティーを開いた瑞樹と蕾夏だったが、寒さのあまり、仲良く風邪をひいてしまった。あれから1週間経つが、あまり回復していない。
瑞樹はここから、新幹線で神戸に向かう。父が住むマンションに、一応“帰省”する訳だ。
「でも、変な感じだよね。お父さんのマンションて、瑞樹自身は全然住んだ事ないんでしょ?」
「そう。なのに“帰省”…妙な気分だ」
喫茶店を出て、2人並んで巨大なコンコースをのんびり歩く。こんな年末ギリギリに帰省する人間が結構いるようで、広い道幅いっぱいに人が溢れ返っていた。
「帰省って、お父さんに会うだけ?」
「その予定。昔の友達に会おうにも、連絡つかねー奴ばっかりだしな。雪山登山してたり、海外勤務してたり」
「大人しく地元で新年迎えるような友達、いないの?」
「…どうせ俺の友達は大人しくねーよ。蕾夏は、同窓会あるんだろ」
「高校時代の、ね。ギリギリまで迷ったけど、一応行くことにした。いきなり新年2日からだよ? 何考えてるんだろう、幹事」
「何も考えてないんだろ」
これが地方だったらわからなくもない。帰省する期間が限られているから、早めに開いてしまおうという事だろう。が、蕾夏の地元の場合、“帰省”する人自体ほとんどいない。みんな自宅から東京や横浜に勤めに出ているからだ。あんな近場に“帰省”する蕾夏の方が特殊なのだ。
それを考えると、やはり心にひっかかる―――蕾夏は何故、わざわざ一人暮らしをしているのだろう、と。
家庭の問題ではないことは、先月藤井家を訪れた時に、ほぼ確信している。適度な自由主義だし、かといって放任している訳でもない。親というよりは兄弟のように蕾夏と接しているあの両親が原因で、蕾夏が家を出るとは思えない。
―――となると、やっぱり、あいつかな。
辻 正孝。彼の姿を見つけた時の蕾夏の硬い表情を思い出し、瑞樹は複雑な気分になった。理由はよくわからないが、なんとなく気に食わない奴。それが瑞樹の辻に対する印象だった。
「お土産、買ってく?」
ちょうど土産物店の並ぶあたりにさしかかり、蕾夏が瑞樹にそう訊ねた。
「土産なんて買った事ないから、いい。鳩サブレも人形焼も、親父、嫌いだし」
「“東京ばなな”は?」
「どうだろう。俺以上に甘いもん駄目だからな」
「…顔だけじゃなくて、味覚まで似てるんだねぇ、瑞樹とお父さんて。おいしいのになぁ、“東京ばなな”…」
お前は“東京ばなな”の回し者か、と言いたくなる位残念そうな顔をする蕾夏に、瑞樹はつい笑ってしまった。
「そうだ。ね、今夜、電話してもいい? 電話で年越しのカウントダウンしよ」
「お前、そういうの好きだなぁ」
「何かの“瞬間”に立ち会うのって、楽しいじゃない」
「…まあ、確かに、悪くないな」
「でしょ? ―――あ、私、ここまでだね」
JRの在来線改札口で、2人は足を止めた。
瑞樹の顔を見上げた蕾夏は、その気だるそうな表情を見ると、心配げに顔を曇らせた。
「…瑞樹? 大丈夫? 熱ある?」
「いや? あんまり自覚はないけど」
すると、蕾夏の手が伸びてきて、瑞樹の額にピタッと押し当てられた。冷たい手のひらが心地良い。思いのほか、自分の額が熱かったことに気づく。
「ほら。やっぱ、熱ありそう」
「俺が熱あるんだったら、お前も多分熱あるぞ」
同じように、蕾夏の額に手をあてる。手のひらに感じる熱は、平熱ではなさそうだ。
「あー…ほんとだ」
熱のせいで少し潤んだ黒い瞳が、上目使いに瑞樹を見上げる。その目に、思わず瑞樹は、蕾夏の額に押しあてた手を反射的に引っ込めた。
「どうかした?」
「―――別に」
不思議そうに訊ねる蕾夏に、ついぶっきらぼうな返事を返してしまう。
―――こいつ、今自分がどんな目したか、全然わかってねーんだろうなぁ…。
「そう? じゃ、今晩電話するから。気をつけて帰ってね」
「お前も無理すんなよ」
蕾夏は嬉しそうに笑うと、手を振りながら、改札の方へと走っていった。
―――ああいう時は、子供なんだけどな、どう見ても。
ギャップの激しさに、こちらの感情の切り替えがついていけない。瑞樹は、にわかに熱が上がり始めたように感じる頭を軽く振り、新幹線改札口へと向かった。
***
この時期、帰ってくる人間より地方へ出て行く人間の方が多いせいか、見慣れたホームは、11月に来た時以上に寒々としている気がした。
手をコートのポケットにつっこみ、蕾夏は肩を縮めた。北風で髪がパラパラと視界にかかるが、それをはらうために手を出す気にはなれない。うるさそうに目を細め歩き出すと、腕にかけた小ぶりなボストンバッグが下がってきてしまったので、諦めて手を出した。手袋を持ってくれば良かったかな、と、少し後悔する。
電車の中で眠ったのが良かったのか、熱は少し下がっているようだ。額に押し当てられた瑞樹の手のひらの感触を思い出すと、くすぐったいような感じがして、知らぬ間に口元がほころぶ。
新幹線、今どの辺走ってるのかな、などと考えつつ何気なくホームを振り返った蕾夏は、ふと思い立ち、バッグを地面に置いた。
切符を指に挟んだまま、両手の親指と人差し指をピンと90度に立てると、その4本の指で四角いフレームを作る。それを目の前にかざすと、視界の中に、四角く切り取られた風景が現れた。画家や写真家が、構図を決めるのによくやるポーズだ。
少し色の落ちたベンチと、フェンスの向こう側に立つ冬枯れした木を画面の中心に据え、そこからゆっくりと左に体を回してゆく。フレームの中に描かれる風景も、それにつれて移動してゆく。
―――へえ…、駅って、結構絵になるんだ。気が付かなかった。
真っ直ぐに伸びる線路や、駅名の入った看板、遠くに見える遮断機―――普段、何気なく見ているものが、1枚の絵として考えると、どこか郷愁を帯びた風景に見えてくる。まるで映画のワンシーンを切り取ったみたいだ。
新鮮な感動に暫し酔っていると、フレームの中に見覚えのあるコートが入り込んで来た。
一瞬、息が止まる。数度瞬き、蕾夏はフレームを作っていた手を崩して、目の前にかかっていた髪を掻きあげた。
改札の向こう側、コートのポケットに手を突っ込んで立っている辻が、蕾夏と目が合って、薄く微笑んだ。
―――なんでこうタイミング良く迎えに来てる訳?
一瞬不思議に思った蕾夏だったが、2日前に大体の帰る時間を母に電話で伝えた事を思い出した。きっと、今回の情報の出所も母だろう。蕾夏は小さくため息をつくと、地面に置いたバッグを手にして、少し重い足取りで改札を抜けた。
「お帰り」
「…ただいま」
駅には、駅員以外、誰もいなかった。いつもなら電車を待つ人が風を避けるように集まっている筈のベンチの周辺にも、人影は全く見当たらない。元々小さな駅だし、学校も会社もない大晦日の昼間では、乗降客が少ないのも当然だろう。
「随分ギリギリに帰ってきたもんだね」
荷物を持とうか? という風に、辻がボストンバッグに視線を走らせたが、蕾夏は首を横に振った。もとより、持ってもらうほどの荷物ではない。
「特に変わりはない?」
「うん。仕事も、人間関係も、問題ないし」
「そう、か。―――とりあえず、少し、歩きながら話そうか」
そう言って、辻は、またいつものように手を差し出してきた。ごく自然な、柔らかな笑みを浮かべて。
蕾夏は、複雑な気分で、辻の手を見下ろしていた。触れた時のあの冷たさを思い出し、無意識のうちに身震いする。
辻を、傷つけてしまうかもしれない。でも、次にこういう機会があったら、絶対に言おうと決めていた事だ。言うなら、早い方がいい。
「…辻さん」
意を決し、蕾夏はまっすぐに辻の目を見つめた。
「私、もう、一人でも大丈夫」
辻の表情が、僅かに強張った。それを見て、蕾夏の胸がチクリと痛んだ。
「辻さんがいなくても、ちゃんとやっていける。だから―――もう、辻さんの手はいらないの。一人で歩けるよ」
“辻さんの手はいらない”―――酷な言い方だ、と、もう一人の自分が蕾夏を責める。でも、蕾夏は、その声にあえて耳を塞いだ。
辻に繋がれた手。それが、2人の関係を象徴するものだった。その手を振り払う意味を、蕾夏も辻もよくわかっている。蕾夏はきゅっと唇を引き結ぶと、差し出された手から目を逸らして、辻のすぐ横をすり抜けた。
いや。
すり抜けようとした。
「…一人で大丈夫、だって?」
背後から聞こえた、辻の感情のこもらない声に、蕾夏は思わず足を止めた。
辻の手が、蕾夏の肩を掴む。その予想外の力に、蕾夏の手からボストンバッグが離れた。トスン、という鈍い音をたてて、コンクリートの床の上に落ちる。
「! 辻さ―――」
名前を叫ぼうとした刹那、辻の左腕が蕾夏を背後から抱きしめた。みぞおちに食い込むほどの腕の力に、声がねじ伏せられてしまう。
「もう、一人でも平気だって、本当に、そう思ってるの?」
そう言いながら、辻の右手の指が、蕾夏の背中をなぞった。
右肩から、肩甲骨の上を通って、左斜め下に―――もうある筈もない傷跡を辿るように、正確に。
―――ドクン。
蕾夏の心臓が、大きく痙攣し、瞬時に全身が強張った。
「あ……」
一気に襲い掛かる、「あの日」の記憶。
その瞬間、蕾夏の頭の中で、目も眩むばかりのフラッシュが光った。
「や―――…!!」
悲鳴をあげかけたところに、辻の大きな手のひらが、蕾夏の口を塞いだ。
悲鳴―――というよりは、絶叫。
神経が焼き切れるほどに叫んだのに、それは全て辻の手に遮られて、駅員にすら届かなかった。そんなシチュエイションまでが「あの日」と重なり、蕾夏の恐怖心を増幅させる。抵抗すら忘れて声にならない悲鳴をあげる蕾夏を、辻は宥めるかのように抱きしめ続けた。
「…蕾夏」
耳元で、まるで言い含めるみたいに、辻が名前を囁いた。辻に名前を呼ばれるのは前から嫌いだった。一気に全身が総毛立つ。
「まだ君は立ち直ってなんかいない。たったこれだけの事で、簡単に14歳の君に戻ってしまうんだから。君には僕がまだ必要な筈だ。違う?」
―――違う! 違う、違う!
パニックを起こしながらも、蕾夏のどこかがそう言っている。暴れ狂う自分の中の恐怖に
「たとえ違っていても、僕には君が必要なんだよ。…頼む、離れないでくれ」
僅かに残った理性が、辻の掠れた声に罪悪感を覚える。でも、同じ理性が、こうも言う―――辻が差し出す手を、握ってはいけない、と。
辻は、待っている。蕾夏がどうすれば追い詰められるか知り尽くしているからこそ、耐え切れなくなって蕾夏が縋りつくのを待っている。辻の思惑通りになるのだけは、死んでも嫌だった。
―――絶対に、辻さんの手は、とらない…!
精神が暴走しかけたところを、際どいところで踏みとどまる。蕾夏は唇を噛むと、辻の手の甲に思いっきり爪を立てた。
「……っ!」
痛みに辻の腕の力が緩んだところで、蕾夏は体を捻り、辻を力いっぱい突き飛ばした。驚くほどあっさり辻の足元がよろめき、蕾夏は辻の腕から解放された。
心臓が、暴れる。
まるで何百メートルも全力疾走したみたいに、呼吸が乱れ、震える。蕾夏は、自らの腕を抱くようにしながら、必死に深呼吸を繰り返した。大きく吸って、少し止めて、肺が空っぽになるまで吐いて―――かつて辻から教えられた通りの深呼吸を、何度も何度も繰り返す。
一方の辻は、少し傷ついたような、でも後悔を滲ませた表情で立ち竦み、蕾夏に爪を立てられた手の甲を、微かに震えている手で押えていた。
「……ごめん」
苦しげな、いつもより幾分低い声で、辻がそう呟く。その声に、蕾夏もようやく顔を上げた。
辻の目を見て、蕾夏の中に広がったのは、怒り以上に、絶望感だった。
少なくとも、辻は今まで、蕾夏を助けようとしてくれていた。その事だけは間違いない。なのに―――その彼が、自ら蕾夏の傷口を広げようとした。塞がりかけた傷を更に
お前の傷を、その弱さを、その痛みを思い出せ―――と。
―――…痛い。
気が違いそうに、痛い。
蒸し返された傷が痛すぎて、罵る言葉も出てこないよ…。
蕾夏は、のろのろとボストンバッグを掴むと、足をひきずるようにして、その場を立ち去った。一度も、辻の方を振り返らずに。
悲しかった。どうしようもなく。大声で泣きたいほどに。
でも、「あの日」がそうであったように―――やっぱり蕾夏は、泣くことができなかった。
***
「何これ。親父が作ったの?」
ビールの空き缶をキッチンのごみ箱に放り込んだ瑞樹は、ダイニングテーブルの上に置かれた重箱に目を止め、父にそう声をかけた。
リビングのソファに座って新聞を広げていた父は、それをチラリと見、瑞樹とよく似た仕草で肩を竦めた。
「俺がそんなに上手く作れる訳ないだろう?」
「じゃ、誰」
「名前がなぁ…思い出せないんだよ。外注の女の子だと思うんだけど」
「…またかよ。去年のおせちも、名前の思い出せない誰かが作ったんだったよな?」
「中年の一人暮らしだから、気の毒がって差し入れしてくれるんだよ。ありがたく受け取らないとな」
―――ただの差し入れが、こんなに凝ってる訳ねーだろ。
金粉を散りばめたかまぼこや、どう見ても手作りな栗きんとんを見下ろして、瑞樹は眉を顰めた。
学生結婚だった父は、まだ50前で、実年齢も若いが、見た目もかなり若い。瑞樹と父が並んでいても、親子と思われる事は稀だ。帰ってくる度におせち料理の作り手が違う事からもわかる通り、今でも結構もてているらしい。歳考えろよ、と思う瑞樹だったが、一人侘しい生活を送られるよりはましか、と最近は割り切っている。
「構わねーけど、いい加減、1人に固定すれば? じき50だろ。そのうち誰も見向きもしなくなるぜ?」
「ハハ、いいよ、見向きもされなくても。今更再婚する気なんてないしな」
そう言って笑う父の顔に、瑞樹は複雑な表情を浮かべた。
「―――まだ、思ってる訳? 例の“運命の女”ってやつ」
「なんだ。そんな話、まだ覚えてたのか」
父は、ちょっと意外そうに目を見開いたが、瑞樹の苦々しげな表情を見て言わんとするところを察したのか、困ったような笑顔を浮かべた。
「瑞樹は不服かもしれないけど、仕方ないさ。俺の人生を動かすほどの女なんて、もう二度と現れない。
「…別に、不服じゃないよ」
瑞樹は、微かに笑みを浮かべてそう言うと、おもむろに傍らに脱ぎ捨てていたジャケットを掴んだ。
「なんだ? 出かけるのか?」
「いや、ベランダに出るだけ。親父、先に風呂入っとけよ」
瑞樹の手に煙草や灰皿が握られているのを見て、煙草を吸わない父は、納得したように笑った。
腕時計を確認すると、今年も残り10分足らずだった。
まだ風邪の気だるさは抜けきっておらず、6階のベランダに吹きつける風は少々寒すぎた。が、頭をクリアにするにはちょうどいい感じだ。瑞樹は、今年最後の煙草を口にくわえ、火をつけた。
ベランダから眺める神戸の街は、穏やかだった。おととしあたりは、震災の爪あとがまだ色濃く残っていて、さほど被害のなかった地区とはいえ、青いビニールシートのかかった屋根などが点々と確認できたものだ。
神戸にそれほど愛着がある訳ではないが、第二の故郷である事は間違いない。完全に復興を遂げる前に、震災の名残を写真におさめておいた方がいいのかもな、と、瑞樹はぼんやり考えた。
と、その時、瑞樹の携帯が、ポケットの中で震えた。
おそらく、蕾夏からだろう。近所迷惑になるかと思い両隣の様子を窺ったが、転勤族の多いこのマンションは、大半が帰省で留守にしているようだ。急いで携帯を取り出し、通話ボタンを押した。
「はい」
『瑞樹?』
やはり、蕾夏からだった。耳慣れた声に、神経がふっと緩む。
「ああ。風邪の具合、どうだ?」
『ん、大丈夫。瑞樹こそ、具合はどう? 熱下がった?』
「昼間よりは大分マシ。煙草吸うんで、今、マンションのベランダに出てるとこ」
『は!? 外に出てるの!? 駄目じゃない、また風邪悪化するよ』
「大丈夫だって。結構人起きてるな、この時間。外歩いてる人も見える。蕾夏は今、どこから?」
『自分の部屋。ラジオで“行く年来る年”聞いてるの。ほら、時報がわかるから』
「……」
瑞樹はふと眉をひそめ、煙草を灰皿の縁でもみ消して、携帯を持ち直した。
「―――蕾夏?」
『え、なに?』
「お前、泣いてるのか?」
『―――…え?』
電話の向こうで、息を呑む気配。
確かに声は明るい。泣き声も入ってなければ、うわずった調子もない。が…どこか、違和感があったのだ。必死にいつもの蕾夏を演じているような気配が。
「―――どうしたんだよ」
『…泣いてないよ』
「…ふーん」
『ほんとだよ?』
「あいつと、何かあった?」
返事はなかった。図星だと言っているようなものだ。
思い出されるのは、あの日見た、辻 正孝の敵意剥き出しの冷たい目―――何があったにせよ、気分のいい話でないのだけは間違いない。蕾夏にとってだけではなく、瑞樹にとっても。
やっぱり最初の印象通りの、気に食わない奴だ。瑞樹は苛立ったように、もみ消した煙草をもう一度灰皿に押し付けた。
『…あ。あと1分だって』
「…ああ。こっちでも見てる」
窓ガラス越しに、部屋の中のテレビの画面が見えた。年末の風景をバックにして、時計のアニメーションが時を刻んでいる。
2人とも何も話さず、時が経つのをじっと待った。
―――3、2、1、0。
ようやく、長針と短針が、文字盤の12の数字の上で重なった。
『…Happy New Year.』
柔らかなトーンの、でも完璧な発音の“Happy New Year”が耳に届く。瑞樹も、少し口元をほころばせた。
「あけましておめでとう」
ただの新年の挨拶だが、そう言葉を交わすと、なんとなく優しい気持ちになれた。
『―――なんか、不思議だね』
「何が?」
『だって、秒針にしたら、ほんの1ミリ動いただけなのに、昨日はもう“去年”だなんて』
「…ああ。確かに、そうだな」
昨日は、もう「去年」。僅か1秒前の事が、もう「去年」の事なのだ。
―――新年早々、「去年」の事を蒸し返すのも酷だよな。
「…東京戻ったら、初詣行って、賽銭投げゲームでも写真におさめるか」
少しふざけた調子でそう瑞樹が言うと、ほっとしたように、蕾夏が小さな笑い声をたてた。
『あはは、いいね。ついでに、おみくじ引きレースも写真におさめようよ』
いつもの調子を少し取り戻した蕾夏の声に、ささくれ立った神経も少し慰められた気がする。
が―――押さえ込んだ苛立ちを表すかのように、瑞樹の指先は、ずっと、煙草の吸殻を灰皿に押し付け続けていた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |