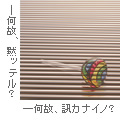| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
「それでさ―――成田、聞いてる?」
和臣が非難がましい声をあげる。
瑞樹は、ぼんやりした顔を和臣の方に向けると、だるそうに前髪を掻き上げて、
「聞いてる」
とだけ答えた。
丸テーブルを囲むようにして、瑞樹、和臣、久保田の3名が顔を揃えている。何故男ばかり3人で新年会をやる羽目になったのか、そのいきさつはいまいち不明だが、和臣が思う存分ノロケられる、という意味で、女性陣がいないのは幸いだった。
和風な酒の肴ばかり並ぶテーブルで、全員珍しく冷酒を飲んでいた。あまり強くない和臣は、既に顔がかなり赤い。
「でねぇ〜。奈々美さんの着物姿って、目茶目茶可愛いんだよ。やっぱり暖色系が似合うよね。年上だなんて嘘みたい。売店のおじさんにも“可愛いガールフレンドだねぇ”なんて言われたし」
「良かったな」
久保田が、そう相槌をうちつつ、肉じゃがを頬張る。他に相槌の打ちようもない。既に30分近く「良かったな」以外の相槌は打っていない気がした。
まあ、気持ちもわからないでもない。あれだけしつこく「奈々美さん、奈々美さん」と追っかけ回していた相手を、やっと「彼女」と呼べるようになった訳だから。多少浮かれまくっても大目に見よう。和臣のおノロケを聞き流す位、久保田には造作ないのだし。
―――むしろ、問題はこっちだよな。
和臣の話を聞いているフリをしながら、久保田は、隣に座る瑞樹の様子を時々窺っていた。
先月あたりから、どうも様子が変だとは思っていたが、そろそろ「異常」の域に入りつつある。年末年始の休暇を終えてからというもの、エネルギー切れを通り越して、ほとんど幽体離脱だ。一体何があったのだろう? と、久保田は勿論のこと、同じ部の佳那子も相当心配をしている。
「ねー、久保田さん。今度ダブルデートしましょうよ。オレ、デートとかあんまりした事ないから、どこ行けばいいのかわかんないんですよ」
「アホか。俺にだって、そんなのわかる訳ないだろ」
迷惑千万、という顔で久保田が和臣を睨むと、人の会話など聞いてないだろうと思われた瑞樹が、ぼそりと呟いた。
「ジャズ・バーのライブなんていいんじゃねーの」
「―――…瑞樹…お前、とことん性格悪いな」
クリスマスに、瑞樹と蕾夏の策略にまんまと嵌められた事を思い出す。箸を持つ久保田の手がぷるぷる震えた。が、そんな久保田を一瞥して、瑞樹は片眉を上げてふっと笑う。
「人の顔盗み見してる暇あったら、カズのデートコースでも真剣に考えてやれば」
―――こ…こいつは〜〜〜っ!
「そうですよ。久保田さん、真剣に考えて下さいよ。オレ、ほんとに困ってるんですからね」
何故久保田が怒りに震えてるのか全く理解していない和臣は、そう言って口を尖らせた。
「だって、オレのゴールは、あくまで“結婚”だもん。付き合い始めたけど、これからが勝負でしょ。見てろよ、成田。オレはお前より先に結婚してみせるっ」
「何の競争をしてるんだよ、お前は」
瑞樹は、少し迷惑そうにそう突っ込みを入れ、運ばれてきた冷奴を自分の前に引き寄せた。
「あ、そうそう。成田、藤井さんにお礼言っといてね。元はといえば、彼女が奈々美さんの相談に乗ってくれたから、ここまで漕ぎつけた訳だし」
「…わかった」
冷奴をつつきつつそう答えた瑞樹だったが、その言葉をきっかけに、また考え事に嵌り込んでしまった。
***
どこか遠くの方で和臣の浮かれた声を聞きながら、瑞樹は、大晦日のことを思い出していた。
瑞樹は、蕾夏の声に関しては、かなり勘が働く方だ。日々の感情の微妙な変化が、声から嫌でも感じ取れてしまう。多分、顔も名前も知らない状態で長く電話をし続けていたため、たった1つの情報源である「声」に対して、普通以上に感度が鋭くなってしまったのだろう。
だから、わかってしまうのだ。
大晦日にあった、あの電話の声の、異常さが。普通を装った声の、その裏に隠れている本当の声が。
一緒に初詣撮影に行った時、表面上、蕾夏は特に変わった様子もなかった。
初めて出席した高校の同窓会の事、両親と興じた元旦七並べ大会の事、体調不良でほとんど会えなかった翔子の事―――そんな帰省中の話を、明るく喋っていた。おみくじを引いたら大吉が出て大喜びしていたが、正月はそういう風に仕組まれてるんだ、と瑞樹がクールに言い放つと、気分をそがれたと言って憤慨したように背中を叩いてきた。
あまりに普段通りな蕾夏。その姿に、大晦日の夜の電話は存在しなかったかのような錯覚を覚える。
だが、それでも瑞樹は、気づいていた。
蕾夏は何度か、何か言いたげな目を瑞樹に向けてきていた。何かを抱え込んで苦しんでるような目を。そういう目をしておいて、次の瞬間、必ず目を逸らしてしまう。そして、また何事もなかったかのように、口にしなかった“何か”を飲み込んでしまう。普段の蕾夏になってしまえば、その“何か”は欠片も見えなくなる。
―――あいつ、なんで、俺に何も言わないんだよ。
「…みーずーきー、なんかお前、怖いぞ」
「え?」
久保田の声に、瑞樹は我に返った。見れば、久保田も和臣も、少々引きつった顔をして瑞樹を見ている。
「なに」
「成田、怖いよ。なんか、例の“2、3人殺してそうなオーラ”を発してた」
和臣の言葉に、そんな馬鹿な話あるか、と、瑞樹は冷奴を見下ろした。
考え事をしながら無意識に箸を動かしていたらしく、冷奴は不揃いに12分割されていた。
「……」
久保田と和臣の視線が痛い。努めてその視線を無視し、瑞樹は小さくなりすぎた冷奴を口へ運んだ。
「―――なんかなぁ。最近のお前、ちょっとおかしいよ。よくぼーっとしてたり、急に不機嫌になったり。どうかしたのか?」
久保田が、心底心配した声でそう言う。瑞樹はその言葉さえ無視して、黙々と冷奴を平らげる。どうしたのかなんて、自分でもよくわからない。答えられる筈もなかった。
―――辻 正孝。
なんでこう、この男の存在に苛立たされるのか。
彼が蕾夏の異変の原因なのは察していた。が、何があったのかを察するには、瑞樹はあまりにもあの2人のバックボーンを知らなさすぎる。そのことに、瑞樹は苛立っていた。
そして更に苛立つのは―――「それ」を知ったところで、一体自分はどうしたいのか、それがわからないことだった。
***
「…蕾夏ちゃん、聞いてるの?」
佳那子が呆れたような声を出したので、蕾夏は考え事からはっと我に返った。
こちらも、やはり丸テーブルを囲むようにして、佳那子、奈々美、蕾夏の3人が顔を揃えている。男性陣同様、女性陣も新年会を行っているのだ。
「大丈夫、聞いてるよ」
「クレームだからって、耳が聞くのを拒否してるんじゃないの?」
「あはは、それはちょっとあるかも」
「…いい根性してるわね」
気分を害したという目で蕾夏を睨む佳那子に、奈々美は耐え切れずに声をたてて笑ってしまった。
「か…佳那子にこんな目させるのって成田君位のもんだと思ってたけど…凄いわー。藤井さん、尊敬しちゃう。さすが成田君の親友やってるだけの事はあるよね」
「冗談じゃないわよ、ナナ! もう、クリスマスってことで右も左も前も後ろもカップルだらけよ!? そんな中にいきなり放り込まれて、私も久保田も散々気まずい思いしたんだからっ!」
「あ、でも、演奏は良かったでしょ?」
ケロリとそう言う蕾夏に、佳那子は思い切り脱力した。
「…ええ、良かったわよ」
「じゃ、いいじゃない」
にこっ、と笑った蕾夏は、続けて、信じられないような事を口にした。
「久保田さんと佳那子さん、飲み歩く以外、2人きりではあんまり出掛けられないんでしょ? クリスマスやバレンタイン・デーみたいな恋人っぽいイベントも避けてるみたいだし。たまには恋人気分味わうのも悪くなかったんじゃない? ね?」
「―――…」
佳那子の顔から、血の気がさーっと引いた。
―――なんで、何も事情を知らないこの子が、こんなポイント押さえまくったコメントを言う訳!?
何か事情を推測させるような失言、過去にしたかしら…何も思い浮かばないけど。そういえばこの前、久保田も言ってたわね。どこまでかはわからないけど、成田にも事情が一部バレてそうだ、って。でも、口の堅い成田が、何か知っててもそれを蕾夏ちゃんに話すとも思えないし…。
―――悪魔コンビ、おそるべし。
メーターを振り切った心拍数と今も吹き出す冷や汗を誤魔化すべく、佳那子もワイングラスに口をつけた。
「なぁに? 佳那子たちって、やっぱり恋人同士なの?」
事情を何一つ察していない奈々美が、キョトンとした顔で、蕾夏と佳那子の顔を見比べる。
「違うわよっ」
「ふーん…なんだ、残念。神崎君、久保田君と佳那子もまじえて、4人でダブルデートしたい、なんて言ってたのに」
「…冗談でしょ。やめてよ」
「やだぁ、大丈夫よ。私がそんな事させないもの。せっかく彼氏が出来たのに、何が悲しくて佳那子や久保田君と一緒にデートしなくちゃいけないのよ」
「……」
―――ナナ。あんたって奴は…。恋人できると、こうも変わっちゃう訳?
女の友情なんて、儚いものだと痛感する。奈々美は今後、何につけても「神崎君」優先だろう。よかったわね神崎、と、心の中で自棄気味に祝福しておいた。
半分幸せボケ状態な奈々美は、楽しげに初詣の話を始めてしまった。それ、昨日も聞いたわよ、と思いつつ、佳那子は隣の蕾夏の様子を窺う。
―――やっぱり、どこか、おかしいわよねぇ…蕾夏ちゃん。
再び虚ろな表情になってしまった蕾夏を、佳那子は心配そうに見つめた。
***
どこか遠くの方で楽しげな奈々美の声を聞きながら、蕾夏は、大晦日のことを思い出していた。
あの日蕾夏は、駅から実家までの短い道のりを、いつもの3倍の時間をかけて歩いた。
辻に対する憤りと罪悪感の狭間で、蕾夏はいまにも押しつぶされそうになっていた。加えて、忘れかけていた過去の痛みが、それまでの何倍もの凶悪さで襲い掛かってくる。果たして正気を保ち続けられるか、自分でも自信がなかった。
でも、蕾夏は、こういう事態には免疫があった。14歳の自分にできたのだから、25歳の自分にできない筈がない―――そう言い聞かせた結果、家の玄関をくぐる頃には、一応「いつもの蕾夏」の仮面を被る事ができた。
両親に心配をかける訳にはいかない。何も事情を知らないのだから。蕾夏は、精神力を総動員させて、いつものように笑い、いつものように話した。
だが、一人っきりになると、途端に防御壁がガラガラと崩れた。
久々に寝転がる自宅の2階のベッドの上で、蕾夏は体を丸めて震えた。辻の言葉は正しい。自分では相当回復しているつもりでいたのに、あんな些細な行為で、蕾夏は14歳の頃に戻ってしまっていた。
なんとか「今」に繋がりたくて、蕾夏は約束通り、年越し直前に瑞樹に電話をかけた。
不思議なほどいつも通りの声で喋る自分を、蕾夏はどこか別の次元で見ていた。可笑しい―――本当は震えてるのに、まるで何もなかったみたいな、自分の声。その声を聞いていると、本当に何もなかったような錯覚すら覚える。
なのに。
―――蕾夏? お前、泣いてるのか?―――
瑞樹の言葉に、蕾夏は凍りついた。
何故、わかってしまったんだろう? 自分ですら錯覚するほどなのに、何故瑞樹は、まだ涙1つこぼしていない蕾夏の異変を感じ取ってしまったんだろう?
絶句するしか、なかった。あいつと何かあったのか、と訊ねる瑞樹に、口を開けば洗いざらい話してしまいそうで。洗いざらい―――そう、今日あった事を説明するなら、全部話す羽目になる。そんな勇気は、到底ない。
でも、瑞樹に訊ねられたら、答えてしまいそうな気がする。だからこそ、問いただされる事を、蕾夏は一番怖れた。
そんな蕾夏の不安をよそに、初詣に行った時も、その後の電話でも、瑞樹は何も訊いてこなかった。時折、何か言いた気に蕾夏を見つめることはあるが、実際には、何も言わない。
ホッとした。
でも、ホッとする反面、心のどこかで「訊いて欲しい」と思っている自分に気づき、愕然とした。
―――何故瑞樹は、何も訊かないんだろう?
「らーいーかーちゃん。そろそろ現実世界に戻ってくれない?」
佳那子にそう言われ、蕾夏はまた我に返った。
見れば、いつの間にかシフォンケーキがテーブルに並べられていて、佳那子と奈々美は既に半分を食べ終えている。どの位、考え事に没頭していたのだろう? 恥ずかしくなって、蕾夏は思わず赤面した。
「ごっ、ごめん! やだなぁ、ケーキが来たなら来たで、声かけてよ」
くすくす笑う2人を見ないようにして、慌ててシフォンケーキを食べ始める。
―――訊いて欲しい。そして、話してしまいたい。その思いは確かにある。誤魔化しようが無い。
でも、全てを知ってもらう事に何の意味があるのか―――それは、蕾夏自身にもわからなかった。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |