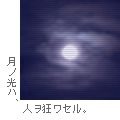| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
―――月の光は、人を狂わせる―――。
誰に聞いたんだったかな、そんな話、と、瑞樹は、吸い込まれそうな光を放つ満月の写真の前で、そんな事を考えた。
「静かで、幻想的で、でもなんとなくあったかい写真だね」
隣に立った蕾夏も、その写真に惹き込まれている。落とし気味な照明も、写真の世界に浸るには良い演出となっていた。
「時田郁夫の写真にしては地味だけど、傑作だよな」
『幽玄』と名づけられたその写真は、『写真家・時田郁夫展』ではかなり目立たない部類のもので、会場でも一番角に、ついでといった感じで飾られていた。すぐ隣に飾られた巨大なアンコールワットの写真の方が人目を惹く。が、『幽玄』は、静まり返った湖面と、上空に浮かぶ満月の対比が叙情的で、見ていてまさに「惹き込まれる」感じがする写真だった。
「―――そろそろ行くか。あいつら、もう見終わってるんだろ?」
「あ、そうだね」
外で待っているであろう久保田と佳那子の事を思い、2人はやっとその写真の前を離れた。
ビルの外に出ると、1月下旬の海風がもろに吹きつけて、思わず身を竦めた。辺りは既に暗く、まだ低い位置にほぼ満月の月が輝いている。これはこれで、なかなか『幽玄』な風景だった。
「おーそーいー」
ようやく現れた蕾夏と瑞樹に、すっかり体の冷えてしまった佳那子が文句を言う。隣の久保田が、まぁまぁ、とそれを宥めた。
「早くどっか入ろう。俺も寒い」
***
写真家・時田郁夫の個展の招待券は、久保田が取引先から貰ったものだった。
偶然ではあるが、時田郁夫は、瑞樹がここ数年、最も注目している写真家だ。どうせなら1人か、瑞樹の影響で時田郁夫の写真が気に入ったらしい蕾夏と見たいところだったが、「スポンサーは俺なんだからな」の久保田の一言には逆らえない。何故か、佳那子も交えた4名で来る羽目になってしまった。
「やっぱり冬のお台場は寒いわねぇ」
やっと落ち着いたカフェで、ワインを片手に佳那子がそう言う。口では文句らしき事を言ってはいるが、表情は笑顔だ。
―――なるほどね。俺たちはダシに使われた訳だ。
2人きりでの外出は難しくても、4人ならOKといったところなのかもしれない。別に久保田と佳那子の事情を全て知り尽くしている訳ではないが、おおっぴらに“恋人”と言えない事情があるらしいのは察している。瑞樹と蕾夏はちょっと目を合わせ、たまには協力してやるか、という風に苦笑を交わした。
「寒いけど、いい写真沢山見れたし、月も綺麗だから、文句はないんだろ?」
「ま、そうね」
久保田の言葉に、佳那子もまんざらでもない口調で肩を竦める。
「でも、成田がそんなにカメラが好きだとは知らなかったわ。カメラ持ち歩いてるのは知ってたけど、撮ってるのなんて見たの、江ノ島の時だけだし。―――久保田は? 見たことある?」
「あるある。大学時代はほとんど毎日。そういやあ、屋上とか銀杏の木の下で、よくカメラ抱えたまま居眠りしてたよな。何しに大学来てるんだろコイツ、っていつも思ってた」
「…うるせーよ」
瑞樹がむっとしたように眉を顰める。そんな瑞樹を見て、サラダを取り分け終わった蕾夏は、クスリと笑った。
「でも、夢中になれる趣味があるっていいよね。写真撮ってる時の瑞樹って楽しそうだもん」
フォローを入れるかのように、蕾夏がそう言うと、久保田が意外そうな顔をした。
「藤井さん、瑞樹が写真撮ってるとこ、よく見るの?」
「ん、去年の秋位から、撮影についてってるから」
「へーえ…退屈じゃない? 撮ってる間、藤井さん、何もする事ないだろ」
「全然。面白いよ。一緒に被写体探して歩いてると、いろんな物が見つかるしね。この間も、東京のど真ん中だってのに、キツツキがあけた木の穴見つけちゃったし」
その時の蕾夏のリアクションを思い出し、瑞樹は思わず声を殺して笑った。
あの時蕾夏は、それを見つけた次の瞬間、「あー! キツツキの巣だー!」と大声で叫んだかと思うと、まるでおもちゃを見つけた子供みたいに、猛ダッシュで走って行ってしまったのだ。あれは巣じゃねーよ、木の中にいる虫を食った跡だよ、と冷静な解説を加えたが、最後まで蕾夏は「キツツキの巣」を連呼していた。
「…何よ」
「いや、別に」
面白そうに忍び笑いする瑞樹を、蕾夏が軽く睨んだ。そんな2人の様子を見て、最近2人とも少し様子がおかしい、と感じていた久保田と佳那子は、少しほっとした。
「瑞樹、今日はカメラ持ってきてるのか?」
「一応」
「なら、帰りに月撮れよ。俺の部屋に飾りたい」
「無理。三脚持ってきてねーし、第一、寒い」
その時、久保田と瑞樹の会話に割って入るように、突如、携帯電話の着信音が響いた。
途端、サラダを食べていた蕾夏の手と、ワイングラスを取ろうとしていた瑞樹の手が、それぞれビクン、というように止まった。
着信音は、間違いなく、蕾夏の膝の上に置かれたバッグの中から響いている。曖昧な緊張感が、2人の間に流れた。
「あの…蕾夏ちゃんの電話じゃない?」
「え…あ、うん」
佳那子の指摘を受けて、少し慌てた様子で、蕾夏はバッグから携帯電話を取り出した。が、もたもたしていたせいか、半分位取り出したところで、着信音は切れてしまった。
でも、瑞樹は気づいていた。携帯の液晶画面を僅かに確認した蕾夏が、一気に体を強張らせたのを。
嫌な予感に、背中にゾクリとした冷たさを感じる。
「あー…っと、切れちゃった、ね」
取り繕うように、蕾夏は久保田と佳那子に苦笑を返している。久保田や佳那子も、どこか釈然としない違和感を感じながらも、特に何も口にはしなかった。
が。
携帯電話をバッグに戻しかけた時、また着信音が鳴った。今度はさすがに、4人全員に緊張が走る。
一瞬硬直した蕾夏の手が、かろうじて携帯を引き出した。その時、偶然、液晶画面に表示されている名前が、はっきり瑞樹の目に入ってしまった。
―――“辻 正孝”。
「……っ」
その後の行動を計算するより早く、瑞樹は蕾夏の手から携帯をもぎ取り、通話ボタンを押していた。
「みっ、瑞樹っ!?」
驚いて声をあげる蕾夏に背を向け、携帯を耳にあてる。
『…藤井さん?』
携帯から聞こえてきた声は、どこか不安げではあるが、間違いなく辻の声だった。歯噛みしたくなるような苛立ちを胸の奥に感じながら、瑞樹は感情を抑え、口を開いた。
「成田です」
『え?』
電話の向こうの辻の気配が、うろたえたような雰囲気に変わる。が、瑞樹はそれを無視した。
「―――失礼します」
それだけ言うと、素早く電話を切り、そのまま電源も切った。あまりの対応に、久保田も佳那子も、目を見開いて唖然とした。
「ちょっ…と、成田!」
佳那子が、思わず非難の声をあげる。
けれど、当の蕾夏は―――混乱した表情で、声も出せずに、瑞樹を見ていた。全力で耐えていたものが決壊しそうな、動揺しきった目で。
―――もう、限界だ。
瑞樹は唇を噛むと、蕾夏の腕を掴み、荒々しく席を立った。
「…悪い、隼雄、30分で戻る。それまでここで待ってて」
「は!? ど、どこ行くんだよ!?」
「絶対、追ってくるなよ」
呆然とする2人を残し、瑞樹は蕾夏と自分の分のジャケットを掴むと、蕾夏を引っ張ってカフェの外へ出た。
***
「ね、ねぇ、瑞樹、痛いってば」
腕を引っ張られながら、蕾夏はまだ困惑の残った声で抗議した。なのに、瑞樹は立ち止まらない。誰もいない夜の海浜公園をどんどん歩いていってしまう。
「瑞樹! 痛いっ!」
だんだん腹が立ってきて、蕾夏は瑞樹の背中に怒鳴った。無視されるのは、腹が立つ以上に心細い。
「止まってよ! 大体なんで勝手に人の電話取ったの!? 佳那子さんたちだって驚いてたじゃない! あんな事やめてよっ!」
唐突に、瑞樹の足が止まった。蕾夏の腕を掴んだままくるりと振り返った彼の顔は、本気で怒っていた。
「…だったら、話せよ」
その怒りを抑えたような声色に、思わず一歩、
「なんで何も言わないんだよ! 俺が訊かないからか!? 俺があの電話から今まで、ずっと平気でいたとでも思ってんのかよ!?」
「お…思ってないっ!」
「じゃあ話せ!」
「何を話せって言うのよ!」
「お前が話したいって思ってる事をだよ!」
蕾夏の顔色が変わった。
―――私が、話したいと思ってる事…?
辻と何があったのか、と訊かれると思っていた。予想を覆す言葉に、うまく頭が回らない。
「…話したい事なんて、ない」
「嘘つけ。そんな目しといて、何もない訳ねーだろ」
「瑞樹とは関係ない事だもの。瑞樹に話す事なんてないっ」
「関係ない?」
切り離されたようなその一言に、瑞樹の苛立ちがピークに達した。
「関係ないなら、なんで俺がこんなに振り回されてるんだよ!? お前がなんでそんな目するのかわかんねぇと、誰でもない、俺が困るんだよ! いくら関係ないってお前が言っても、もう巻き込まれてる。もう関係あるんだよ!」
瑞樹の言葉に、蕾夏は息を呑んだ。
また、崩されていく予感がする。
グラグラと揺さぶられる。奥深く、鍵をかけておいたものをこじ開けられる。
―――…もう、限界かも、しれない。
動揺に瞬きも忘れていると、少し冷静になったのか、瑞樹が蕾夏の肩にコートをかけてくれた。ふわり、と肩があたたかくなる。
「…ありがと…」
掠れる声でそう小さくお礼を言って、緩慢な動きでコートに袖を通した。襟元をぎゅっと握ると、なんだか少し安心できる気がする。
瑞樹も自分のジャケットを羽織り、自らを落ち着かせるように大きく息を吐き出してから、改めて周囲を見渡した。少し離れた所にベンチがあるのを見つけて、蕾夏の方をかえりみる。
「―――座るか?」
「…ううん、いい」
小さく首を振る蕾夏に、「そうか」と短く呟くと、瑞樹はポケットに手を突っ込んで、黒い海の方を眺めた。つられるように蕾夏も視線を向ける。
月が、さっき見たよりも高い位置に輝いている。ビル群や船のあかりを水面に映している海は、頬に感じる風とはうらはらに、波もほとんどなく穏やかだった。そんな風景を、2人とも、暫く黙って眺めていた。
「―――前に言ったよな。言いたい事を飲み込むな、お前らしくない、お前らしくないのが一番嫌だ、って」
「…うん」
「言いたくない事は、何も言うな。…その代わり、お前が言いたい事は、全部聞くから」
「…どんな話でも?」
「―――どんな話でも、それをお前が話したいんなら、ちゃんと聞くから」
一切迷いのない、揺るぎない、瑞樹の声。
その言葉に、心のどこかで、カチャリ、と鍵の開く音がした気がした。
***
「―――…“好き”って、一体、何なんだろう」
長い長い沈黙の後、蕾夏が、ポツリとそう呟いた。
唐突な話に、瑞樹はちょっと眉をひそめ、蕾夏の方を見た。蕾夏は、少し虚ろな表情で、相変わらず海を眺めている。
「…想いが受け入れられなかったら、相手を憎んで傷つける―――それが“好き”って気持ちなのかな。…だったら私、どうすれば良かったんだろう…」
「―――辻さんの事か?」
「…辻さんも、そう」
「も?」
「…中学の時の、同級生も、そう」
蕾夏は、小さくため息をつくと、ふいに瑞樹の方を見た。その肩が微かに震えているのに気づいて、瑞樹はますます眉を寄せた。
やめさせた方がいいんじゃないだろうか、そう思い始めた時、蕾夏が、ゆっくりと口を開いた。
「―――私ね、昔、背中に傷があったの。もう、消えたけど」
「傷?」
「その同級生に、酷い目に遭わされた時の、傷」
「…酷い目、って…」
不吉な予感に、心臓がざわめく。が、蕾夏は、目を逸らさず、あくまで淡々とした口調で続けた。
「―――ナイフで脅されて、レイプされそうになった時の、傷」
瑞樹の顔色が、変わった。
「…床に引きずり倒されて、気失う位叩かれて、抵抗してるうちに背中を斬られて―――もの凄く、怖かった。でも、一番怖かったのは…」
耐え切れなくなったように、蕾夏は視線を落とした。
「―――…気がついたら、私も、相手を斬りつけてた事」
声など、出る筈も、なかった。
頭が、ガンガンした。その場面を想像して、吐き気すら覚える。自分が動揺してもどうにもならない、そうは思っても、つい口元に当てた手が震えてしまう。
目の前で、自らの腕を抱くようにして俯いている蕾夏を、改めて凝視する―――小さな肩に、細い手足。中学生なら、今の蕾夏以上に華奢だっただろう。そんな体で、それほどの暴力に耐えられたとは、到底信じられない。
「―――結局、未遂で終わったけど…あれ以来、私、時々事件のフラッシュバック起こすようになっちゃったの。あの時感じた怖さや痛さや、手に握ったナイフの感触が甦ってきて、気が違いそうになるの」
そこまで話して、蕾夏は大きく息を吐き出した。やはり、話すのには勇気が要ったのだろう。吐き出す息も、どこか震えている。
ふいに顔を上げ、心配げな顔をしている瑞樹と目が合うと、蕾夏は微かに微笑んだ。
「…そんな顔、しないで」
「…こんな顔しか、できねーよ…」
「初めて、人に話した、この話。…親にも先生にも…辻さんにも、話さないできたから」
幾分穏やかな表情になった蕾夏は、また、暗い海の方を眺めた。海風で乱れた髪を、冷たくなった手で掻き上げながら。
「―――辻さんはね、まだ医大生だったのに、私を送り届けてくれた友達から聞いた切れ切れの説明だけを頼りに、精一杯の事してくれたの。フラッシュバック起こした時も、ずっと手を握っていてくれた。もう君は誰も傷つけてないし、誰も君を傷つけてないよ、って言い聞かせてくれた―――あの頃、私がバラバラにならないように繋ぎ止めてくれたのは、間違いなく辻さんだったの。…なのに―――…」
蕾夏は言葉を切り、唇を噛み締めた。コートを握る指先が、力が入ったせいで血の気を失う。
「この前の大晦日の日、その辻さんが―――私にフラッシュバック起こさせたの」
瑞樹の表情が、にわかに険しくなる。
「あの時の悪夢をもう一度思い出させて、私をバラバラにしようとしたの。あの、辻さんが」
「…何で?」
「―――私が、もう二度と辻さんの手はとらないって、決めたから」
「……」
その言葉で、瑞樹は、理解した。あの時の辻の、冷たい視線の理由を。
彼は、蕾夏が離れて行くのが、許せなかったのだ。
ずっと手の中で大切にしてきた蕾夏が、回復して、自分の手の中から飛び立つのが、我慢できなかった。たとえそれが間違っている衝動でも、縛り付けずにはいられなかった。
―――蕾夏のことが、“好き”、だから。
「…私、どうすれば良かったんだろう…?」
海を見つめる蕾夏の目に、次第に涙が浮かんできた。
「私、辻さんを許せない…。治りかけた傷を抉って、私に突きつけた。そんなの、許せない。でもそれ以上に―――私、自分が許せないよ」
「…お前は何も悪くない」
瑞樹の呟くような声に、蕾夏は大きく首を横に振った。
「あんなに辻さんを必要としてた癖に、辻さんが私を必要とした時には、何ひとつ返す事ができないなんて―――なんで私って、こんなに身勝手で弱いんだろう? 私、どうしても自分が許せないよ」
「―――もう、よせって!」
いたたまれなくなって、瑞樹は蕾夏の両肩を掴んでこちらを向かせると、その目をまっすぐ見据えた。
「お前は弱くない! 身勝手でもない! そんな事言うな!」
瑞樹の勢いに飲まれたように、蕾夏は目を丸くして、息を呑んだ。
「お前は“患者”で、あいつは“医者”だろ。なら、お前があいつにできる事は“回復する事”だけじゃねーのか? なんで回復するのに罪悪感感じるんだよ。何ひとつ返す事ができないなんて言うな。お前は一つも悪い事してない!」
蕾夏の、涙の浮かんだ黒い瞳が、動揺したように揺れた。
瑞樹の言葉は、理解できたのだろう。だからこそ、心を動かされ、動揺してるのだろう。
でも―――それでも罪悪感を拭えないだけの長い歴史が、蕾夏と辻の間にはある。たった一言で、そんな長い時間を補う事などできないのだ。
―――痛い。
瑞樹の中のどこかが、キリキリと、締め付けられるように痛みを訴える。正気を保てないほどに。
「…瑞樹?」
急に黙り込んだ瑞樹を、蕾夏は戸惑ったような目で見上げた。2、3度瞬くと、それまで耐えていた涙が、蕾夏の頬にこぼれ落ちた。
その涙に誘われたように―――瑞樹は蕾夏を引き寄せると、その唇を衝動的に奪っていた。
***
―――これは、狂気だ。
他に名づけようなんてない。極彩色の、暴走する狂気。月の光は、人を狂わせる―――本当の事かもしれない。
なんで俺、こんな事してるんだろう、と、瑞樹の中の冷静な部分が自問する。同情? それとも辻への対抗心だろうか―――それなら、自分も辻と同じ独占欲の塊にすぎないのか、と自嘲的になる。
なんでもいい。
今感じてるこの痛みが、消えてくれるなら。
互いの痛みを唇で受け止めるように、くちづける。何度も、何度も、何度も。体は凍えそうなのに、唇だけが、熱を持ったように熱い。その熱に浮かされたように、制御不能な狂気に身を任せ続けた。
それは、甘美というには程遠く、ひたすらに―――切なかった。
「―――…っ!」
突然、驚いたように瑞樹が唇を離した。
いきなり途切れた狂気に、一瞬、頭の中が空っぽになる。やはり現実に戻りきれていないような目をした蕾夏と、至近距離で視線がぶつかった。
蕾夏の肩から手を離すと、瑞樹は、胸ポケットの中から携帯電話を取り出した。が、取り出している途中で、微かな音をたてて震えていた携帯は、ピタリと止まってしまった。
「…間に合わなかったな」
前髪を掻き上げ、液晶画面を確認すると、瑞樹の表情が微かな苦笑いに変わった。
「…な、に?」
「早く戻れって催促だろ」
そう言って、瑞樹が蕾夏の方に向けて見せた携帯の液晶画面には、くっきりと久保田の名前が表示されていた。そういえば、30分で戻ると言って出てきたが、約束した時間はとっくに過ぎている。
携帯をポケットに放り込み、まだ微かに残る混乱を振り切るみたいに2、3度頭を振ると、やっと頭が正常な状態に戻ってきた。
目を上げ、すぐそばに佇む蕾夏の顔を見ると、頬を伝っていた涙で、風で乱れた髪が頬に貼りついていた。無意識のうちに手を伸ばし、その絹糸みたいな髪を指ではらう。そんな瑞樹に、蕾夏は思わず顔を赤らめ、視線を逸らした。
「…キ…ス、しちゃったね」
「―――そうだな」
逸らされている蕾夏の目は、戸惑っている一方で、どこか不安げだった。
言いたい事は、わかる―――性別を超えた“親友”という安寧の居場所を失うのを、彼女は恐れている。心地良い2人の距離が変わってしまうのではないかと、不安を抱いている。
―――じゃあ、自分は?
自分は今、どちらを望んでいるのだろう―――?
「―――…ま、いいじゃん。俺たちの関係が“何”なのかなんて、定義しなくても」
瑞樹は苦い笑いを浮かべ、蕾夏の頭にポン、と手を乗せた。涙は止まったものの、まだ僅かに潤んでいる蕾夏の困惑した瞳が、瑞樹を見上げてくる。
「…いい、の、かな」
「いい。…何があろうが、どんな呼ばれ方をするようになろうが…突き詰めていけば、“親友”である事だけは変わらないだろ?」
「…うん」
その言葉に、ほっとしたように、蕾夏が表情を和らげた。
―――そう。どちらを望んでいるのだとしても…これが、今言うべき言葉だし、多分永遠に変わらない事。
自分の言葉に、瑞樹自身も、どこかほっとしていた。
「…っと、そうだ。これ」
ふと思い出し、瑞樹は、ジャケットのポケットを探って、蕾夏の携帯電話を取り出した。さっき取り上げたままになっていたのだ。
「悪かった―――やり過ぎだった」
蕾夏の手を取って、その手に携帯をしっかり握らせる。それを見下ろしながら、蕾夏は小さく首を振った。
「多分、もう1回話し合いたいって電話だったと思うから―――私、出てもうまく話せなかったと思う。瑞樹に取り上げてもらって、良かったかもしれない」
「次は、ちゃんと出ろよ」
訝しげに眉をひそめて、蕾夏は瑞樹を見上げた。
「逃げるなんて、お前らしくねーよ。お前らしくないのが、一番嫌だ」
「…でも、私、まだ辻さんに罪悪感持ってるよ?」
「大丈夫だって。―――お前は、強い奴だ。卑怯な手にも暴力にも屈しない。自分を貫くためなら、相手を傷つける事も厭わない位に。そうしながら、相手に負わせた傷を思って泣く優しさも持ってる―――やっぱり、最強の女だよ」
「……」
「…いいじゃねーか、傷つけても。傷つけて平然としてるお前じゃない事位、辻さんだって百も承知だろ。傷つけた分、同じだけお前も心痛めてる―――それでいいんだって」
そう言って、瑞樹は蕾夏の頭をぐしゃぐしゃっと撫でた。そんな瑞樹を、蕾夏は驚いたような表情で見上げていた。
“君は誰も傷つけてないし、誰も君を傷つけてない”―――いつも辻が言っていたセリフが、頭を掠める。
あの言葉に救われているような気がしていた。それに安心しながら、傷つけたくない、傷つけられたくない、と、手足を縮めていた。
…でも、瑞樹は、違う。
傷つけてもいいと―――その傷を思って涙すればそれでいいと、言ってくれる。傷つけられても、それをはね返すだけの強さを蕾夏が持っていると言ってくれる。
―――なんでこの人は、いつもいつも、私の欲しい言葉をくれるんだろう…。
蕾夏は、やがてふわりと柔らかな笑顔を浮かべ、手にした携帯電話をぎゅっと胸に抱いた。
「…ありがとう」
―――1つだけじゃなく、いろんな、意味で。
「じゃ、戻るか」
「うん」
ポケットに手を入れて、少し間を空けて、2人並んで歩く。
でも蕾夏は、見えない手がしっかりと自分に繋がれている事を、カフェまでの道程の間、ずっと感じていた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |