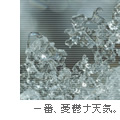| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
佳那子は、セーターにGパンというラフな服装の上にダウンジャケットを羽織ると、玄関を出た。
午前6時半。2月上旬の朝は、まだ暗い。玄関脇の犬小屋の中を覗きこむと、愛犬のデュークが顔を出し、尻尾を振った。
「おはよ、デューク」
慣れた手つきでリードをとりつけ、いつものように散歩に出た。
デュークは、ちょうど遊びたい盛りのビーグル犬で、歩く速度も、リードを引く力も、佳那子にはちょうどいい。適度な歩調で、近所をぐるりと回る。それが佳那子の、出社前の日課なのだ。
が、今日はちょっと、勝手が違った。
「…冷たっ…」
歩き出してすぐ、何か冷たいものが頬に当たった。雨かな、と思ってダウンジャケットの袖を見ると、雪とも雨ともつかない水滴が、いくつかへばりついていた。
―――みぞれ…かな。
みぞれ混じりの雨は、佳那子が一番嫌いな天気だ。嬉しそうに尻尾を振っているデュークには悪いが、佳那子はダウンジャケットのフードを被ると、家へと引き返した。
***
昼休みに会社の窓から外を見ると、外は雨だった。暗い空なのは相変わらずだが、佳那子はどこかでほっとした。
「…あいつ、何かあったのかなぁ…」
背後のデスクに座っている久保田が、ぼんやりした調子でそう呟いた。下のファミレスで、瑞樹とランチを食べに行ったとばかり思っていたが、いつの間にか戻ってきていたようだ。
「何、誰のこと?」
「瑞樹だよ」
「ああ…去年の終わり頃から、集中力欠いてるわね」
「いや、そうじゃなくて―――ここ1、2週間の事だよ」
「1、2週間?」
佳那子は眉をひそめた。
去年の11月か12月あたりから、瑞樹はずっと、様子がおかしかった。仕事中に他の事を考えるなんて皆無だった男がディスプレイを眺めてぼんやりしている姿には、佳那子ならずとも首を捻ったものだ。
だが、言われてみれば、ここ1、2週間は、元の瑞樹に戻っている気がする。仕事中は完全に仕事に没頭し、休憩時間になるとフラリとどこかへ消え、また戻ってくると感心する位のスピードで仕事をこなしていく。ぼーっとしてる姿も、妙に苛立ってる姿も、確かに見かけなくなったようだ。
「蕾夏ちゃんと喧嘩でもしてて、仲直りしたんじゃない? 元に戻ってくれて良かったわ」
「元に戻った、かねぇ…」
久保田はそう言って眉を顰め、どこか憮然とした風情でプラスチックのコップに入ったコーヒーを飲んだ。その視線を辿ると、ミーティングデスクで和臣と話をしている瑞樹がいる。別におかしなところは無さそうだが、と、佳那子は首を傾げた。
「俺には、前とも違ってきてる気がするけどなぁ…」
「そう?」
「佐々木にはわかんないかもしれないけどな」
確かにわからない。ただ、久保田が、瑞樹の様子をもの凄く気にしている事だけは、よくわかる。佳那子は、久保田の隣の席を借り、腰を落ち着けて聞くことにした。
「あいつって、いっつもフラフラしてただろ。上手く説明できねーけど…誰に対しても無関心で、下手すると自分自身に対しても無関心で、友達も恋人もいらねぇの一言でバッサリだし―――どこ見てるのか、何考えてるのか、誰にもわからない。一匹狼っつーか、その瞬間しか生きてないっつーか…」
「…ああ、うん。そうね、それは、わかるわ」
「昔からそういう、掴みどころがなくて、刹那的な奴だったけど―――なんか、ここ1、2週間で、変わってきてる気がする」
「どの変が? 私には、いつもと同じに見えるけど」
「―――目が、変わってきた。なんて言うかこう、人生の方向性見つけたというか、適当に流されてた奴がちゃんと地面に足つけて歩き出したというか―――とにかく、今のあいつ、今までと違う空気をまとってる」
久保田はそう言って、心もち眉を顰めたような顔で、またコーヒーをすすった。何か、そう思わせるような特別なシーンにでも出くわしたのだろうか?
「でも久保田。地に足がついたり、方向性を見出したりしたんなら、それはいい傾向なんじゃないの?」
極当たり前のように佳那子が言うと、久保田は何故か、大きなため息をついた。
「―――普通は、確かにな」
「え…」
「…瑞樹が“変わる”のは、たとえ傍目には良い傾向でも、俺は不安なんだよ」
―――多恵子に対して、そうだったように。
久保田の、口にしなかった言葉が、聞こえた気がした。
佳那子の胸が、ズキンと痛んだ
***
夕方になるにつれ、気温が下がり始め、雨は次第にみぞれへと変わっていった。
定時を過ぎたところで、佳那子はまた窓の外を見た。雪と言うには水を含みすぎている白い物体が窓を叩き、微かな氷の粒を窓に残して融ける。その様を眺めていると、気分は一気に憂鬱になった。
ふと振り返ると、瑞樹の席はもぬけの殻だった。休憩に入ったのだろう。
そう言えば瑞樹は、休憩時間になるとよくどこかへ消えてしまう。どこに行くのだろう、と思った事は何度かあるが、日頃あまり気にした事はなかった。いつだったか雑談ついでに和臣に訊いた時、和臣は「屋上じゃないかなぁ。たまに行ってるみたいだし」と答えていた気がする。
屋上など、佳那子は一度も行った事がない。どんな所なのだろう?
―――なんでこう、今日はナーバスになってるのかしら。
理由は、大体察してはいた。この天気のせいだ。そして、昼休みの時の久保田の言葉のせい。
「…あー、もうっ」
苛立ったように爪を噛むと、佳那子は上着を羽織り、事務所を抜け出した。
***
エレベーターが最上階に到着し、屋上に続く短い階段を上ると、鉄製の重いドアが立ちはだかっていた。
少し急いたようにそのドアを押し開けると、次の瞬間、だだっ広いコンクリートの空間が目の前に広がり、佳那子は一瞬息を呑んだ。
数歩、歩き出すと、みぞれが頬を叩いた。その冷たさにぞっとすると、妙な不安がせり上がってきた。
「成田!」
思わず名前を呼ぶと、想像とは全く違った所から返事が返ってきた。
「佐々木さん?」
ちょっと驚いたような声が背後から聞こえ、佳那子は慌てて振り返った。
瑞樹は、階段へと続く鉄扉のすぐ横の壁にもたれかかって、立っていた。Tシャツにダンガリーシャツだけの事務所内にいた時と同じ服装で、特に何をするでもなく腕組みをしていた。
「珍しい。何か用?」
訝しげに眉をひそめる瑞樹に、佳那子は急に安堵し、体の力を抜いた。
「な…なんだ、そんな所にいたのね…」
「―――なんでもいいけど、そこ、雨当たるぜ?」
そう言われて、瑞樹が何故そこにいるのかわかった。この広い屋上の中で、扉のある部分だけが
―――馬鹿みたい。何しに来たのかしら、私。
自分の行動に、自分で嫌気がさす。
屋上から連想したのは、やっぱり多恵子の事―――でも、今佳那子の目の前には、ぐるりと屋上を取り囲むように、頑丈な金網が張り巡らされている。誤って落ちる事は勿論、自らの意志で身を投げるのも不可能だ。
チラリと瑞樹の方を見ると、瑞樹は相変わらず、腕組みしたまま落ちてくるみぞれを眺めていた。いきなり現れた佳那子に、再度用件を訊く様子もない。
―――やっぱり、この、天気のせい。
瑞樹は覚えていないだろうが、実は佳那子は、大学時代の瑞樹に一度だけ会った事がある。会った、というよりは、一方的に佳那子が彼を見かけただけだが。
時間にして10分かそこらの、偶然。でも、強烈に覚えている。
佳那子は、重い気分で、灰色の空をぼんやりと眺めた。
***
多恵子が死んだ夜に降っていた雪は、明け方には雨に変わり、通夜が行われた夕方頃にはみぞれに変わっていた。
半ば久保田に支えられるようにして、佳那子はなんとか通夜の会場に辿り着いた。ショックのあまり、到底一人では立てない状態に陥っていたのだ。
大学生の時に母が病死してから、まだ3年しか経っていない。人の死は、その時の記憶がオーバーラップして、ただでさえ辛い。ましてや多恵子の場合、死因は自殺である。しかも―――死の直前まで一緒にいたのに、佳那子は今夜多恵子が死ぬ気だなんて、少しも気づく事ができなかったのだ。あまりにもショックが大きすぎて、佳那子には耐える事ができなかった。
一方の久保田は、案外落ち着いていた。
久保田は、大学時代に何度も覚悟させられていた。多恵子が薬を飲む度、手首を切る度、今度こそ駄目かもしれない、と思わされてきた。今度こそ駄目だっただけで、いつ「今日」が来てもおかしくはなかった。だから、思いのほか落ちついていられたのかもしれない。
多恵子は、顔は無事だったそうで、祭壇に置かれた棺の小窓を開ければ死に顔に会う事ができた。が、次々に訪れる弔問客は、誰も彼女の顔を見ようとはしなかった。久保田も、佳那子も、やはり焼香するのが精一杯で、とても顔を見る勇気はなかった。
「最後まで、多恵子と親しく付き合ってくださったそうで…」
上品そうな中年女性が、ハンカチで目元を抑えながら、久保田と佳那子に頭を下げた。初めて会うが、これが多恵子の母らしい。そういえば、顔立ちがどことなく似ていた。
多恵子の父の方は、魂がどこかへ行ってしまったような面持ちで、祭壇の多恵子の写真を眺め続けていた。医者として、かなりの成功を収めた人物だと聞いているが、そんな威厳も自信も、目の前にいる初老に近い男性からは感じられなかった。
なんとなく立ち去り難く、多恵子の母を慰めるような会話を交わしつつ、2人は暫くその場にとどまった。その間にも弔問客は切れることなく訪れ、焼香とお悔やみを繰り返していく。
そんな時だった。
「悪い、ちょっと、はずすから」
隣にいた久保田が、ふと入り口の方を見て、佳那子の耳元でそう言った。誰か知り合いが来たらしい。佳那子は頷き、なんとなく久保田が歩き去るのを目で追った。
久保田の視線の先には、黒っぽいジャケットに身を包んだ男性が1人、立っていた。
傘をささずに来たのか、彼の髪は僅かに水を含んでいた。ジャケットの表面にも、水滴がいくつもついている。邪魔そうに前髪を掻き上げた彼は、歩み寄る久保田を見て、微かに微笑んだ。
「お前が来てくれるとは、思わなかったよ」
「佐倉さんから連絡もらったから」
密やかな声で会話する2人を、佳那子は祭壇横の多恵子の両親のそばで見ていた。久保田の表情や口調から、どうやら後輩らしいな、と察しながら。
彼も、他の弔問客同様、焼香を済ませた。どの程度の付き合いか知らないが、特に鎮痛な面持ちでも、泣いている訳でもなく―――無表情に。
焼香が終わると、彼はおもむろに、久保田の方をかえりみた。
「顔、見れねぇの?」
「え…」
さすがの久保田も、ちょっと、うろたえた。困ったように多恵子の父の方を見たが、彼はまだ放心状態のようだ。仕方なく、多恵子の母の方を見る。
「あの…いいですか、見せてやっても」
久保田がそう訊くと、驚いたような顔をしていた多恵子の母は、すっと表情を和らげ、嬉しそうに微笑んだ。久保田を通り越して、その向こうにいる彼に、直接返事をした。
「ええ…ええ、見てあげて下さい。あの子の最期の顔ですから」
「―――ありがとうございます」
意外なほど丁寧な言葉で多恵子の母にそう言うと、彼は、棺の傍らに歩み寄って、顔の部分の小窓を開けた。
周囲の誰も、そこを覗き込む勇気はなかったが、彼は、不思議なほど穏やかな表情で、ガラス越しに多恵子の死に顔を見下ろしていた。
「多恵子」
微かな声で、そう呼びかけて。
「良かったな」
彼は、そう、呟いたのだ。
自殺願望者だった多恵子の死に顔に、面と向かって「良かったな」と言った男。
それが、瑞樹だった。
***
多恵子の気持ちを、一番理解してそうに見えたせいかもしれない。刹那的な生き方だという点が共通しているせいかもしれない。
瑞樹は、多恵子に似ている。佳那子はそう、思っている。
勿論、瑞樹は自殺願望など持っていない。ムカつく奴を屋上から突き落とす可能性はあるが、自分が屋上から飛び降りる事は120パーセントないタイプだろう。
でも―――多恵子がそうだったように、瑞樹も、何の前触れもなく、自分たちの前からフラリと姿を消してしまいそうな、そんな予感がする。何にも関心がなく、誰にも執着しない彼だから、姿を消すのも簡単なような気がして。
“瑞樹が変わるのは怖い”と、久保田は言った。死ぬ直前の多恵子も、傍目には良い方向に変化しているように見えたから、それを思い出して不安を感じているのだろう。
佳那子は、瑞樹がどう変わろうがあまり心配はしていないが、久保田は違う。救えなかった命を、瑞樹に重ねて見ている。その事に佳那子は気づいていた。
一番そばにいながら、多恵子が望みを叶えることを阻止できなかった。その後悔を、久保田は今も抱えている。それを瑞樹に投影している。それを思うと、佳那子も胸が痛かった。
「…今日みたいな天気って、嫌いだわ」
無意識のうちに、そう口に出して言ってしまっていた。
瑞樹は、一瞬、佳那子の方を見、それから苦笑いを浮かべて濃紺の空を仰いだ。
「なるほど、ね―――あの日も、確かにみぞれ混じりの雨だったもんな」
佳那子は、思わず目を見張った。
「覚えてたの?」
「隼雄の腕につかまって今にも倒れそうにしてる女を、俺が忘れる訳ないだろ」
「…あんた、余計な事ばっかり覚えていすぎよ」
つい馬鹿正直に、顔を赤らめてしまった。それにしても意外だ。一部始終、じっと見ていた佳那子とは違い、瑞樹の方が佳那子を見たのはほんの一瞬の事だったろうに、よく覚えていたものだ。
「―――久保田が、成田が最近、変わったっていうから、ちょっと気になっただけよ」
さりげなく訊くなんて無理そうなので、直球勝負に出た。すると瑞樹は、少し意外そうな顔をして、佳那子の方を向いた。
「隼雄が?」
「目が変わってきた、って。地に足つけて歩き出した気がする、って言ってたわよ。何かあったの?」
「…ふーん。目が変わった、か」
苦笑とも自嘲ともとれない妙な笑い方をして、瑞樹は髪を掻き上げた。
「まあ…ここ何日か、いろいろ考えてたからな」
「何を?」
「自分の事。これから、どうするべきか」
「…で、決まった訳?」
「ほぼ、見通しはたった」
ふと嫌な予感がして、佳那子は眉を寄せた。
「まさか、会社辞めるとか言い出さないでしょうね?」
「…そう来るか。さすが“システム部の才女”の異名とるだけあるな」
「ちょっと、笑い事じゃないわよ? 実際、成田に抜けられたら、仕事が回っていかないもの。困るわよ」
「仕事の話じゃねーから、心配ご無用。―――さて、戻るか」
軽く伸びをすると、瑞樹は鉄の扉の取っ手に手をかけようとした。あまりに唐突に話が打ち切られたので、佳那子は慌ててその手を制した。
「ちょ、ちょっと。なら、何の見通しが立ったのよ?」
「何。そんなに気になるもんか? それ」
不思議そうにそう言った瑞樹は、続いてニッ、と意味深な笑顔を作り、間近にいる佳那子の顔を覗き込んだ。
「第一、干渉する相手、間違ってねーか? それともあんた、隼雄から俺に乗り換える気?」
「―――!!」
からかうような表情を浮かべて真っ直ぐに自分の目を見据えてくるダークグレーの瞳に、一瞬、体中の血が沸騰しそうになった。
「ばっ…バカじゃないの!?」
「ハハハ、真に受けんなよ。冗談に決まってるだろ」
―――こ…っ、こいつ…。なんだか悪魔レベルがアップしてない!?
「成田っ! あんた、ほんっっっとーに性格悪すぎよ!」
「はいはい。…ま、隼雄には“心配すんな”とだけ言っとけよ。―――あんたの方は、俺自身より、隼雄が俺の事でやきもきするのが心配なだけだろ?」
「……」
「じゃあな。偵察ご苦労」
―――この、悪魔っ!
笑いながら去っていく瑞樹の背に、佳那子は精一杯睨みをきかせた。
―――…でも。
成田の周囲から彼女志願者が消えない理由、少しだけわかったかも…。
ほんの一瞬とはいえ、あの目に翻弄されそうになった自分を自覚し、佳那子は敗北感にがっくりとうなだれた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |