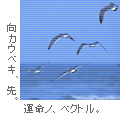| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
冬の城ヶ島の海は、無彩色だった。
寒そうな白い波が、切り立った海岸線を洗う。岩場に群がっているウミネコが、そのたびに羽根をばたつかせていた。
「冬の海ってのも、なかなか乙だよねぇ」
三脚にニコンS3をセットしていた蕾夏の父は、同意を求めるように瑞樹を振り返った。
「そうですね」
―――さっきから寒い寒い、これだから冬の海は嫌だ、って連発してたのに、ウミネコの群れ見つけた途端、これだもんなぁ。
自然好きな親子だよな、と考えながら、瑞樹は岸壁に腰を降ろした。カメラのセットが終わった蕾夏の父も、その隣に腰をおろすと、買っておいたお茶のペットボトルの口をひねった。
「瑞樹君も飲む? 紙コップ持ってきてるよ」
「あ、いただきます」
本当は自分もお茶を購入しているのだが、瑞樹はそれには触れず、素直に藤井氏の勧めに応じた。
***
そう。何故か瑞樹は、蕾夏の父に誘われて、冬の三浦半島めぐりに来ているのだ。しかも、2人きりで。
確かに昨年蕾夏の家に行った際、カメラ愛好家である蕾夏の父は、瑞樹に「今度一緒に写真撮りに行きたいねぇ」と言ってはいた。城ヶ島という名前もその行き先のひとつにあがっていたのは確かだ。
とはいえ、蕾夏から「今週末あたりどうだ、って電話があったんだけど…どうする?」と困惑気味の声で電話がかかってきた時は、さすがに呆気にとられた。
―――変わってるよなぁ。ありえないだろ、普通。
機嫌良くお茶を紙コップに注ぐ藤井氏を横目で眺め、瑞樹は複雑な心境になる。
―――まぁ、よりによってこの時期に、平然と誘いに応じる、俺も俺だけど。
ハイ、と差し出されたコップを受け取り、瑞樹は軽く頭を下げつつ、チラリとそんな事を考えた。
「あー、嬉しいなぁ。僕、息子とこうやって写真撮影に行くのが夢だったんだよ」
心底嬉しそうに言われ、瑞樹は紙コップを落としそうになった。
「…俺、いつ息子になったんですか?」
「あはは、似たようなもんだろう? 蕾夏の親友なんだから」
「……」
少々ドギマギしながら、瑞樹は紙コップに口をつけた。あまり無邪気に信頼されるのも困りものだ。
「蕾夏とは、こういう撮影旅行には行った事ないんですか」
「うーん。2人では、ないね。ああ、でも、アメリカにいた頃は、蕾夏の事は随分撮ったよ」
藤井氏は、ペットボトルの蓋を閉め、自分の分のお茶を一口飲むと、岩に当たって砕ける波を眺めた。
「蕾夏は飛行機がダメで、おかげで遠出はできなかったけど、近場のあらゆる場所で写真を撮ったよ。ワシントンD.C.は緑豊かで景色が良くてね。撮影場所には事欠かなかったな。ちょっと足を伸ばせば、シェナンドー国立公園で紅葉狩りなんかもできたし。桜が多くて、日本人には嬉しい街だったなぁ」
「桜、か…。ワシントンD.C.っていうと、やっぱりそれが最初に出てくるな、俺は」
以前写真で見たポトマック河畔の桜並木は、そこが日本かと思うほど見事だった。日本を象徴する花だけに、異国の地で咲き誇ってるのを見て結構感慨深かったのを覚えている。
「桜って言えば、蕾夏から聞いてるかな。向こうの小学校に植わってた桜の木の話」
「いえ」
「なかなか泣かせる話でねぇ…っとととと」
風にあおられて、ペットボトルが倒れてコロコロと岸壁の下に転がり落ちた。藤井氏が慌てて手を出したが、間に合わなかったのだ。
瑞樹は岸壁を飛び降りて、足場の悪い岩場を、意外なほど慣れた感じで駆け下りた。3分の1程度中身の残ったペットボトルを拾うと、藤井氏の方を振り返って苦笑する。
「置いとくと、また飛ぶかも」
「いやー、ごめんごめん。鞄にしまっとくよ。でも君、こういう所に慣れてそうだねぇ」
「親父が釣り好きで、時々ついてって写真撮ってたんで。城ヶ島も横浜に住んでた頃、何度か来たし」
藤井氏にペットボトルを渡すと、瑞樹はよっ、と勢いをつけて岸壁によじ登った。そういえば、昔父と来た時も、父の落としたルアーを何度か取りに行かされたよな、と思い出しながら。父との思い出は、結構温かい。せいぜい月に1回かそこらだったが、共有する時間を持てたのは幸いだったと、つくづく思う。
「…で、何ですか、桜の話って」
「ああ、そうだったね。―――蕾夏が、向こうの小学校に入った時の話でね」
またお茶を一口含み、藤井氏は海に目を移した。
「僕らが転勤したのは、蕾夏が5歳の、秋だったかな。あの子が小・中学生のうちに帰国する事は決まってたから、日本語学校に入れる事も考えたけど…普通の学校でこそ得る事もあるかもしれないと思って、英語をある程度マスターするのを待って、春に、プライマリースクールの年長さんに編入させたんだ。でもねぇ、驚いたよ。入学式が終わって迎えに行ったら、教室に蕾夏がいないんだから」
「え?」
「先生も一緒になって探したら、蕾夏は、学校の校庭に植えられていた桜の木に抱きついて、泣いてたんだ。どうしたのか訊ねたらね。ボロボロ泣きながら言うんだ。“なんで私だけ、髪が黒いの?”って」
藤井氏は、そう言って苦笑いした。
「ご近所に同じ年頃の子はいなかったし、そんな指摘を受けた事はなかったけど、5、6歳の子供なんて残酷だからね。同級生に“なんでライカの髪は黒いの?”“なんでライカだけ目が黒いの?”って言われたらしい。教室を飛び出した蕾夏は、校庭に咲いてる桜を見て、思ったんだそうだ。“ああ、日本の花だ”って。―――そう思ったら、嬉しくて嬉しくて、泣けてしまったらしいよ」
「…蕾夏らしい」
桜の木にしがみついて泣いてる小さな蕾夏が、目に浮かぶようだ。思わずクスリと笑ってしまう。
「感受性の塊みたいな子だからね。小さい頃から、感動も大きければ傷つくのも大きくて、なかなか大変だったみたいだけど―――悩んでると、その桜の木に抱きついて、よくエネルギーもらってたよ」
「エネルギー?」
「蕾夏の言葉だけどね。そうやって、一人で全部解決してた…親としちゃ、結構寂しい子だよ。何も相談してくれないからねぇ」
困ったように笑う藤井氏を見ていて、瑞樹は胸が鈍く痛んだ。
誰にも話さなかった―――親にも、先生にも、辻さんにも。そう言った蕾夏の言葉を思い出したのだ。
「瑞樹君は? どんな子供だった?」
「俺ですか?」
他意もなくそう訊かれ、瑞樹は一瞬、言葉につまった。
子供の頃の、自分。
―――子供時代なんて、あったんだろうか、俺には。
どう答えるべきかと言いよどんでいると、藤井氏は、穏やかな笑顔を瑞樹に向けた。
「…やっぱり君は、蕾夏と似ているね」
「え…」
以前にも言われた言葉だ。瑞樹は眉をひそめた。
「蕾夏は本心を“笑顔”で隠している。瑞樹君は本心を“無表情”で隠している―――やっぱり君も、一人でなんでも抱えてた子供時代を過ごしてたんだろうな」
「……」
やはり、親子というべきなのか。それとも、記者という職業柄なのか。
蕾夏以上に、あなどれない人だ。
「―――確かに、誰にも何も頼らない、愛想のないガキでしたね」
春の海みたいな藤井氏の横顔に、そう言う。藤井氏はその答えが気に入ったのか、楽しげに笑った。
***
蕾夏の父は、三脚を設置した場所から、ほとんど動かなかった。望遠レンズを岩場で休むウミネコの群れに向け、定点観測態勢を取っている。
瑞樹は、あちこち動き回って風景や水鳥や海を撮った。実際、ウミネコも撮影した。が、蕾夏の父は、一向に撮る様子がない。
何かの瞬間を狙ってるな、と直感的にわかる。その瞬間が近くなれば、藤井氏に動きが出るかもしれない。撮影を続けながらも、目の端で彼の姿だけは捉え続けた。
撮影は、そこそこ順調だ。元々景勝地だし、瑞樹が好きな被写体である鳥も、沢山いる。上空を舞う水鳥の伸びやかな羽根に半ば見惚れながらシャッターを切ると、胸がすくような爽快感があった。
でも―――何か、足りない。
正体は、わかっている。“色”だ。
無彩色なのだ。空も、海も、鳥も―――カメラを向けた瞬間に、“色”が感じられない。どれも無声映画のように、淡いモノクロに見える。
浅草で見たこんぺい糖や秋の空は、今も目に迫るほどに、鮮やかな“色”を持っていた。猫も、藤袴も、色のない障子ですら、艶やかな“色”を伴っていた。
―――無理矢理にでも、連れて来ればよかったかな。
寒そうだからやめとく、という言葉に従ってしまったのを、少しだけ後悔する。彼女がいれば、この景色も、もう少し違った“色”に見えたかもしれない。
「これだけ歩き難そうな所なのに、元気に走り回るよなぁ。やっぱり若いね」
やっと戻って来た瑞樹に、蕾夏の父がお茶を差し出した。
「あんまり“若い”って歳でもないですけどね」
「そうは言うけど、僕の半分の歳だからね。やっぱり若いよ」
そう言って笑った藤井氏は、やおら立ち上がり、三脚に据えたカメラのファインダーを覗いてみた。
「今日はまだ、渡らないかなあ…」
藤井氏が、ぽつりと呟く。それで瑞樹は、ああ、と思いあたった。
「そういえば、そろそろ北に移動する頃か…ウミネコは」
「そうだよ。今がギリギリ、この辺りで冬のウミネコが見られる最後の時期だな」
ウミネコに変化は無いようだ。藤井氏はファインダーから目を外し、寒そうにダウンコートを耳のあたりまで引き上げた。
気づいてしまうと、瑞樹もちょっと、ウミネコの渡りの瞬間をカメラに収めておきたくなった。鳥を撮るなら、ライカよりズームのきく一眼レフの方がいいかもしれない。本格的にウミネコ待ちを決め込んだ瑞樹は、デイパックにライカをしまい、代わりに一眼レフカメラを取り出した。
「渡り鳥って不思議だよねぇ。繁殖時期になると、誰に教えられたでもないのに、ちゃんと繁殖地へと真っ直ぐに飛んでいくだろ? 鮭の遡上も謎だけど、なんでわかるのかねぇ…」
心底不思議、という声で藤井氏はそう言った。
そういうのを「帰巣本能」と呼ぶ事は、百も承知だ。でも、藤井氏のセリフがまるで蕾夏が言いそうなセリフだったので、瑞樹は涼しい顔でからかった。
「どっかに書いてあるんじゃないですか? “越冬地こちら”とか“繁殖地こちら”とか」
「あははははは、そうか! それなら迷わずに済むね。でも、僕は見たことないなぁ、そんなたて看板」
「…冗談ですよ」
「うん、わかってるよ」
冗談にも真面目な話にもトーンが全く変わらない藤井氏なので、どこまでが冗談でどこからが本気なのか、その見極めが結構難しい。
「まぁ、自然の力というか、野生の本能なんだろうねぇ。DNAの中に、ちゃんと向かうべき方角が書き込まれてるんだろうな」
「その点、人間は駄目だな…」
「駄目?」
瑞樹がさらっと言った言葉に、藤井氏は目を丸くした。
「どうしてだい?」
「方向音痴が多いし、本能なんてとっくの昔に退化してるし」
「ははは、確かにね。でも―――人間だって、ちゃんと向かうべき方角は、DNAに刻まれてるよ」
「?」
人間に帰巣本能などあっただろうか? いや、多少はあるが、野生動物のような力はない筈だ。
瑞樹が要領を得ない顔をしていると、藤井氏は座っている瑞樹を見下ろし、ニッ、と笑った。
「瑞樹君、恋をした事はある?」
「は?」
唐突な言葉に、瑞樹は目を丸くした。
「恋じゃなくてもいいけど、これだけは手放したくない、って思う位、大切なものを見つけた経験、あるかな?」
「…ええ、まあ」
「もしかして、最近見つけたのかな? 去年会った時と、君、目線が違ってるけど。何を見つけたのかな」
「―――それは、企業秘密です」
内心の動揺を誤魔化すように、瑞樹もニッ、と笑ってみせる。藤井氏もそれ以上つっこんで訊く気はないらしく、話を続けた。
「見つけた事があるならわかるだろうけど―――そこまで思えるものは、多分、DNAレベルで刻み込まれたものなんだと思う」
また風が強くなってきた。藤井氏は、再びダウンコートの襟元を押え、海のはるか彼方を望んだ。
「僕にとっての夏子も、そうだったよ」
「夏子?」
「ああ、蕾夏の母親。僕の妻だよ。お母さん、とか、おい、とか呼ぶと怒るんでね」
去年見た溌剌とした笑顔を思い出し、瑞樹も藤井氏の苦笑につられるように苦笑いを浮かべた。
「どうしてだろうね―――いつの間にか、自分の日々の生活も、仕事も、趣味も、少しずつ彼女の方に引き寄せられてた。僕は鈍いから、気づくのに時間がかかったけど―――ある日ふと気づくと、自分の持ってるもの全て、彼女の方しか向いてなかったんだよ。それが恋だとか愛だとか認識する前にね」
わかるかい? という風に、蕾夏の父が瑞樹の方に視線を向けてくる。
わかります、という風に、瑞樹は目で頷いた。それに納得したように、また彼は海に目を向けた。
「実を言えば、当時は僕も彼女も、それぞれ恋人がいてね。お互い、その相手こそが運命の人だって思い込んでたんだ。おかしいだろう? でも、僕も、彼女も、気づく事ができた―――自分の中に刻み込まれた相手が誰なのか。自分の目が、どこを見ているのか…」
「―――運命のベクトルが、どこに向いているかを」
ぽつんと、瑞樹が呟いた。ややもすれば風で掻き消えるほど、小さな声で。だが、藤井氏はそれを聞き逃さなかった。
「ああ、その表現、いいね。運命のベクトル―――案外詩人だね、君も」
「―――親父のセリフなんです」
瑞樹は苦笑を浮かべ、藤井氏が見てたのと同じ海の彼方に目を移した。
―――いつから、と、線引きするのは難しい。
ここ1ヶ月、何度も何度も、思い出そうとしたけれど、わからなかった。でも…それでもいい。きっと線引きなどできないのだろう。蕾夏の父が言うように。
ただ、その予感を覚えた日だけは、はっきり覚えている。
腹立ち紛れとはいえ、人生で初めて、自分の意志で自分の方から触れた唇―――その感触の甘さにうろたえ、混乱した日。でも、その日から、ではない。もっと、ずっと前から。
あえて言うならば、それはおそらく、“最初から”。
姿も名前もなかった、あの時から。
無機質なディスプレイに映し出された文字に過ぎなかった時から―――自分でも気づかないほど緩やかに。
彼女だけだった。
凍結させたまま、ずっと動く事の無かった瑞樹の“感情”を、耐え切れないほどに揺さぶったのは。
その言葉で、その声で、その姿で―――ただ隣にいるだけで、モノクロの世界をカラーに変えてしまうほどに。
と、その時―――眼下のウミネコの群れが、それまでと違った動きをした。
「あ!」
瑞樹と蕾夏の父は、同時に声を上げると、それぞれ慌ててカメラを構えた。
来る、と、直感が訴える。ぼんやりと海を眺めていた目が、獲物をとらえる時の目に変わる。全身が総毛立つ緊張感に、瑞樹は息を呑んだ。
ウミネコの群れは、暫し落ち着かない様子を見せていた。が、やがて、最初の1羽が舞い上がると、それを合図にしたかのように、羽音をたてて、一斉に空に舞い上がった。
ざっと数えて、30羽から40羽。逆光をうけた黒い塊は、ちょうど瑞樹たちの頭上を掠めるコースをとって、真っ直ぐに、目指すべき土地へと旅立った。―――北へ、北へ、と。
2人は、息を詰め、シャッターを切り続けた。その姿が、点のように小さく絞られ、見えなくなるまで。
「―――凄いねぇ…」
感心したように、藤井氏がそう言葉をもらす。
「まっしぐらだよ―――迷う事なく、一直線だ」
「…そうですね」
瑞樹も、カメラをおろし、ウミネコの一団が飛び去った空を仰いだ。
海風が髪を乱す。その冷たさも、気にならなかった。
―――俺が向かうべき先。運命の、ベクトル。
簡単な道程じゃないのは、わかっている。もし間違えれば、今のこの平安をも永遠に失う。失ったら、多分今度こそ立ち上がれない。もしかしたら、彼女をも立ち上がれなくしてしまうかもしれない。
それでも。
それでも―――…。
瑞樹は、目を閉じると、風に乱された髪を乱雑に掻き上げた。
再び目を開けた瑞樹の瞳は、真っ直ぐに前だけを見つめていた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |