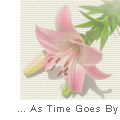| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
―――誰かが、歌ってる。
ああ、この声は、ホリー・コールだ、と頭の片隅で思う。いつ聴いてもせつない声だ。それでなくとも、この『コーリング・ユー』という曲は、旋律そのものが、胸を締め付けるほどにせつないのに。
「隼雄」
…多恵子?
一瞬、そう考えて、そのあり得ない答えに苦笑する。
瑞樹? …お前、そこにいるのか?
目に浮かぶのは、銀杏の木の下で、大事そうにライカM4を抱きしめて眠っている姿―――多分、大学2年か3年の頃。何時間そうしていたのか、彼の髪にも顔にもシャツの上にも、色づいた銀杏の葉が落ちていた。
一瞬、死んでるのかと思った。あの時。
―――なあ。
お前、生き急ぐなよ。頼むから。
お前は、俺たちを置いていくなよ。
「隼雄」
現実の声に、久保田はようやく目を覚ました。
***
「…っれ…、佐々木?」
久保田は、自宅のベッドで寝ていた。間違いない。天井も壁も、自室のものだから。
「…お前、一体どうやって入ったんだ?」
「やだ、何も覚えてないの?」
ビーズクッションの上に座った佳那子は、久保田の言葉を聞いて呆れたような顔をした。見ればその服装は、通勤する時のパリッとしたスーツ姿だ。会社帰りだろうか?
そこで気づいた。自分はパジャマ姿だ。記憶が確かならば、今日は平日で、ちゃんと会社に行った筈だ。一体何がどうなっているのか、久保田にはさっぱりわからない。
「…記憶がとんでるらしい」
「あのね。今日一緒に飲みに行って、その店で倒れたのよ、あんたは」
「倒れた? 俺が!?」
鬼の霍乱、と自分で言ってはいけないのだろうが、まさにそんな感じがする。久保田は滅多に風邪すらひかない。倒れる、なんて表現されるほどの状態など、それこそ皆無だ。
でも、言われてみれば、さっきから体がだるくて頭が痛い。滅多にないから忘れかけているが、これは風邪の時の状態だ。朝から体が重いとは思っていたが、こういう事だったとは気づかなかった。
「タクシー呼んで連れてきて、鍵を拝借して中に入れさせてもらったの。熱はさっき測ったら38度1分だった。風邪薬か解熱剤、常備してる?」
「ああ、ある…けど…ちょっと待て。今、何時だ?」
「午前1時」
「は!?」
だるさも頭痛も忘れて、久保田はガバッと飛び起きた。が、忘れたのは一瞬だけの事で、すぐに熱で頭がクラリとし、また寝転ぶ羽目になった。
「ご、午前1時ってお前…」
「大丈夫よ」
久保田の言いたい事を察して、佳那子はニコリと笑った。
「お父さん、今日から3日間、講演で沖縄行ってるの。原口さんは私の味方だし、お父さんの関係者は一緒に沖縄だし。お父さんも最近は警戒ゆるいから、留守中の監視まではつけてないわよ。あ、原口さんには、ちゃんと電話しておいたわ。万が一お父さんから連絡入っても、対策は万全よ」
原口さんというのは、佐々木家のはなれに住んでいる中年夫婦のことで、妻は佐々木家の家政婦を、夫は父の秘書をやっている。夫の方は父の味方だが、父にくっついて沖縄に行っている。「私の味方」と佳那子が言っている「原口さん」は、つまりは妻である家政婦の方だ。
「という訳で、心配御無用」
「…知らねーぞ、後でバレても」
大きくため息をつき、久保田はぐったりと頭を枕に沈み込ませた。少し安心したが、安心した途端、なんだか熱が上がったような気がしたのだ。
「何か食べる? おかゆ位ならすぐ作るけど」
「…いや、いい。それより何か飲みたい」
「駄目よ。風邪薬飲ませるんだから、何か固形物か流動食を胃に入れておかなくちゃ」
「それなら、冷蔵庫にスポーツ用のドリンクゼリー入ってるから、それでいい」
「ん。わかったわ」
佳那子は軽やかに立ち上がると、台所へと向かった。
ちょうどそのタイミングで、ずっと流れていた『コーリング・ユー』が終わり、次の曲になった。エラ・フィッツジェラルドの歌う『アズ・タイム・ゴーズ・バイ』。その曲順で、今再生されているのが、佳那子のMDである事がわかった。日頃持ち歩いているものを久保田の部屋のMDデッキにかけたらしい。
―――ああ、この曲だったよなぁ…。話をするようになったきっかけは。
熱を帯びた頭で、ぼんやりとそんな事を考えているところに、佳那子が戻って来た。お盆の上に、ドリンクゼリーと水の入ったグラス、そして風邪薬を乗せている。
「お前、さっき、“隼雄”って呼んでたか?」
ドリンクゼリーを受け取りつつ、久保田が訊ねる。すると佳那子は、悪戯を見つかった子供のような笑い方をした。
「やっぱり言い慣れないわね。長年“久保田”で通しちゃってるから」
「俺も言われ慣れてないからな。おかげで、お前の声だってわからなかった」
「成田の名前、呼んでたわよ」
アルミで出来た袋にストローを挿していた久保田は、その言葉に思わず手を止めてしまった。
「…俺、うわ言なんて言ってたのか?」
「その前に、多恵子ちゃんの名前も呼んでた。やっぱり“隼雄”って呼ばれたら、あの2人が出てきちゃうのねぇ…」
「…“久保田”って呼ばれりゃ、すぐお前が出てきたぞ、言っとくけど」
多少むっとしながら、久保田は体を起こして、ドリンクゼリーを飲み込んだ。冷やされていたゼリーは、熱っぽい体には心地良い。これなら、1袋食べることができそうだ。
確かにこのところ、ハードスケジュールだったからなぁ―――と、冷たいゼリーを飲み込みつつ、思う。
4月からの新しいキャンペーン企画が難航していて、ここ2週間ほどは、企画部も営業部も不眠不休状態だった。今日でようやく見通しが立ったからこそ、久々に佳那子と飲みに行った訳だが、自分でも知らないうちに疲れがピークに達していたのだろう。日頃の久保田なら、風邪なら初期症状のうちに封じ込めに成功している筈だ。
体調管理も仕事の一環だ、と日頃から和臣に言って聞かせているのに、その久保田が倒れたのではしめしがつかない。最後の一口はもう飲みたくない気分だったが、回復のためだ、と考え、なんとか飲み込んだ。
「全部食べられた?」
「なんとか、な」
「そう、良かった」
久保田からアルミの袋を受け取ると、佳那子はにっこり笑って、風邪薬の錠剤を瓶から3錠取り出した。
「はい、これ飲んでね」
てっきり手渡されると思ったら、佳那子はその錠剤を、久保田の口の中に1錠ずつ指で押し込んでいった。
「おいおい…子供じゃねーんだから」
「まぁ、いいじゃない」
久保田の抗議を無視して、佳那子はお盆の上のグラスに手を伸ばした。と思ったら、その水を、自分で飲んでしまった。
「おーい? 佐々…」
何やってんだ、と思って声をあげると、佳那子はそれを塞ぐように、唇を久保田の唇に重ねてきた。
冷たい水が、口移しで流れ込んでくる。その水と一緒に、風邪薬をコクン、と飲み下す。ほんの数秒の事で、久保田は完全になすがままだった。
「―――飲めた?」
「……」
まだ僅かに口の中に残っていた水を飲み込み、久保田は、艶然とした笑いを向けてくる佳那子を、唖然とした顔で凝視した。それから、大きくため息をついて、ベッドに倒れこんだ。
「…ったく…このお嬢さんは、一体いつからこーゆー不良な真似をするようになったのかねぇ…」
「不良にした張本人に、そんな事言われたくないわよ?」
「…うつっても知らねーぞ?」
挑発されて、ただで引っ込むような久保田ではない。佳那子の頭を引き寄せて、今度は自分からくちづけた。それも、佳那子にとっては予想通りの行動だったのだろう。久保田の肩に、佳那子の手が甘えたように絡んできた。
「―――もしかして、凄く久しぶりか? こういうの」
「今年の誕生日は、お父さんがお見合いぶつけてきて潰されちゃったしね」
「…さてはお前、今日俺が倒れて、“チャンスだ”とか思ったな?」
「あら、久保田の格言なんじゃないの?」
いつもきちんと整えている久保田の髪をぐしゃっと崩すように指で梳いて、佳那子はくすっと笑った。
「“今だ、と思った時に、即行動しろ。あの時チャンスだったな、と思う時には、もう遅い”―――私はそれに従ったまでよ?」
***
正直、2人のお互いの第一印象は、かなり悪かった。
仮採用の間、久保田は営業部、佳那子はシステム部に配属され、同じフロアで毎日顔を合わせていた。
奈々美は事務として4階に配属されていたが、同期の女性が2人きりだという事もあって、すぐに親しくなれた。昼休みなども一緒に過ごしていたし、帰りも駅までは一緒に帰っていた。そんな時、佳那子の口から、よくこんなセリフが聞かれるようになったのは、仮採用も1週間が過ぎた頃だ。
「営業の久保田君って、気に食わないわ」
それを聞いて、奈々美はキョトンと目を丸くした。
「どうして? 同期じゃピカイチだって噂じゃないの?」
実は密かに久保田の事を悪くないな、と思っていた奈々美にとっては、佳那子がその久保田を気に食わないと評価するのは納得がいかなかった。が、佳那子は不機嫌に眉を寄せた。
「私、調子がいい奴って嫌い。上司に対する立ち回り方とか、同期を上手く操縦してるあたり、まだ22歳のくせにベテランの営業マンみたいでいやらしいわ。もっと真摯な態度が欲しいじゃないの、新人なんだから」
真面目でこつこつ型の佳那子から見ると、久保田はそういう「お調子者」に見えたのだ。そういう苦手なタイプが、仮採用期間にも関わらず着実に社内での評価を上げていっているのが、佳那子としては癪に障ってしょうがなかった。
一方、久保田の方も、システム部の紅一点である佳那子に対して、強烈な苦手意識を持っていた。
「要領悪いよなぁ、あいつ。上司にいちいちつっかかってくし、やる必要ない仕事を押し付けられてるのに気づかないで真面目に残業してるし。助言すると“大きなお世話”って顔するし」
同期と飲みに行って、そんな話をすると、同期は決まってこう言う。
「真面目なんじゃないか? 仕事に対して一生懸命って感じで、いいじゃないか」
「あれじゃあ、いずれ潰れるよ。男ばっかのシステム部で、雑用係にされるのは目に見えるじゃねーか。そういう立場に甘んじられるほど、プライド低くねーだろ、あの女」
自分に噛み付いてくる時の佳那子のプライドの高さを考えれば、雑用をやらされる位なら会社を辞めてやる、と言いそうだ。もっと肩の力抜けばいいのに、と、久保田は眉を顰めていた。
とにかくあの2人はそりが合わない、というイメージが定着した頃、新人歓迎会が開かれた。
普通なら部で固まって宴席を囲む筈が、新人歓迎会だけは違っていた。新人はひとまとめに集められ、席順も決まってしまっていた。そして久保田と佳那子は、偶然なのか先輩たちの粋な計らいなのか、隣同士にされてしまったのだ。
かなり不服に思いながらも、新人の身では逆らえない。2人とも、決められた席に渋々落ち着いた。一言だって話なんてしてやるか、というムードをまといながら。
奈々美と席が離されてしまった佳那子は、終始無言でそこに座っていた。久保田は反対隣の同期と時々言葉を交わしつつ、隣に座る佳那子の様子を時々気にしていた。
―――ほんとに、肩に力が入りすぎな奴だよなぁ…。こういう時こそ、そっち側の隣の奴と親しくなるとかして、人間関係広げりゃいいのに。人見知りが激しいタイプなんだろうなぁ、こいつ。
そんな久保田の考えなど知る由もなく、佳那子は黙ったままでいた。
久保田も話しかけないまま宴席も半ばを過ぎた頃、恒例のビンゴゲームが始まり、全員にビンゴのカードが配られた。
結構運の強いタイプと自負している久保田は、かなり順調に番号を消化していっていた。チラリと覗いてみると、佳那子も同じ位のペースで番号を開けていっている。案外強運の持主かもしれないな、と妙な部分で対抗意識を刺激された。
が―――リーチがかかってからが、なかなか当たりが来ない。ちょっと苛ついた頃。
「あ、それ、ビンゴ!」
隣の佳那子が、明るい声を上げた。
「おおー、佐々木さん、早い! 新人トップを飾ったということで、皆さん拍手〜」
パチパチと拍手があがる中、久保田一人が面白くないという顔をしていた。たかがビンゴだが、佳那子に負けたという事がどうにも悔しい。
副賞を貰って戻って来た佳那子が、ふっ、と勝ち誇った笑いを久保田に向ける。頭の血管がぶち切れそうになったが、辛うじて耐えた。が、相手も自分に対抗心を持っているのだと、それで気づいた。
―――やっぱり、気に食わねえ。
そう思った時。
副賞をバッグの中に仕舞っていた佳那子が無意識のうちに口ずさんでいる歌に、久保田は表情を変えた。
聴き覚えのある―――いや、かなり好きな歌だ。
「…“アズ・タイム・ゴーズ・バイ”?」
思わず、曲名を口にする。と、佳那子がぱっ、と顔をあげ、久保田の方を見た。
「え?」
「いや、今歌ってたの。“アズ・タイム・ゴーズ・バイ”だろ? エラ・フィッツジェラルドの」
久保田がそう言うと、佳那子の目が突然キラキラと輝いた。日頃自分に向けられる鬱陶しそうな目との落差に、一瞬息を呑んだ。
「久保田君、ジャズ好きなの?」
「ああ、かなり」
「私もよ。ああ、でも、“アズ・タイム・ゴーズ・バイ”は、私の中ではエラじゃないの。カーメン・マクレエ」
「あー、いいよなぁ、カーメン・マクレエ! 3大黒人女性ヴォーカリストって、あと誰だったっけ―――ああ、サラ・ヴォーンか」
「サラ・ヴォーンもいいわよねぇ…。黒人のジャズ歌手って、やっぱり声量が違うし、黒人が辿った歴史のせいかもしれないけど、魂がこもってるって感じがしない?」
同じ趣味の人間に出会えた事が嬉しくてしょうがない、といった感じで、佳那子は楽しげな笑みを見せて話し続けた。
久保田も、話題がジャズとなれば底なしだ。ついさっきまで「気に食わない」と思っていた佳那子相手に、熱のこもったジャズ談義を繰り広げた。
―――なんだ。案外、いい奴じゃないか。
久保田も、そして佳那子も、そう思った。
それが、2人の関係が変わった瞬間。
勿論、その後、急転直下で2人の関係が更に変わるとは、本人たちでさえ思いもよらなかったのだが―――…。
***
―――人間、人生がどう転がるかなんて、わかったもんじゃないよな…。
床にぺたんと座り、ベッドに顔を埋めるみたいにして眠っている佳那子の頭を軽く撫でながら、久保田は苦笑した。表面上は気丈にしていたが、やはり目の前で倒れられて動揺していたのだろう。思ったより元気そうだとわかってホッとしたのか、あっという間に眠ってしまったのだ。
なんでよりによって、こんなややこしい女を選んでしまったんだろう、と、時々自分の馬鹿さ加減に自分で呆れてしまう。でも、そう思うたび、心の中で訂正する。
選んだんじゃなくて、俺が選ばれたんだよな、この女王様に、と。
「全く…時々、突拍子もない事して、驚かせてくれるんだからなぁ、こいつは…」
眠っている佳那子の顔は、久保田の意表をつけた事に満足したみたいに、少し嬉しそうに微笑んでいる。確かに、このところ「飲み友達」以上の事は何もできずにいたので、今日のようなアクシデントが“チャンス”であったのは事実だ。
―――まぁ、今日位は、恋人のムードで過ごしてもいいよな。俺、病人なんだし。
風邪薬が効いてきたのか、だんだんと瞼が重くなってきた。
スピーカーからは、デューク・エリントンの『A列車でいこう』が流れている。その心地良い音色に誘われたように、久保田は佳那子の頭に手を乗せたまま、ゆっくりと目を閉じた。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |