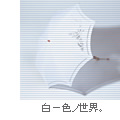| Psychedelic Note | size: M / L / under800x600 | |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog | ||
家に帰り着くと、既に日付が変わっていた。
珍しく大量に入っていた郵便物をまとめてテーブルの上に放り出し、瑞樹は冷蔵庫に直行した。既に7月も後半。真夜中だというのに、空気が湿気で重い感じがする。また苦手な季節が巡って来た訳だ。
ウーロン茶をグラスに半分ほど注ぎ、一気に飲み干す。少しは体が冷やされた気がして、とりあえずまだクーラーを入れるのは止めておいた。蕾夏にすぐ電話をしようかと思ったが、なんとなく郵便物の山が気になり、瑞樹はそちらを優先することにした。
くだらないDMや携帯の請求書などをポイポイとより分けていた瑞樹は、1通の封書に目を止めた。
―――この出版社名って…。
封を切ってみると、中からはA4のコピー用紙に印刷された文書が1枚出てきた。
文面に目を走らせた瑞樹は、結局、文面を暗記してしまうほど、何度もそれを読み返した。そして、
「…嘘だろ」
と、思わず呟いた。
***
『ほんとに!? ほんとに時田賞!? グランプリでも準グランプリでも佳作でもないんだよね!?』
受話器の向こうの蕾夏の声が、既に興奮状態になっている。
「ほんとに時田賞」
『うそーっ!』
「…だから、本当だって」
瑞樹は、4月に屋久島で撮った写真を、『フォト・ファインダー』誌のコンテストに出品していた。
新人フォトグラファーの登竜門、などと言われているコンテストだが、正直、その手の賞取り合戦には興味はない。6人いる審査員の1人、時田郁夫に写真を見てもらいたい、という自己満足のためだけに出した。郵便局に写真の入った封筒を出した段階で、瑞樹のコンテストは終わっていた。
ところが―――である。
今日、出版社から送られてきた、1通の封書。そこには、瑞樹の出品した写真が時田賞に選ばれた、と書いてあった。一応賞金が出るからそれを取りに来て欲しい旨と、出版社の1階ロビーで受賞作品の展示会をやるからよければどうぞ、といった趣旨の通知だった。
時田賞―――コンテストに設けられた賞の中では、ちょっと特殊な賞と言える。グランプリとか佳作などの選考からはもれたが、審査員が個人的に気に入った1点に送る、審査員特別賞だ。
時田賞はその名の通り、時田郁夫が個人的に推す1点に送られる賞―――毎年何百点何千点の応募がある中で、その1点に、瑞樹の写真は選ばれてしまった。
『夢みたい…』
「だよなぁ…」
電話越し、2人とも夢うつつ状態で、そんな事を口走る。
『ね、それ、展示会っていつからいつまでやってるの?』
「8月の頭の平日5日間」
『平日なのかぁ…会社帰りに見に行こうかなぁ。瑞樹行く時、一緒させて』
「最初からそのつもりだったし。賞金もその時ついでに貰ってくるかな…。30万か。中途半端な額…」
上位賞3名ならば確かに賞金も高額だが、その代わり、著名人を集めた授与式みたいなものが催される。そういう式典は酷く苦手な瑞樹なので、中途半端な額で構わないから、事務所に行ってポンとハンコ押して貰ってくるだけの方がはるかに有難い。
第一、時田賞だ。グランプリより、準グランプリより、瑞樹にとっては意味がある。
「お前、いつなら行ける? 賞金貰いに行く日連絡しろって書いてあるから、明日にでも電話しとくけど」
『ええと…火曜日かな。最近課長、歯医者に通ってて、毎週火曜日は早く帰るから』
「おっけ。火曜日な」
『あー…ほんと、夢みたいだけどさ。私、時田郁夫は、多分瑞樹の写真なら気に入ると思ってたんだ』
妙に確信を持った口調に、瑞樹は思わず苦笑した。
「なんでわかるんだよ」
『だって、時田郁夫って、趣味でレンジファインダー愛用してるんでしょ? スナップ撮りが好きってことだろうから、瑞樹と基本的に写真スタイルが似てるんだろうって思ったの』
ちょっと意外だった。時田郁夫が愛用しているカメラの話も、M型ライカのようなレンジファインダーカメラがスナップ撮りに強いことも、そこまで突っ込んで話した記憶はなかった。どこでそんな知識を仕入れて来たのだろう?
「お前、妙に詳しいな」
『え? あはは、まぁね。この位は。―――ねぇ、展示会のこと、翔子にも知らせていい?』
「いいけど…来ないだろ、あの調子じゃ」
瑞樹の口調が、つい苦々しげなものになってしまう。横浜の時の翔子を思い出したのだ。
虹を撮った後、瑞樹と蕾夏が戻ってくると、翔子は突然「帰る」と言った。その思いつめた様子にただならぬものを感じ、蕾夏も一緒に帰ると言ったのだが、翔子は1人で帰ると言ってきかなかった。仕方なく1人で帰らせたが、発作らしき症状を見せた後だけに、蕾夏はその後、ずっと翔子の心配をして上の空だった。
『…来ないとは思うけど、見て欲しいの、瑞樹の写真を』
「そう急がなくても、どうせ来月号の“フォト・ファインダー”に掲載されるぜ?」
『じゃあ、それも知らせとく。…どのみち、ハガキ出すつもりでいたんだ。この前の横浜以来、全然連絡ないから』
蕾夏は、翔子の家には電話はしない。辻が偶然出る可能性があるからだ。翔子は元々携帯を持っていないし、大学を離れるとメールも一切やらない質なので、手紙位しか連絡方法が残されていないのだ。
「お前の幼馴染の事だから、お前の気の済むようにすりゃいいよ」
もうあんな女ほっとけよ、という気持ちもあったが、瑞樹はそう言っておいた。翔子は蕾夏にとって大切な友達―――その事実は、今も変わらないのだから。
***
「うわー…藤井さんだー。綺麗だー…」
「ほんと。屋久杉の写真だけど、これって蕾夏ちゃんの写真よねぇ」
「どうでもいいけど、カズ。木下の目の前で、他の女の写真見て涙流すなよ。誤解受けるぞ」
「…いいのよ、久保田君。カズ君のは、一種の宗教だから」
あっさりそう言う奈々美の隣で、和臣が写真を眺めながらボロボロ涙をこぼしていた。見兼ねて久保田がハンカチを差し出すが、さっぱり気づかない。その様子に佳那子は苦笑し、久保田のハンカチを和臣の手の中に押し込んでやった。
約束した火曜日。結局、会社の連中も一緒に行くと言い出し、出版社1階のロビーに展示された写真の前は、賑やかな連中で占拠されていた。
そんな4人の背後、瑞樹の隣に立った蕾夏は、パネル大に引き伸ばされた自分の写真を見つめて、唖然としていた。
―――これが…私?
画面中央、屋久杉に耳を当てて身を寄せている自分は、信じられないほど、穏やかな顔をしていた―――屋久杉の鼓動に身を委ねているみたいに。プレッシャーや逆境、過去の辛い記憶に負けまいと常に身構えている自分ではなく、すべてを取り去った、素のままの自分がそこにいるように思えた。
自分なのに、自分じゃないみたいだ。
思わず、見惚れる―――写真の中の自分にも、周囲を取り巻く、淡く光を含んだ緑色の景色にも。
ふと写真の下に目を移すと、時田賞の文字と瑞樹の名前、そして『
「“生命”…」
「―――それが撮りたかったんだろ?」
そう言って、瑞樹がニッ、と笑った。それを見て、蕾夏も少し笑った。
あの時、聴いていた、何千年もそこに立ち続けている強い生命―――屋久杉の心音。それは、力強い、という以上に、とても穏やかで優しかった。今目の前にある写真は、穏やかで、とても優しい―――あの時感じた生命が、そこにはちゃんと息づいていた。
「さて、と…隼雄。俺、上行ってくる」
久保田の肩を叩いて瑞樹がそう言うと、振り返った久保田がニヤリと笑った。
「お前、俺たちが何しにここまで来たか、わかってんだろうな?」
「…1人5千円まで」
「よっしゃ」
賞金でおごってもらうことが4人の目的なので、その辺は覚悟している。瑞樹は苦笑し、蕾夏を見下ろした。
「お前も来る?」
「え、行ってもいいのかな。本人じゃないのに」
「別に構わないだろ。一応、モデルだし」
「…私がモデル、っていうより、屋久杉がモデルだけどなぁ…」
そう言いながらも、蕾夏は瑞樹に続いてエレベーターへと歩き出した。雑誌の編集部を覗く機会など滅多にないので、興味深々だったのだ。
「賞金、今日飲み食いしたら、残りどうするの?」
エレベーターに乗り込んですぐ、蕾夏が小声で訊ねた。
「まだ決めてない。結構難しい額で」
30万円。パーッと飲み食いで使い切るには惜しい金額だが、日頃手の出ない機材を買うほどの大金でもない、本当に中途半端な額だ。
「学生時代に何回か入賞して賞金貰ってたけど、学生だけに1万円でも“これでフィルムが買える”って大喜びしてたのにな。30万も貰って使い道が思い浮かばないなんて、幸せなんだか不幸なんだか…」
「DVDが普及してきてるから、DVDプレーヤー買うとか?」
「まだ規格があやふやで、下手したら将来何も見れないただの箱になる可能性があるだろ」
「…それはあるなぁ。うちのお父さん、ビデオで失敗してるもの。ベータ買って自慢してた癖に、VHSに席巻されちゃって、今では飾ってあるだけ」
そんな話をしているうちに、『フォト・ファインダー』の編集部がある14階に到着した。
編集部は、来月号の準備の真っ只中らしく、足を踏み入れた瞬間に「こりゃ修羅場に来ちまったな」と察した。前もって賞金受け取りの日を連絡するように言われた理由がよくわかる。
受付らしき人に用件を伝えると、一番奥のデスクまで行くよう言われた。
「…やっぱ、私が来たの、まずかったんじゃない?」
「この状況じゃ、俺1人だろうがお前がいようが同じだと思うけど」
確かに、完全に一般人の2人が紛れ込んでいるのに、編集部を駆け回る人々は、誰一人2人に注意を払っていない。こんな状況であの雑誌が作られているのか、と、1冊の雑誌に敬意を払いたくなる。
「あの…編集長の山本さんですか」
カッターシャツを腕まくりした中年の男性に瑞樹が声をかけると、それまでゲラ刷りを眉間に皺を寄せて睨んでいた彼は、ぱっと顔を上げた。黒縁の眼鏡が少しずり落ちているのがコミカルだ。
「ええと…ああ! 時田賞の…成田さん、ですか。7時からの約束でしたね」
山本が、デスクの上のカレンダーに目を走らせながら、慌てた様子で立ち上がった。A4サイズのカレンダーはスケジュールが真っ黒に書き込まれていて、よくあの一瞬で「成田」という名前を読み分けたな、と感心するほどだ。
「このたびは、おめでとうございます。とりあえず賞金の受取証にサインいただいて、と…印鑑はお持ちで?」
「三文判ですが」
「あ、それで結構です」
山本は、実に事務的に机の中から紙やら朱肉やらを取り出し、さっさと賞金引渡しの手続きに入った。蕾夏の事は、全く目に入っていないようだ。なんだか空気にでもなった気分で、蕾夏はキョロキョロと編集部内を見回した。
戦場と化している編集部は、幼い頃母に連れられて訪れた父の新聞社を思い出させる。取材先から駆け込んできた父が、編集長と記事の内容について
実は蕾夏も、一時は「大きくなったら新聞記者になる!」などと言っていた。元々、詩を書いてみたり、父の写真に短い文章をつけたりと、ものを書くこと自体が結構好きだったし、それに、やはり父の仕事というのはなんとなく憧れがあったのだ。しかし、その望みは、蕾夏の読書感想文を読んだ父の一言で、簡単に打ち砕かれた。
『蕾夏。お前の文章は、観念的すぎる。観念的って意味、わかるか? 具体的、の反対語だぞ。お前にはわかっても、第三者にはわからないよ、これじゃ』
「はい、以上で結構ですよ。ご足労願いまして、すみませんでしたね」
「いえ」
瑞樹の短い声で、蕾夏は我に返った。どうやら手続きが全て終わったらしく、瑞樹は受け取った大げさな水引のついた祝い袋を仕舞っているところだった。
「それで、成田さん。あと10分位、お時間ありますか?」
「は?」
山本の言葉に、瑞樹と蕾夏は、顔を見合わせた。下に久保田たちを待たせているが、4人もいるし、10分位なら問題ないだろう。
「10分位でしたら」
「そうですか! でしたら、お呼びしますね」
「は?」
「時田先生が来てるんですよ」
大抵の事には驚かない2人も、これには目を丸くした。
***
ちゃんと写真撮って下さいよ、と編集者からガミガミ言われながら登場した時田郁夫は、年のころは30代に見えた。
が、2人は、時田郁夫のプロフィール位、とっくに頭に入っている。現在43歳。頭に巻いたバンダナと無精ひげがトレードマークで、外見からしたら相当ワイルドな写真を撮りそうに見える。が、実際の彼の写真は、壮大ではあるが、不思議なほど静かで温かい写真が多い。
元々編集者で、32歳の時、プロのカメラマンに転向した変り種だ。独学でカメラを勉強したそうで、そういった点も瑞樹が彼に傾倒している理由の1つである。
「すまないねぇ、なんだか、バタバタしてて。ここ、僕の古巣なんだけど、編集者が口うるさいんで有名なんだよ」
時田はそう言って苦笑した。そうですか、とも、とんでもない、とも答えようがない。2人してリアクションに困る。
「えー…。はじめまして。時田郁夫です」
「成田瑞樹です」
時田が差し出した手を、瑞樹は自然と握った。瑞樹より少し低い背ではあるが、時田の手は瑞樹よりゴツゴツと骨ばっていた。
「あ。こっちの子、あの写真の子だよね」
それまで空気と化していた蕾夏に、時田が目をとめた。蕾夏は慌てて笑顔を作り、会釈した。
「お名前は?」
「藤井蕾夏です」
「らいか、かぁ…ハハハ、撮られるために生まれてきたみたいな名前だなぁ。僕も娘がいたら付けたい名前だよなぁ、らいかって」
やっぱりカメラ好きは同じ発想なのか―――蕾夏はげんなりしつつも、愛想笑いをしておいた。
「まず最初に―――君たちには、謝らないと。ほんと、すまない」
「は?」
唐突な時田の謝罪に、2人は眉をひそめた。賞に選んでくれたのだから、こちらが感謝しこそすれ、時田に謝られる理由などない。
が、時田は、心底済まなそうな顔で苦笑した。
「実はね。成田君、もう1枚出してたでしょう。あっちは準グランプリの候補まで残ったんだよ」
「は? そうなんですか?」
意外だった。もう1枚は、もっとずっと前に撮った、ゴールデンレトリーバーとその飼い主のスナップ・ショットだ。特に思い入れはないが、構図や切り取ったタイミングが良かったので、一応送ったに過ぎない。
「そう。他の審査員には、あっちの方がわかり易かったんだね。でもねぇ…僕は“生命”の方が数十倍好きで、絶対譲れなかったんだ。上位2名は審査員の全員一致で選ぶのが原則だから、僕が“生命”の方に固執したせいで、成田君、準グランプリを逃しちゃったんだよ。いやほんと、申し訳ない」
そう言って頭を掻く時田に、瑞樹は静かな笑みを浮かべ、首を振ってみせた。
「そんなことより、時田さんにこっちを選んでもらって嬉しいです。俺も、こっちが好きですから」
「そうかい? 案外無欲なんだねぇ。アハハハハハ」
愉快そうに笑う時田を見ながら、瑞樹と蕾夏は、密かに顔を見合わせた。
なんだか楽しそうで、どっかピントがずれてるというか、どこまでが本気でどこからが冗談なのか見極め難いというか―――この雰囲気、誰かに似てるな、と会った瞬間から思っていたのだが、それが今、はっきりわかったのだ。
―――親父さん、だよな。
―――うん。お父さんに似てるかも…。
そういえば、以前会った"猫柳"の先輩・勅使河原も、どこかこんな雰囲気があった。カメラ好き共通のタイプなのだろうか? 瑞樹は首を捻り、蕾夏は余計げんなりした。
「でも、君たちは面白いね」
ふいに、時田がそんな事を言った。まるで画家が構図を考える時みたいに、顎に手を置いて、少し離れて瑞樹と蕾夏を交互に見比べながら。
「面白い…ですか?」
「うん。面白い。あの写真見て、その点が凄く気になったんだ」
「???」
「そうだ。これ、見てもらえるかな」
時田はそう言って、山本のデスクの上にあったA4の紙を手に取った。その紙を、紙芝居よろしく、パッと目の前に広げる。
それは、何も書かれていない、ただの白紙だった。
「これ、何に見える?」
「―――コピー用紙ですよね」
「そうだけど、これが“写真”だとしたら?」
「は?」
「この真っ白い紙は、“写真”だ。何を撮った“写真”だと思う? 成田君も蕾夏ちゃんも考えてみて」
白い紙を前に、瑞樹も蕾夏も、唖然として立ち尽くした。なんだか、禅問答のような世界だ。まさか、真っ白の紙を“写真”に見立てろなんてテストが待ち構えてるなんて思わなかった。
わかりません、と答えるのも癪だ。2人は、何も書かれていない白い四角形をじっと見つめた。
1分ほど、見つめ続けただろうか。どちらからともなく、互いの顔をチラリと見遣る。先に口を開いたのは、瑞樹の方だった。
「…光、かな」
「…うん。朝の光」
2人には、その四角い白い世界が、眩しすぎる光でハレーションを起こした景色に見えた。あまりに強い光で、何も見えない―――白一色の世界。
「ほら、面白いだろ?」
何故か満足そうな顔で、時田は紙を机の上に戻して笑った。が、2人には、何が面白いのかさっぱりわからなかった。
「今のは、僕が写真学校の講演会でやった、想像力を試すテストだよ。100人の生徒に回答を貰ったけど、一番多かった回答は“雪景色”だった。“光”だなんて答えた生徒はいなかったよ」
言われてみれば、そうかもしれない。
真っ白な景色、と言われた時、真っ先に「雪景色」を挙げるのは、雪を知る日本人だけに極自然だ。一方、「光」なんて抽象的なものを挙げる人間は、確かに稀だろう。
「“生命”を見た時に僕が感じたものは、一言では説明できないけど…“生命”というタイトルは、まさにピッタリだった。僕が口で説明したら、他の審査員の先生たちも理解してくれたんだけど―――みんな口々に言うんだよね。“この写真は、観念的すぎる”って。同じ高水準にあるなら、もう1点のスナップの方がいいって」
「観念的…」
無意識に、蕾夏が呟いた。ついさっき思い出した、父に言われた言葉―――お前の文章は、観念的すぎる。その符合に、ちょっと驚いた。
「“生命”は、カメラマンも、そこに写ってるモデルも、同じ物を感じて同じ物を捕まえようとしてるように思えた。2人だけにわかる言葉が、そこにあるように見えた。…対話している写真だと思った。なんというか―――蕾夏ちゃんというファインダーを通して見たものを、成田君が写真に撮った、というか。面白い。とても面白いよ」
瑞樹の表情が、少し動いた。
蕾夏というファインダーを通して見た世界―――それは、あの日、屋久島で感じた感覚に、確かに近かった。
蕾夏を見ていると、聴こえる筈のない屋久杉の脈動が瑞樹の体の中にまで響いてくる気がした。そのリアルな感触に、全身が震える位に。
あの時感じたものは、十分撮れたと思う。けれど―――それは、蕾夏と自分しか感じられない物なのだろうか。いくら撮っても、他の人間には理解できない物なんだろうか…口で、説明しないと。
複雑な表情をしている2人を見て、時田は小さく笑った。
「…まぁ、いいじゃないか。君たちの写真は発展途上なんだよ、まだ。僕は、どんなプロの写真より、あの“生命”が好きだよ」
「…つけ上がるんで、あんまり褒めないで下さい」
瑞樹が居心地悪そうにそう言うと、時田はまた楽しげな笑顔を見せた。
「君の写真も面白いし、君自身も面白い。蕾夏ちゃんも面白い。―――ま、いずれ、暇ができたら、一緒に写真でも撮りに行こう。蕾夏ちゃんの事、僕も撮ってみたいしね」
「…は?」
―――プロが、そんな簡単に素人誘っていいのかよ?
眉をひそめる2人をよそに、時田はポン、と瑞樹と蕾夏の肩を叩き、打ち合わせをしていた応接室に戻ろうとした。
「…あの…なんで、そこまで…?」
思わず蕾夏がそう声をかけると、時田は振り返って、ニッ、と笑った。
「僕も、白紙を見て“光が写ってる”って答えた人間だからだよ」
***
「“カフェ・ブルーム”の5千円コースで手を打とう」
「…なんでもいい。勝手に行ってくれ。俺たち、後ろからついてくから」
2人がいない間に、残っていた4人の間ですっかり話し合いはついていたらしい。久保田と佳那子を先頭にして、一行は目的の店まで歩き出した。瑞樹の知らない店名なので、どうせ久保田と佳那子が発見した「酒のうまい店」なのだろう。
元気一杯な前を行く4人に比べ、最後尾を歩く瑞樹と蕾夏は、かなり疲労していた。
たった10分だったが、中身が濃すぎた。もっとも、雲の上の人だった時田郁夫と話した、という段階で既に目一杯だが。
「…瑞樹、どう思う? さっきの話」
「さっきの話って?」
「観念的すぎる、って話」
「―――ああ、あれな」
瑞樹は、少し眉根を寄せ、小さくため息をついた。
「…まぁ、仕方ない。俺が撮りたいもん撮ったら、ああなったんだから。プロなら許されないだろうけど、幸い素人だからな。人にわかる写真撮るより、好きなもん撮ってた方がいい」
「うん、そうなんだけど…」
少し言いよどんだ末、蕾夏は、傍らを歩く瑞樹を見上げた。
「瑞樹は、プロにはならないの?」
「え?」
「カメラマンになりたい、って思わないの?」
真剣な蕾夏の目に、瑞樹も息を呑んだ。
前にも訊かれた質問だ。だが―――あの時と今では、少し、瑞樹の中での感じ方が変わっている。
「―――そりゃ、なれたらいいな、とは思う。時田郁夫の例を考えれば、俺が今からプロ目指したっておかしくはないし。けど…なれないと思う」
「どうして? 才能はあるでしょ? 時田郁夫が認めたし、もう1点の方は準グランプリ候補にあがった位だし」
「いや、写真そのものに自信が無いとか、そういう訳じゃなくて…」
瑞樹は、ちょっと言うべきかどうか迷ったが、思い切って口を開いた。
「…俺、ファインダー通して、人と目を合わせるのがダメなんだ」
思わず、蕾夏の足が止まった。
「…え?」
「被写体の目が見れないんだよ、カメラ構えると」
意外な言葉だった。蕾夏はいつだって、瑞樹にカメラを向けられると、その向こうの鋭い視線を痛いほど肌に感じているのに。普段は、こっちが目を逸らしたくなってしまうほど、真っ直ぐ目を見る人なのに―――その瑞樹が、カメラ越しでは、人の目を見れない?
「どうして?」
訊かずにはいられなかった。が、瑞樹の表情が少し沈んだ気がして、訊くべきではなかったかも、と後悔する。
「あ、べ、別に、言いたくなかったらいいし…」
「―――M4を買った頃、家族の写真撮ったんだよ」
蕾夏の様子に苦笑し、瑞樹はまた歩き出しながら、ためらいがちに話し始めた。
「その頃にはもう、家族はバラバラで―――親父はお袋を繋ぎとめるのに必死だったし、お袋は親父と不倫相手の板ばさみにあって精神不安定になってたし…俺はそんな両親の事を妹に悟られまいとしてた」
蕾夏の目が、大きく見開かれる。
「悟られまいと…って―――じゃあ、その頃の瑞樹は、全部知ってたの? その…」
「知ってたよ。お袋が不倫してるのも、全部」
想像もつかない。瑞樹がライカM4を手に入れたのは、確か10歳の時だと聞いている。10歳―――その頃の蕾夏にとっては、親は絶対的な存在だった。不倫してるとか、離婚するかもしれないとか、そんな事は思いつきもしなかった。
「単なる気まぐれで家族にカメラを向けたけど…ファインダーを覗いて、一瞬、お袋と目が合って―――背筋が、ぞっとした。眩暈と吐き気に耐えながら撮った写真は、当然最悪。……あれ以来、どうしてもダメなんだ」
「……」
「プロなら、何にでもカメラが向けられないとな」
―――教えてよ。なんで、恋愛なんて馬鹿げた事するのか。
寂しげにそう言っていた、“8歳の瑞樹”。年齢不相応に大人だった彼を思い出し、蕾夏は唇を噛んだ。
「…ごめん…そんな話させて」
消え入りそうな声の蕾夏を見下ろして、瑞樹は微かに笑った。
「お前、言ってたじゃん。俺が話したくなるまで待つって。…それが今だっただけだよ。だから、謝るなって」
「…うん」
蕾夏も、微かに笑みを返し、視線を前に移した。
―――瑞樹は、ポートレートを撮る時、その向こうにお母さんの目を見てたんだ…いつも。だから、撮れなかったんだ。
やっと、理由が見えた。切ない理由に、胸が痛む。
けれど、新しい疑問も浮かんでしまった。
―――瑞樹は、ファインダーの向こうのお母さんの目に「何」を見たの…?
とても、大切な疑問のような気がした。
けれど―――到底、訊くことなどできない疑問のような気がした。
| ▲ |
| TOP About Novel Diary Vote BBS Special Link Mail Blog |
| Copyright (C) 2003-2012 Psychedelic Note All rights reserved. since 2003.12.22 |